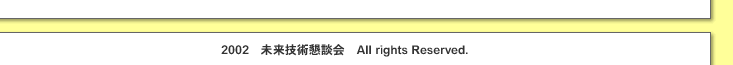|
【月尾委員】
茅先生は大先輩なので反論しにくいのだが、これは、話を簡単にするためにこのように説明しているのだが、例えば、新聞というものを電子新聞に置きかえるという動きが始まっているが、トータルエネルギーで計算すると、同じ情報を家まで送るのに、紙の新聞と比べ、電子新聞のエネルギー消費は大体 20分の1だと言われている。
それから、日本の紙のうち、厚紙も入れて大体10%が新聞紙を使っているということである。
そうすると、もし多くの人が電子新聞を読むということになれば、新聞が使っているエネルギーは一気に減ると同時に、紙の消費もかなり減らせるということである。
その技術が発展途上国へ先に普及すれば、発展途上国の方がより高い生活水準を得て、なおかつ新しいパラダイムで生活出来るという可能性があると思う。
そのようなことが現在いろいろと起こっており、例えば中国が世界で一番多数の携帯電話を所有している国になった。
人口当たりではまだまだ低いが、量的には1番になったということである。
それはなぜかというと、古い固定電話が普及していなかったため、一気に携帯電話が普及したからである。
衛星放送の受信者数も中国の方が圧倒的に多い。
これも隅々まで鉄塔を建てる訳にいかないため、衛星で送ってしまうということになったのである。
すべての技術がそうであるとは言わないが、先進国が新しいパラダイムに転換した技術を積極的に途上国に提供することによって、茅先生がご指摘になったような問題の解決も可能ではないかと思う。
そういう側面もあると信じ、先進国の責務を果たしていったらいい。
【白石委員】
直接的な質問ではなく雑駁な感想だが、22世紀、100年後を考えてみると、人口も半減しているだろうし、少子化が進むことによって日本の人口などはトキのレベルになっているかも知れない。
民族や国籍、宗教を融合しているという前提でとらえる必要があるということを考えた場合、この場で性別の比率で、且つこうした職業の構成のままで議論していくことが、国民生活の未来像を語るに値するかどうかということを、まず私は考えた。
太陽系以外の惑星群が見つかり、先進諸国の人は宇宙に移住しているかもしれない。
地球上は非常に後進国で、人口爆発、環境悪化が進み、もはや大多数の人は地球にいないかもしれないという、こういう前提も置く必要があるのではないか。
今を前提として考えてはいけない。
ここを月尾先生はおっしゃったのだが、私もこの点には大賛成である。
2点目としては、参考資料として出していただいている技術予測調査は、非常に興味深い冊子であり、それぞれ各分野の中で今後こうした課題が重要になるだろうということをうまく整理されているが、今ある状況、今日的状況をどう課題解決していくか。
このようなスタートを切った場合には、あまり思い切った未来技術というのは予測出来ないだろう。
むしろ私達がこのような生活をしたい、将来的にどのような生活を望む、という中で、どのような技術について重点的な対応が求められるのかということで、希望ありきで今から派生的に現状を伸ばしていくのではなく、どのような生活をしたいのか、こういうところに議論のスタート地点を置くべきだろう。
また、個別の技術開発であるとか、個々の分野について重点課題が出ているが、これを統合していくことが重要であろう。
具体的には、1つある分野での功績や技術の進展などが、また別の分野でのネガティブイフェクトをもたらす必要もある。
個々に議論をしていてはいけないのではないか。こうした領域を統合してどのような生活が実現するのか。
個別に考えていくのではなく、私達の希望する生活を実現する上で、この分野のこれと、この分野のこれと、この分野のこれとを融合させていくべきだという、統合化の視点が必要ではないかと感じた。
【高木政務官】
今の白石さんの言われるメンバーの話で、佐藤技術審議官からも言われましたが、話を聞いたときに同じような意見を申し上げた。
そのとき、例えばどうしても役所がこういうことを始めると、学者の先生方をまずターゲットにしてお招きするというパターンが多いと。
その中で佐藤技術審議官から、例えば漫画家であるとか、いろいろな職種の方々を2回目以降お呼びしましょうという、そういう発想があるということをどうか知っていただきたい。
その上でまた価値観の話で大変恐縮だが、先程、茅先生がAとBに分け過ぎだとおっしゃったが、僕もそれは少し感じたのだが、ただ自分達の生活を振り返ると、多様な価値観は必要であると、僕ら政治家も結構いろいろなところで言っている。
言っていながら、やっていることは何かというと、統治するという発想でいうと、1つの価値観にまとめたがる。
だから、教育もそうであるし、逆に一般市民の方々と良く話す機会が多く、例えば今の教育は良くない、偏差値教育は良くないとみんな言っているのだが、うちの子供だけは塾に行かせようと言う。
その偏差値教育にどっぷりと染まっている。多様な価値観は今芽生えている。
実際、若い世代の人達はいろいろなことをやっているし、学校を卒業したからといって就職することが すべて良しとはしない。
しかし、政府の側から言うと、雇用の問題、失業率の問題でフリーターはどうしていくのかなどと言えば、それもまたすぐ問題にしてしまう。
逆に言うと、少しほったらかすという発想が必要なのではと考えたこともあったが、その辺りのところをどのようにお考えなのか。
【月尾委員】
高木政務官は東京選出であり、私も東京にいるのだが、週末に全国いろいろなところへ行っている。
特に佐藤副大臣の地元ではカヌー、スキーなどで遊ばせていただいているのだが、地方へ行くと、悠々と生活している人が沢山おられる。
大学を途中でやめて北海道の山奥へ来て、スキーのガイドや登山のガイドをして生活している。
そのような方々が既に沢山出現してきているのだが、政治なのか、行政なのか、新聞なのか分からないが、その変化を上手く社会に伝えるような仕組みがなく、東京の価値観で日本中を憶測したりしていくということが、全体として行われ過ぎている。
行政がやるのが良いのか、マスコミがやるのが良いのか分からないが、いろいろな価値観で生活や仕事をしている人がいるということを国民が知り、自信を持ってそのような生活を選べるということを進めていけばいい。行政も政治も一律にしたがるという仕組みがあり過ぎるのだろう。
【森地座長】
月尾先生は建築家であり、都市計画家であるのだが、例えば昨日、大東島の話をたまたましたのだが、1,400人程が住んでいる6キロ四方程度のちっぽけな島で、サトウキビだけつくっている。
断崖絶壁で岸壁はあるのだが、人間もつり上げてしか上陸出来ない、船が着けないという、こういう社会である。
それはともかくとして、かつてはそこに外国人が働きに来て農業を行い、農家があり、製糖工場があり、気象庁があり、ある種の階層社会があり、大変苦しかったとおっしゃるのだが、そこに働きに来ている外国の労働者、台湾とか中国の人達がそこに何かを求めてきていた。
つまり、今、月尾さんが知床に行ってカヌーをやる、或いはどこかに行くときのモビリティというのは、ある種のクローズドされた中のモビリティであったり、豊かな人のモビリティ、こういう社会なのだが、片や発展途上国の人達についてあるところでカットをするというのは、大半の国の意識になっている。片や翻って、かつての北海道と韓国、台湾を比べたらどちらが豊かだったかというと、圧倒的に北海道が豊かだったのだが、今、独立させたら違う産業構造になってしまう。
つまり、国家とは何かという議論がほとんど政治の社会で自由であるとか、民族であるとか、そのようなところで論じられているのだが、我々は地域であるとか、生活であるとかを考えたときに、エリアとしての国家あるいは動くモビリティとしての人間というものを、一体どのような格好の規範として考えていろいろなものをデザインするのか。
エネルギーの問題も同じだろう。
これについては相変わらず今のような格好で考えておくのか、あるいはEUが次のステップへ移行してどうなるのかにもかなり関わる話だが、月尾先生のここで議論しておられる話の前提としての地域や国というのは、一体どのような前提に立っておられるのか。発展途上国を主として、人口はどのように考えられますか、ということと絡めてお答えいただきたい。
【月尾委員】
私が説明した幾つかの問題は世界規模の問題である。
これは、日本だけが努力してもダメで、地球温暖化ということで言えば、日本がどれだけ炭酸ガスの排出を減らしても、アメリカが勝手なことやれば一番影響力が大きいので、その影響でダメになってしまう。
そのため、積極的に京都議定書を推進することも必要であるが、一方で日本を守るということも考えれば良い。
例えば水や食料の問題では、世界に飢えた人がいるときに日本だけ贅沢してどうかという議論もあるのだが、役所とか政治という立場では、まず日本をどうするかということを考えるべきである。
【森地座長】
それはエリアとしての日本ということなのか。
【月尾委員】
民族と言っても良いが、エリアとしての日本である。
これから地方分権の議論が進んでいくだろうが、環境問題も、情報という問題も、文化という問題も日本一律ではなく、それぞれの地域固有の問題がある。
そうすると、都道府県が良いのか、道州制が良いのか、国が行おうとしている市町村合併で1,000程度にするのが良いのかという議論があるが、小さい単位でも対応出来る問題もある。
例えば、食料について地産地消という動きが全国で出てきているが、ある地域で有り余るほどの食料をつくり、それを国中に売りまくるとか、世界に売るということではなく、ある流通の範囲の中で必要なものを生産し、そこで消費してしまうという考え方も出てきたということである。
そうすると、狂牛病のような問題もあまり発生しないだろうし、ポストハーベストのような問題も発生しないということになる。
小さい単位で循環とか、完結しているような社会を構築しようという動きも出てくる。
国の政策として考えると、日本という国がどのように自立して行くのか、場合によっては食料の安全保障を守れるか、水の安全保障を守れるか、という単位で考えざるを得ない。
人道的に貧しい国をどうするのかという話も必ず出てくるが、それが救えればそれに越したことはないが、難しい問題であるので、まず日本という領土なり、国民という問題で考えていくというのが研究会での目的ではないかと思う。
【佐藤副大臣】
僕には、日本がこれだけ発展したにも関わらず、どうも一人一人は幸せでないような気がしている。
世界中を見ても、それぞれの国がみんな幸せ感に浸っているかというと、どうもそうではないような気がしている。
そして、いろいろ不幸な出来事が起きている。
未来を見るためには、自分達がこれまで築いてきた価値観というものをもう1回見直す必要がある。その上で、それを未来に活かさなければ、本当の幸せ感というものは掴めないのではないか。
どんなに技術を磨こうが、どんなに新しいことを発見しようが、やはり根本になるのは民族の持っているアイデンティティーというか、その国らしさである。それぞれの国がそれぞれの限定された中で自分達の積み重ねてきたものを1回見直してみるというようなことが根本になかったため、どんなに技術を発展させても本当の幸せ感は得られなかったのだろう。
だから、私達の持っている歴史的、伝統的につくり上げてきた美徳であるとか、いろいろな価値観をもう1回見直してみる必要がある。
僕は、観光について、これまで一所懸命勉強してきたのだが、観光の基本的な問題として、その地域に住んでいる人達がこの町に住んで良かったという価値観、幸せ感を感じないところには誰も人は来てくれないので、そのような町、地域をつくり上げていこうと考えている。
それぞれの地域のアイデンティティーをつくることにより、全体としての美しい日本が出来上がると考えており、国土交通省としても、観光というものを特にこれから重要な政策として実施して行こうと省内で勉強を開始している。
その辺りの精神的な回復というものが、例えば、家族の絆の回復であるとか、友情の回復であるとかが、技術的なものに結びつき、日本全体の一人一人の幸せ感というのが出来ていくような気がしているのだが、月尾先生は、いかがお考えだろうか。
【月尾委員】
おっしゃるとおりで、政治家の方々に是非読んでいただきたいと申し上げている本がある。
「逝きし世の面影」という本だが、現在71歳になられた渡辺京二さんという方がライフワークとして書かれた本である。
これは、江戸末期から明治初期に外国から来た人の記録を調べた本である。
例えばタウンゼント・ハリスという外交官が、外交日記を残しているし、その通訳のヘンリー・ヒュースケンという人が記録を残したりしている。
また、イザベラ・バードという人が東北を1人で旅行した様子を本国への手紙に記している。
そういう膨大な記録を読まれ、当時の日本が外国の人から見てどういう世界だったかということを書かれた本である。
要点は2点あり、1点は日本は地球の上に現存しているただ1つの極楽だと、ほとんどの外国人が感じていたということである。
もう1点は、驚くべきことであるが、この極楽のような日本が西欧の文明を導入することによって滅びていくと思うと悲しい、ということを百数十年前に何人かの外国人が言っているということである。
例えば、イザベラ・バードというイギリスの女性が江戸から北海道まで馬に乗って1人で旅行し、山形の宿に到着してみると、馬の腹帯がなくなっていた。それを旅館の主人に言ったら、提灯を持って山道を戻って行き、探して持ってきてくれた。
それでチップをやろうとしたら、そんなもの要りません、私はお客さんが無事次の宿へ着くまで面倒を見るのが仕事です、と言ったであるというような、現在では無くなってしまったたような風習が書いてあり、これらが西洋文明を入れることによってなくなっていくだろう、というように書かれている。
あまり回顧主義のようなことを言っていても仕方がないが、佐藤副大臣が言われたように、日本が持っていた良さというものを自信を持って見直し、それを国際社会に理解してもらう努力を実践していかなければならない。
ひたすらグローバルスタンダードの中で競争して行くということは、仮に日本が勝ったとしても不幸な国も出てくる。
だから、正に地域が自信を持てるような国、ひいてはそれが日本という国の自信になるという理念で技術開発も行っていかないと、日本の存在意義というものも問われるのではないかと思っている。
技術の話ではなくて申し訳ないが、そのような本もお読みいただければ、何をやらなければいけないかということも見えてくるのではないかと思っている。
【森地座長】
まだいろいろお話はあろうかと思うが、次回以降もあるので、そこにとっておきたいと思う。
ショートスピーチのジャンルについては、事務局の方でいろいろ考えていただいているが、ジャンル自身が動いている、そういう社会なので、先生方からも例えばこういう方のお話を聞くことは大変役に立つということがあれば、是非お教えいただきたい。
8.今後の日程
【望月技術調査課長】
次回は3月12日火曜日の17時から開催する。東京海上研究所の下河辺先生と畑村委員にスピーチをしていただく予定になっている。場所等詳細については、別途ご案内させていただく。
9.閉会
|