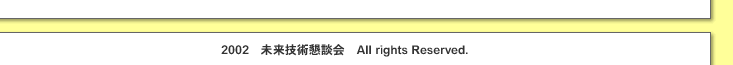|
|
| 7.ディスカッション 【森地座長】 スピーチをしていただいた先生も含めて、ご自由にご質問、ご意見、ご発言をいただきたい。お役所の方々もご遠慮なく発言していただきたい。  【畑村委員】 【畑村委員】 先程の月尾先生の話の中にあったいろいろなものが変わっていくぞというところの、どれについても変わっていくぞというのを皆が認め、それに元気を出してというよりも、本当に勇気を出して変わらないといけないのではないか、というのが一番強く感じることである。それで、従来型で考えているやり方だけでは、どう工夫しても上手くいかないのではないかということを感じることが多い。 今日の話には全然出てこなかったが、例えばこういうところのディスプレイをどうつくるか、などというときに、今、液晶やプラズマディスプレイのようなものをつくることが、除去加工以外の方法では結局出来ないでいる。 そうすると、どうやっても大面積のものをつくるのは無理であり、安くならないのではないか。それから、環境負荷が大き過ぎて情報化の一番最後の方、ディスプレイのところがダメになってしまうのではないか、という感じがしている。 そうなると、従来型の半導体のような技術ではなく、全然違う印刷のようなものでつくであるとか、全く違う発想のものがどこかで出てこないとブレークスルー出来ないのではないだろうか。 そのような現状を見ると、先程のような大きく何かで変わるぞ、という物の見方を先に行う必要があるのではないかということを、今の話を聞いて感じた。 もう1つは、茅先生のおっしゃったとおりだと思うのは、省エネルギーなどと言うと、カッコ良い話が沢山出てくるが、本当かなというウソくさい感じがいつもしていたのだが、それが実際どの程度ウソくさいかということを、きちんと言っていただいたのですっきりした。 【茅氏】 すっきりされただけでは困るので、それを突破して答えを出さなければならないと思っているのだが、どうも人間というのは、本来楽観派と悲観派とがあるような気がする。 私は30年前、ローマクラブの活動に参加したが、そのせいかもしれないが、考えることがどうもやや悲観的である。 だから、私の話だけで世の中を悲観されるのも困るので、そのあたりはご配慮いただきたい。  【高木政務官】 【高木政務官】 月尾先生がお話しされた中で興味深かったのは、インナーフロンティアの話で、未来技術懇談会ということで、未来の技術はどうなるかというのがテーマなのだろうが、今までの歴史をずっと振り返ってみると、便利は果たして普遍的な価値だったのかという、そういう部分にまで問いかけていく必要があるのだろう。 月尾先生は、最後にフロンティア開拓の要点ということで3つ挙げられていて、過去の常識の廃棄みたいなことを言われた。 19世紀から20世紀になるときに報知新聞に記載された記事のように、こんな未来になるであろうと考えて、ある程度実現してきた。 そこに生きてきた人々と21世紀になった今の人々と、実感としてどちらが幸せなのだろうか。幸福だとか、そういう価値観というのは人それぞれ、ここにいるメンバーでもみんな違うだろう。 それをある程度集約、僕は集約しなくて良いだろうと考えているのだが、役所の立場として考えてみると、それなりの1つの価値観を持って実行していく必要があるので、そのような中でのインナーフロンティアのところをずっと行っていくと、価値観の問題、価値基準の問題、この辺りをしっかりしないと、未来技術として何が良いのだろう、ということがはっきりしてこないと感じているが、その辺りはどのようにお考えなのか。 【月尾委員】 政府もIT社会の実現を推進しておられるが、これが社会の価値を非常に変えると思っている。 物と情報の価値はどう違うのかというと、物は同じものが増えていけば、価値が増えると考えられている。 自動車を1台所有しているより2台所有している方が夫婦で使えて便利であるとか、子供も使えるということであった。 しかし、情報は同じものが沢山あっても価値が増えない。 例えば、同じ本を夫婦でたまたま買ってしまった場合、夫婦喧嘩のもとになってしまう。 別の本が2冊あった方が価値が高いということである。 これまでの社会は、高木政務官のご指摘のように、同じ尺度で比較し過ぎてきたのだろう。典型的なのが、役所が47都道府県を並べてどこが上位で、どこが下位だという評価をし、下位になったところは文句を言ってきた。これまでは同じ尺度で一列に並べるということが重要であったが、それはご指摘のとおりに変えなければいけないと思う。 これはおもしろおかしく言っているのだが、かつては隣の家がピアノを買ったらうちもピアノだということで、一生懸命働いて、それを目標にしてきたのだが、現状では日本のピアノは余っており、中古を発展途上国に輸出しているという状況になってしまった。 これからは、隣がピアノならうちは尺八だとか、隣が2台目の自動車を買ったら、うちは2台目の自転車だというようなことで、違うことに価値があるという社会をつくっていくということが、IT社会が目指すべき大事なことだと考えており、ご指摘のとおりである。 遡ってみると、産業革命が起きてエネルギーというものが社会の重要な原理になったときに、効率という概念が社会にもたらされ、効率を上げていくということが良いのだと納得した。 だから、熱心に働いて社会の効率を上げてきたのだが、もうそれでは幸福にはなれない、ということが分かってきたということである。 情報は効率では計れないという性質を持ったものであり、それが社会の中心になってきたので、別の価値観を入れろということである。 具体的にどうするかは難しいが、一言で言えば、多様な価値観があるということが、社会がより豊かだと思うべきであり、基本的にはご指摘のとおりである。 【森地座長】 似たような話だが、遊びであるとか、一国ではなくて世界規模の人口であるとか、例えば教育もいわゆる今の文部科学省の教育ではなく、ワンダーフォーゲルやボーイスカウトがある時期にぱっと出てきて、またなくなっていくとか、このようなメインの生産、消費というところではない、その辺りは月尾先生はどのようにお考えなのか。 【月尾委員】 遊びでいえば、日本のロボット技術は、かつては生産ロボットをひたすらつくり世界一になったが、最近流行しているロボットでは、アイボとか、アシモが高い評価を受けている。 あれは何かというと、癒しだと言われている。 それから、これまでは真っすぐな道路を目的地までつくるという目標で道路をつくってきたが、最近注目を浴びている道路は、熊野古道のように、以前使われていたような道路を発掘して苦労して歩くということに、多くの人の関心が集まっている。 熊野古道は、5年前には年間3,000人しか来なかったのが、現在は14万人来るようになったそうである。 それは、目的地へ早く着けばいいという工業社会の原理ではない社会が動き始めたということで、遊びであるとか、癒しであるというものが高い価値観を持つようになったということであろう。 【茅氏】 この月尾さんのお話というのはそれぞれ大変興味深いのだが、私が1つ気になるのは、AかBかという議論になっているという点である。 これについては、月尾さんの話のときに私はいつも反論するのだが、今回も多少そのような面があり、例えば拡大の考え方や縮小の世界といった考え方は、確かに循環型社会といった議論から見るとそのように感じるのである。 しかし一方において、世界の中にはまだまだ拡大を志向している人々が沢山いる訳である。 中国を見れば一番簡単だが、そういったときに一方的な転換というのはあり得なく、拡大と縮小の両方をいかに共存させていくかということがむしろ問題ではないか。 例えば1970年代にスモール・イズ・ビューティフルという言葉が流行し、エネルギーでいえばソフトエナジーパスというのが登場し、小さいとか、あるいはソフトということがハード、ラージということに対する対比として言われていた。 しかし、現実としてどうかといえば、現実は依然としてこのようなものの組み合わせで動いている。 決して一方だけが勝っている訳ではない。 我々のエネルギーの世界においても、大規模な電源の持つスケールメリットというのは依然として高く、如何にして分散電源のようなものとコンバインするかということが現在の最大の問題点になっている。 分散電源ですべてが出来てしまうというコンセプトは、正直言って我々にはほとんどないのである。 そういった意味で、月尾さんのこの議論というのはおもしろいが、あまりにも問題をAからBへというふうに見過ぎていないか。 この間をいかにしてコンバインするかという側面が、今後の社会の中では大事なポイントであると思う。 ただし、話をきれいにするためにはこの形の方がベターなのだろうが、それだとややミスリーディングになる点があるのではないかというのが私の意見である。 多分、月尾さんから反論があるだろう。 |