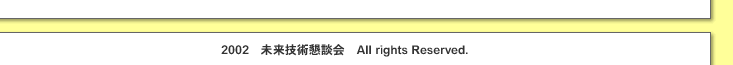|
|
【茅氏】 今の月尾さんのお話というのは総合的な話であったが、多分、この後のショートスピーチで、いろいろ個別の技術についての話が出てくるのだろう。 多分、私はその一番バッターであるということだろう。 お手元にレジュメを用意したが、私がお話ししようというのは、特にエネルギーに関連した技術でどのようなことが考えられているか、どのような技術開発が重要か、ということについて話をさせていただく。 最初に、その背景として何が今一番要求されているかということだが、エネルギー環境問題というと、月尾さんのお話のように、必ず資源と環境という2つが出てくる。 その場合、資源については、化石燃料は有限だ、だから、非化石燃料に早く動かねばいけないという議論が出てくる訳であり、これは正しいのだが、ただ時間的にどうかということになると、現段階ではむしろその議論よりも、温暖化にどう対応するのか、そのことの制約の方がはるかに厳しいということが最初に申し上げたい点である。 資源制約として、月尾さんのお話の中でいろいろな化石燃料資源の耐用年数という話があったが、これについては、現段階においても不確定性が非常に多く、特に業界では、天然ガス、石炭については、かなり楽観論が従来に比べて多くなっているという状況である。 石油についてはまだ怪しげな面がいろいろとあるが、21世紀の前半で生産がピークを迎えるのではないかという見通しが比較的多いので、この面では石油というのはかなり問題であるという気がするが、他の資源に関してはむしろ楽観論のほうが強い状況である。 一方、ここに出ているのは、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の作成した、二酸化炭素の大気中の濃度を安定化するためには排出をどの程度にしなければならないかというシミュレーションの絵だが、例えばよく言われているのが、この下から2番目の線である。 これは大気中の濃度を産業革命以前の自然のレベル、280ppmの約2倍の550ppmに抑えるとすればどの程度のカーブになるかということで、これはいろいろとあり得るが、点線と実線と2つの例を示している。 これは世界全体の300年に渡る絵であるが、ポイントは、長期的に見れば現在のレベルの数分の1まで下げる必要があるということと、そのために、現在発展途上国の経済発展もあり、伸びているという状況がすぐには変えられないことを勘定に入れると、少なくとも今世紀中には現在レベル位まで落とし、それから更に下げていかなければならないということになる。 550ppmがどのようなレベルであるかということについては議論があるが、これから先の温暖化の進行はある程度やむを得ない。 しかし、この程度なら何とか我慢し切れるのではないか、とよく言われている線である。 その次の絵は、それに対応してどの程度のことを行う必要があるのかについて、エネルギーの側面から見たものである。下は、今申し上げた550ppm安定化といった場合に、どのようなCO2の排出カーブがあり得るかという絵であり、それに対し一番上の線は、対策を行わない場合、この程度はCO2が増えるという絵である。 20世紀から21世紀の範囲で排出量の安定化が非常に大きなターゲットであるということがお分かりいただけるかと思う。特に最後のほうを見ると、一番上の線に対して望まれるCO2の排出量というのは数分の1になる。その間をいろいろなエネルギーの手段で埋める必要があるため、相当大変だということがお分かりいただけるだろう。 これに対する答えは、当然技術だけではなく社会だということになるのだが、ここでは技術だけでどういう考え方があり得るかということだが、これは私自身がいつも言っていることだが、このような3つのタイプの技術が必要ではないか。 1つは、現在も有効だが将来も有効であり続ける。 つまり開発を続けていくべきであり、ここでは仮に持続的技術と呼んでいる。 これにおいては省エネルギー技術がもちろん中心だが、それ以外に分散型の自然エネルギーの利用なども1つのポイントになるだろう。 しかし、これだけで答えが出るならば簡単なのだが、先程のようなターゲットを実現するとなるとこれではとても難しい。 そこで長期の技術が必要であるということで、これはいろいろなものが考えられるが、現在は全くないのだが長期のスパンで考えると、今までと違ったインパクトの大きいものを考えなければいけないということで、そこに例が出ている。 3番目は、1番と2番だけでは答えにならない、どうしても間を埋める技術が必要であるということで、中間期的技術と書いてあるのだが、これは長期的に望ましいものとは言い切れない。 つまり、本当はやらなくて済むのであればやらない方が良いという技術だが、間を埋める技術としてこれがなければ、例えば京都議定書、あるいはその後のターゲットは達成出来そうにないということで取り上げるものであり、二酸化炭素の回収処理というのはその典型例だろう。 そして、この中のどれに属するかという点で意見が分かれるのが原子力であり、これは現在、既にかなりの大きなインパクトを持っているが、これを中間期技術と見るか、あるいは長期的に開発すべき技術と見るかは、人によって考え方が違うということである。 この後は、このようなものそれぞれの例について話をする。 まず最初は省エネルギーについて。これは非常に単純な絵で、現在発電で使われているコンバインドサイクル、それから下の方にはいわゆるコジェネレーション、熱電併給の原理のみを示している。 これは現在、天然ガスでは非常に普遍的に使われている方法であり、アメリカの統計によると、世界中に建設中の天然ガス発電所は、大体7割から8割がコンバインドサイクルになっているということである。 ご承知のように、普通の天然ガス発電の場合では、これを単にボイラーで燃やし、そこで蒸気タービンを回すので、効率はせいぜい40%程度ということになるのだが、絵に示すような形で上にガスタービンを載せた場合、現状では一番高いレベルが1,380度位の温度レベルが保てるが、この形のタイプでは、現在運転しているものでも大体50%程度の熱効率である。これはいわゆるHHV(高位発熱量)ベースの計算だが、この程度の数値が達成出来ている。 例えば、現在建設中である東京電力富津火力のコンバインドサイクル、これは2004年の予定だが、これはターゲットが53%になっており、従来の火力発電に比べ約3割効率が高いということになる。 このような意味で、効率を上げるという努力が供給側の技術としてかなり伸びているということが言えるが、今一番注目されているのは燃料電池、あるいはマイクロタービンといった分散電源である。 この燃料電池、マイクロタービンという話はここ10年の話題であり、昨年も「マイクロパワー」という本が出版された。これはIT革命に次ぐ革命を起こすという、言うならば少々センセーショナルな言い方で書いている。私は、そこまではかなり疑問を持っているが、現段階でこれが世間の注目を浴びていることはご承知のとおりである。 これが期待されている理由というのは、従来と比べてかなり小型で、安定的に動かすことの出来る固体高分子型燃料電池、俗にPEMと呼んでいるが、これがいろいろなものの進歩により非常に可能性が大きくなった。特に小型であるために、自動車に載せる、一般家庭で使用するといった需要が期待出来るということが第1の理由である。 一方において、マイクロタービンもかなり小型になってきている。これは材料と同時に、例えば空気軸受(エアーベアリング)の採用、その他で高速回転が可能になったということもあり、低コスト化が進んだ。アメリカではキロワット当たり10万円を切る値段のマイクロタービンが少なくともカタログのレベルでは登場している。 このようなことから、これならば使えるのではないかということで各方面で期待が持たれている。これは小型の分散電源なので、うまく使えば家庭その他で、その廃熱で熱供給が出来る。そうなると、全体としてエネルギーが無駄なく使えることになり、大変具合が良いという点がある。 ところが、どの程度の速度で低コスト化が進むのかという問題点がある。 例えば燃料電池、これについては現在ターゲットが一応作られている。 一昨年から昨年にかけて、経済産業省において資源エネルギー庁の中に懇談会が設置され、私が座長を務めた。 目標設定について検討した結果、例えばコストでは車の場合キロワット当たり5,000円、定置型の場合にはキロワット当たり数万円と、かなり高いターゲットになっている。 しかし、現在はキロワット当たり数十万円であり、1桁から2桁という大きな格差をどのようにして埋めるかという点が問題である。 もちろんこれに関しては、各方面で大変な技術開発を行っているが、触媒、交換膜など大きな問題を持っており、簡単にそれが克服出来るかという点が危惧される。 ともすればこのような開発に携わる技術屋というのは、コンサーバティブになりがちであるということがよく言われるが、このギャップというのは大変大きく、世の中で騒がれているほどうまく低コスト化が進むかという点が一番大きな問題ではないか。 定置型電源としては、発電効率の向上が必須条件となる。現在の段階ではまだ低いが、なぜそれが必要かというと、先程のコンバインドサイクルで申し上げたように、電力系統につながれている大型電源の場合には、相当に高い発電効率が現実に実現しているのである。 従って、定置型の電源として低い効率でこれを動かすということになると、熱の利用が相当に上手くない限りは、コスト的にもエネルギー的にも太刀打ちが出来ない。 例えば、マイクロタービンなどは20%台の効率になってしまうのだが、この段階では長期的には大型の 電源にはかなわないということになる。 そのため、この効率を大幅に上げる必要がある。 私は、コジェネレーションの効用をあまり過大評価すべきではなく、むしろ発電のみで対抗出来る程度になるのが前提だと考えているが、その場合には送配電の不要性ということを考えてみても、そこにある程度の効率が必要であろう。 ここに示したのは国の燃料電池の開発目標であるが、車両用、定置型のいずれも、発電効率は55%以上である。 これはやはりHHVベースだが、現在つくっている大型コンバインドサイクルが53%ということであり、いかにターゲットが高いかがお分かりいただけるだろう。ここでは耐久性、コストということが大きな問題であり、これらをいかに克服するのかということが将来のカギになる。 もう1つの話題は、自然エネルギーの利用である。 これは、二酸化炭素の呪縛がないということもあり、現在、開発について非常に世の中の注目を集めているが、問題点は、このような方法で本当にどこまでこれが我々にエネルギーを与えてくれるか、コストが下がるのか、という2点である。 現在これを推進する方式として、以下の2つの方式が提案されている。 1番は需要側の自由意思による方式で、グリーン料金を払う、いわば一種の寄付行為である。 ただし、これはなかなか日本では通用しないようであり、東京電力管内においても、現在は数千件の実施に留まっているということで、大変残念である。 従って、これは今度の国会に出す予定のようであるが、RPS(再生可能エネルギー証書)と俗称しているが、グリーン証書というのがあり、自然エネルギーの一定量を電力事業者、普通の電力会社がこれを必ず買うという制度がある。 これは、一定の程度の自然エネルギーを電力事業者が強制的に作らされるということである。 このような制度は、既にヨーロッパ、例えばデンマーク等では実施されている。 この制度を導入する際には、ある程度の将来にはこのグリーン証書を持たなくても十分このようなものが経済的に引き合う段階になる、という1つの前提条件がある。 その段階では、このようなグリーン証書の値段が実質的にゼロになるため、自然消滅することを当てにしているのだが、そこまでに、実際にどの程度時間がかかるのかということである。 現実には太陽光発電は、現在キロワットアワーベースで40円から50円という値段である。 商用の発電というのは、大体10円を切る値段で作っており、一体どの程度の時間でこのコストが下がるのだろうか。 生産規模の拡大によってコストが下がるということが期待されているが、現段階における生産者側の予測では、普通の規模拡大のみでは生産コストが少なくとも現在の電力のコストまでは下がらないということになっており、そのギャップをどうするかという問題が依然として残っている。 その意味で、今後を考えた場合どうするかという点は大きな問題として残っていると言える。 また、この自然エネルギーは、あくまでも補助的なものであり、本質的にこれが日本のエネルギーを支えている段階にはならないというのが一般の了解であり、その理由は2つある。 1つは物理的なポテンシャルが低いことである。 これは、例えば日本の住宅の屋根全部を使って太陽光発電をしたと仮定しても、実は数千万キロワット程度の容量しか出ないのである。 これは多いように見えるが、実際には稼働率が普通の商用発電の大体5分の1程度であり、比率的に言うと、半分の屋根を使い、しかもそれが全部南向きと仮定した場合でも、日本の電力の1割程度しか供給出来ないというのが現実である。このことより、これだけに頼るのは無理だということが理解出来るであろう。 もう1つは出力の時間変動が大きいため、需要に対応するためには、電力系統側で大幅なバックアップが必要となることである。 つまり、太陽光発電あるいは風力発電といったものはそれ独自で電力系統の供給源になることが出来ないため、かなり大きなバックアップ電源が必要となる。そういった意味で、これにはかなり限度があると言わざるを得ない。 これが現状だが、今の段階でまだこんな程度だと。つまり非常に小さいということを申し上げた訳である。 次に、長期の技術をどうしたら良いのかということだが、先程申し上げたように、長期的には化石燃料離れをする必要があるということになると、必然的に太陽になる。 太陽エネルギーを使う、しかも大規模に使うということになると、先程申し上げたように、地上で太陽光、風力により供給するというのは、所詮補助エネルギーにしかならないため、別な方法を考える必要がある。 別な方法としては次の2つが考えられる。1つは宇宙空間におけるエネルギーの再使用、もう1つはバイオマスといった形で、一度別のエネルギー形態に変換した後、これを大量に集めてエネルギー化するといった方法である。 バイオマスは既に途上国である程度使われているが、それに対して全く違う方法として考えられるのが宇宙発電である。 この絵はコンセプトを示したものだが、宇宙空間に太陽電池の帆を上げる。地球によって蝕が起るのを避けるために、普通3万キロぐらいに上げるというのがコンセプトだが、そこで発電した電力をマイクロ波に変換して地上に送り、整流し、商用周波に直して供給するといった方式である。 アイディアは今から40年程前、アポロ時代にアメリカで出たのだが、現実には、とてつもない考え方であるということで、SF視されてきたという状況であった。 しかし、長期的に考えると、この方法は常時安定した電力を供給出来る。しかもスペースの制約がなく、宇宙空間であると地上の大体5倍程度の平均密度でエネルギーを得ることが可能であるため、超長期にはこの方式を検討すべきではないかという見方が欧米でも日本でも出てきている。 このため、アメリカのNASAでは1998年から、日本では、宇宙開発事業団、経済産業省が21世紀に入り、部分的な予備的なところから予算を計上し始めるという状況である。 現在、日本の予算規模は、それぞれの省庁で1億円以内とまだ小さいものだが、今後、このような長期の問題については、遠からず本格的な対応が考えられるであろう。現在、核融合について新しい実験炉ITER設置の問題で日本が融資する、という話が出ているが、核融合の場合には、実用炉が出来るという想定が2040年である。しかし、この最初の技術のスタートは1960年であり、80年のスパンがかかっている。そのようなことを考えれば、ここにあるような考え方も今から手を打つということが意味があると私は考えている。 もう1つ中間期技術として、二酸化炭素の回収処理について考える必要がある。それが、発電所あるいは製鉄所の排煙からCO2を回収してどこかに貯留する、あるいは廃棄する、といった方法である。これは一見非常に非現実的に見える。というのは、二酸化炭素の量というのが非常に多い。例えば1つの100万キロの石炭火力をフル稼働した場合、年間数百万トンのCO2が排出される。しかも常温で気体であるため、どうやって捨てるのかということになり、また回収も大変だということを考えがちである。 しかしながら、現実にはかなり行われている方法である。回収するのは排煙からで、一般に良く行われるのは化学吸収である。モノエタノールアミンを使うのが最も一般的であるが、これで吸収し、吸収した後は加温して取り出すという方法である。これについては、既に炭酸飲料用の二酸化炭素を排煙から取り出すということがアメリカで実施されている。 また、今度は逆にそれを捨てる方であるが、これもやはりアメリカで、炭酸ガス田の炭酸ガスを取り出して油田の中に押し込む。そして油を増収するのに使用する、俗にEORと呼んでいるが、このようなタイプの技術が行われている。 これらの技術の延長として、最近は現実にこれに近いことを行うということが既に欧米でスタートしている。例えば、北海油田では天然ガス田の中に数%含まれる二酸化炭素を回収し、その下の帯水層に押し込むというのが1997年から行われており、現在でも順調に稼働している。これは完全に商用ベースで行われているが、その理由は、ノルウェーが大体カーボン1トン当たり1万円から2万円という額の炭素税をかけているため、これで十分引き合うということである。 また、昨年からアメリカの合成燃料(synfuel)の合成工場の二酸化炭素を、カナダの油田のEORに使うというプロジェクトがスタートしている。それ以外に、世界的にも他の場所で幾つか具体的にこれを実施しようという考え方があり、既にかなり現実的に使われている方法である。 このように、CO2の回収処理は従来の公害除去型の方式だが、現段階では技術的にかなり実現可能で、しかも新エネルギーに比べ相対的にコストが安いということが挙げられる。従い、今後数十年のスパンではかなり現実的に使用出来る方法である。 続いて原子力の問題についてだが、これが日本の原子力の現状である。世界に目を向けると、電力の中で原子力の占める比率が30%を超す国というのは実は非常に多い。既に原子力をやめることを宣言したスウェーデンが40数%、ドイツでも32%という状況であり、現実には原子力が電力のかなりの部分を担っていることは事実である。これをどうやってやめられるかということになると、どこの国においても、現状では原子力発電をやめる手段は持っていない。 しかし、原子力発電においては高レベル廃棄物の処理問題という大変難しい問題があり、これをどのように解決するかによって今後の展開が変わるだろう。これは普通の発電所立地の問題と並び、いわゆる社会問題、PAの問題であり、物理的な技術の問題ではない。そのような意味でも、今後この問題をどう扱うのかというのは、まさに世界の基本的な問題であろう。 今まで申し上げたのは、国土交通省と全く関係ない事項だが、私が関心を持っているのは、今後を考えた場合、今までのものと同時に様々な形で住宅の省エネルギー技術が進歩するだろうということである。 これは北海道の札幌につくられた、ローエネルギーハウスという科学技術振興事業団の実験住宅である。上にあるのは太陽光発電のパネルだが、同時に地下にアースチューブを通し、それから熱の回収をする形で現実に家を暖めている。冬の場合、外気は非常に温度が低いため、換気の場合、外部からそのまま空気を取るととても非効率であるため、地中の熱を用いて暖めているという家である。 我々の周囲には、大地あるいは水といった、熱容量が大きく温度の安定した熱源があるので、これを利用して様々な形で熱の回収が出来る。それを使用するというのが最近出てきている方法である。 年間エネルギー種別利用量の内訳を見ると、エネルギー全体のうち、商用電源のみが購入するものは全体の8分の1であり、それ以外は全て賄えるということである。この内訳より、土壌熱が意外に大きいということが分かる。 これは、フランフォーファー研究所というドイツの8,000人程度の大きな研究所に所属するソーラーのグループが築造した、ドイツのフライブルグにあるアウタルキーハウスと言われる実験住宅である。この住宅のポイントは、上方にあるパネルは全部太陽光発電のパネルで、下の方は全て断熱、あるいは熱を効率的に回収するための装置がいろいろと設置されている。一番大きなポイントは、このアウタルキーハウスという名前でお分かりいただけるように、上から来るエネルギーで、この家の電力を含めてすべてのエネルギーを賄うというコンセプトで築造したものであるという点である。夏はこのシステムで問題ないが、冬はどうするのか。冬は天気も悪く、ほとんど日照がない訳であるが、対応策として、ここでは夏の電力が余るため、その電力で水素を作り、冬にその水素で燃料電池を動かして発電をするという方式を採用している。 アメリカでもこれと似たようなコンセプトのシステムがあるが、これは実際にドイツで築造した大変有名な例である。ただし、コストは現段階では大変高い。 次にこれはものすごく簡単な家で、基本的な設備は一般的な住宅と変わらない。続いてこれは、フランクフルトの側のビースバーデンというリゾート都市の米軍キャンプの払い下げ地につくられた商用住宅である。 47棟あったと思うが、これは勤労者用の住宅でパッシブハウスと呼んでいるが、ポイントは、普通の断熱を必死にやっている、換気をすごく工夫しており全体で熱の回収には大変努力している、という点である。 つまり、廃棄の熱を回収し、入り口の空気と熱交換をするといった努力もしている訳であるが、コストは非常に安く、120平方メートル程度の居住面積で1,100万円であり、若手の勤労者が住める家である。 しかし、この家の場合は暖房が設置されていない。つまり、エネルギー使用量を抑えるということで、パッシブハウスと呼ばれている。 デンマークにゼロエナージーハウスというのがあるが、これも同じである。家には調理、給湯、人間の体という熱源があるので、十分な断熱があればそれで十分であるという例で、これは大変上手くいっている。私も訪ねてみたが、そういう話であった。 最後は車の問題についてだが、車のエネルギーを減らす試みが、現在いろいろな形で努力をされている。燃費改善のためには、例えばトヨタのハイブリッド、あるいはホンダも行っているが、そのような形をはじめ、FCの車が検討されている。 現実にはこのような努力のためにいろいろな形の改善が行われているが、過去6、7年の範囲における車の標準燃費、テンフィフティーンモードの標準燃費の推移を見ると、出荷ベースと保有ベースが書いてあるが、点線の保有ベースは下がっている。 下がっているのは1リットル当たりのキロメートルであるので、悪くなっているということである。ところが出荷ベースでは良くなってきている。 なぜこうも違うのだろうと思われるだろうが、技術的に言えば、同じ型式のものは全て改善されているのである。 その理由は、重量、排気量の増加である。重量、排気量とも1970年頃から増加しており、エンジンの排気量は当時に比べ3割以上増えているというのが実態である。 また、車の重量というものも、最近は様々な設備が付属する傾向にあり、またRV化ということもあり、非常に増加している。この傾向が続くと、いくら技術的な努力をしても結局その効果はあまり出てこないということで、今後こういった問題をどう解決するかということを、技術的課題と並んだ問題として危惧している。 いずれにしても、車の問題というのもいろいろあり、我々も単なるFC車だけでなく、真の意味での電気自動車を開発の対象とすることも重要であろう。 |