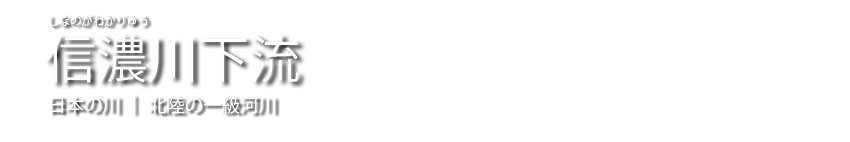
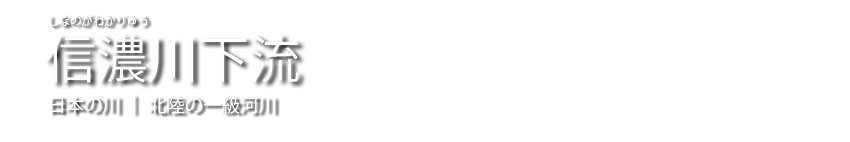

信濃川下流の主な災害
|
主な災害
荒れ狂う水の恐ろしさ、悲惨な洪水
信濃川は、その昔、洪水の度に氾濫をくり返す恐ろしい川でもありました。記録に残されているものだけでも、慶長5年(1600年)から昭和24年(1949年)の350年間に94回もの洪水がありました。これは3年から4年に一度の割合で洪水が起こっていることになり、人々は大変な被害を受けていたのです。
信濃川下流部では、明治29年(1896年)の「横田切れ」、大正6年(1917年)の「曽川切れ」が悲惨な洪水として有名です。大河津分水路が完成した後は、信濃川下流部における大洪水の発生頻度は減少したものの、近年でも昭和53年(1978年)、平成10年(1998年)、平成16年(2004年)7月13日と平成23年(2011年)7月29日の新潟・福島豪雨による洪水で甚大な被害が発生しています。平成23年の洪水では、特に刈谷田川、五十嵐川の沿川での浸水被害が甚大であり、信濃川本川、中ノ口川も堤防天端近くまで水位が上昇し、危険な状態になりました。 過去の洪水・水害 |

三条市の浸水状況(平成16年7月)
|
| 発生日 | 発生原因 | 被災市町村 | 被害状況 |
|---|---|---|---|
| 1896(明治29)年7月(横田切れ) | 梅雨前線 | 分水町から新潟市までの西蒲原郡一帯 | 死傷者75名、流出家屋25,000戸 |
| 1917(大正6)年10月(曽川切れ) | 台風 | 新潟市南部を含む亀田郷のほぼ全域 | 死傷者76名、流失家屋19戸、被害面積8,000ha |
| 1961(昭和36)年8月 | 梅雨前線 | 新潟市、白根市、三条市などの下流域一帯 | 死者3名 全壊家屋80戸,浸水家屋9,545戸(半壊・床上2,407戸、床下7,138戸) |
| 1978(昭和53)年6月 | 梅雨前線 | 新潟市、白根市、三条市などの下流域一帯 | 田畑の浸水16,000ha、床上床下浸水約3,500戸 |
| 1998(平成10)年8月 | 梅雨前線 | 新潟市 | 半壊家屋3戸 浸水家屋10,264戸(床上1,422戸、床下8,842戸 ) |
| 2004(平成16)年7月 | 梅雨前線 | 三条市、見附市、長岡市など | 死者15名、全半壊家屋979戸 浸水家屋17,071戸(床上10,712戸、床下6,359戸) |
| 2011(平成23年)7月 | 梅雨前線 | 三条市、見附市、長岡市など | 死者4名、全半壊家屋849戸 浸水家屋8,669戸(床上1,101戸、床下7,568戸) |
|
大正6年10月「曽川切れ」
大正6年(1917年)10月2日の曽川切れでは、新潟市江南区天野地先で堤防が決壊し、亀田郷一帯の8,000haが泥海となりました。
決壊地点の堤防の復旧は50日以上もかかり、経費は莫大はものとなりました。この水害により5万人の住民が生活に苦しんだと言われています。 過去の洪水・水害 |

水浸しになった沼垂町
|
|
H10.8.4水害
平成10年(1998年)に新潟市を襲った8月4日の集中豪雨は、新潟地方気象台観測史上最大の60分間降雨量97㎜、日降水量265㎜を記録しました。
ポンプによる強制排水に依存せざるを得ない新潟市内の各地域では、ポンプの排水能力を超えた雨量により通船川や鳥屋野潟流域において、床上・床下浸水の被害が広がりました。 過去の洪水・水害 |

通船川付近の浸水状況

新潟市中央区笹口の様子
|
|
過去の主な渇水
平成6年の渇水
|
| 発生年月 | 取水制限延日数 ※1 | 最大取水制限率 ※2 | 信濃川下流の瀬切れ発生日数 |
|---|---|---|---|
| 平成6年7月 | 3日 | 30% | |
| 平成6年8月 | 19日 | 50% |
※1、※2は、信濃川下流管内における暫定水利権に対する取水制限延日数及び最大取水制限率を示す。
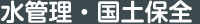



 河川トップに戻る
河川トップに戻る