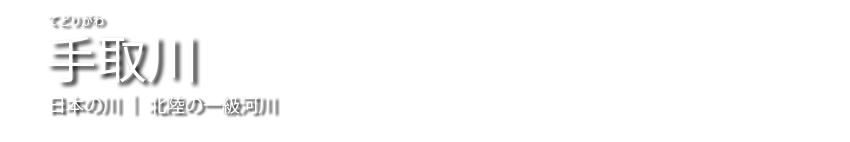
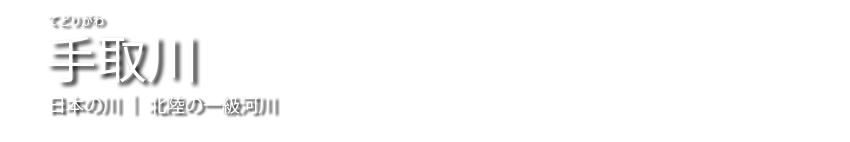

手取川の自然環境
|
多様な河川景観・多様な生物の生息・生育・繁殖環境
最上流部の地形
|
|
上中下流部の地形
|

上流部(源流白山)の状況

手取峡谷
|
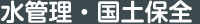
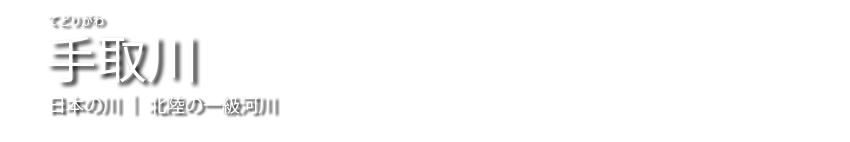

|
多様な河川景観・多様な生物の生息・生育・繁殖環境
最上流部の地形
|
|
上中下流部の地形
|

上流部(源流白山)の状況

手取峡谷
|