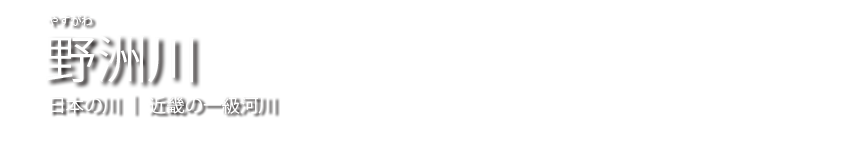
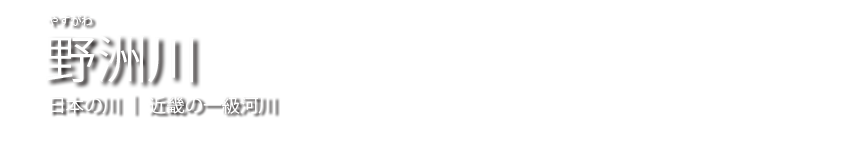

野洲川の歴史
|
野洲川放水路整備
|
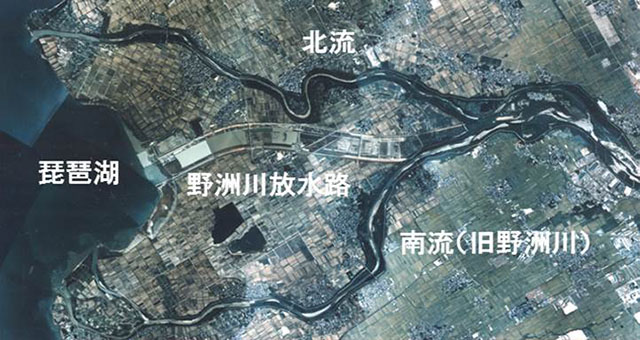
昭和50年(1975年)の野洲川
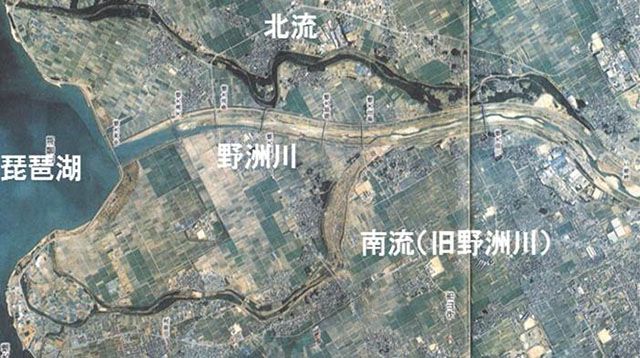
平成2年(1990年)の野洲川
|
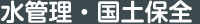
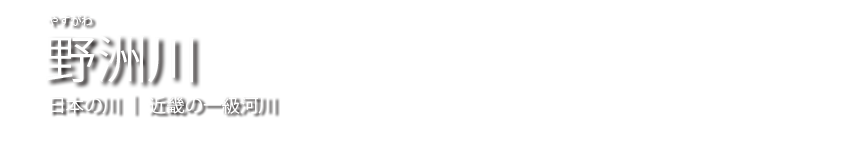

|
野洲川放水路整備
|
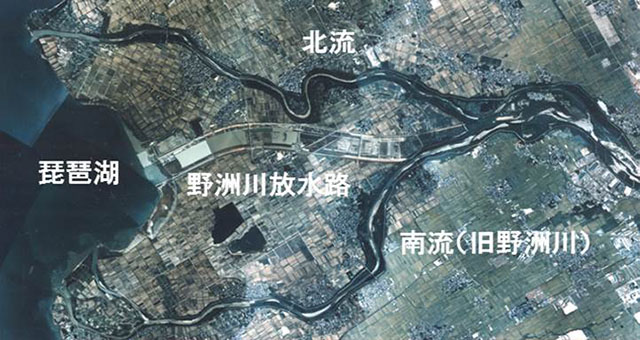
昭和50年(1975年)の野洲川
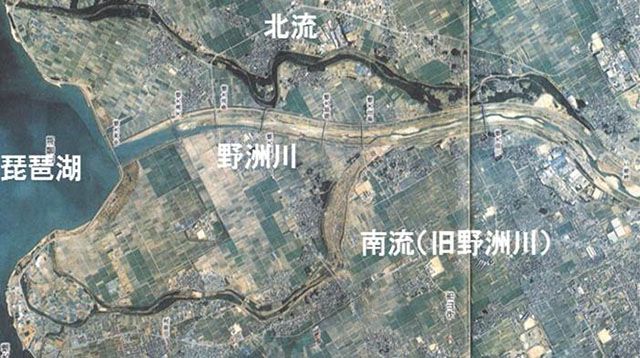
平成2年(1990年)の野洲川
|