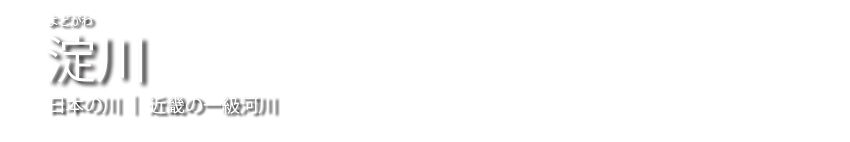
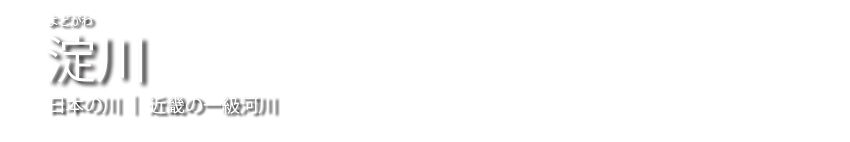

淀川の歴史
|
淀川改良工事による新淀川掘削
|
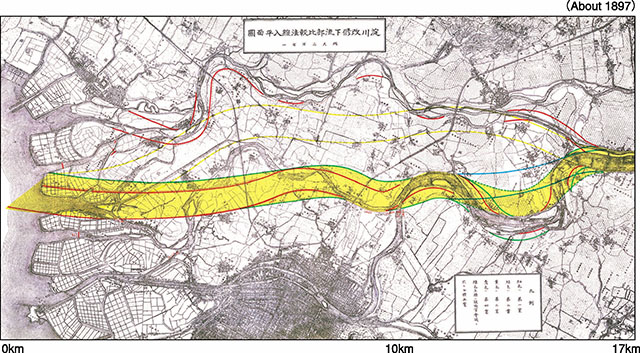
現在の淀川と改良工事前の三川
|
|
淀川大堰
|

淀川大堰
|
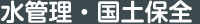
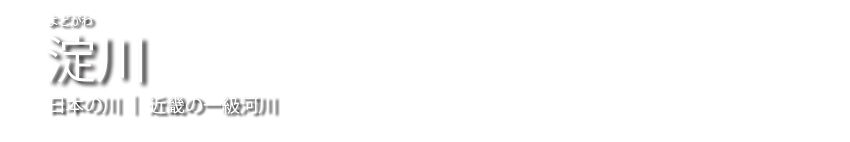

|
淀川改良工事による新淀川掘削
|
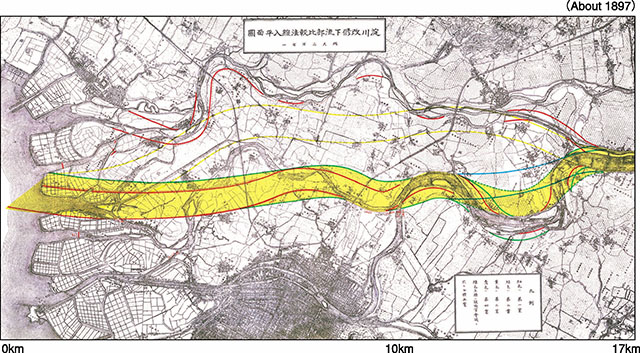
現在の淀川と改良工事前の三川
|
|
淀川大堰
|

淀川大堰
|