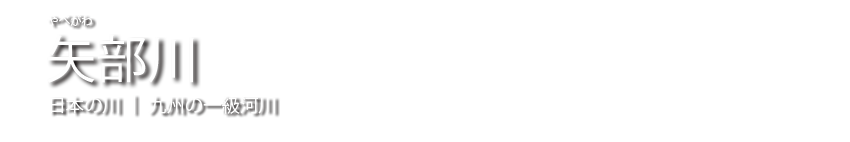
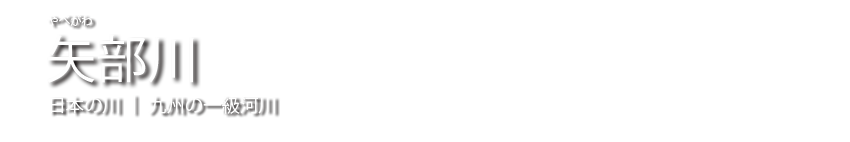

矢部川の歴史
|
先人の治水施設【千間土居】
|

千間土居
|
|
先人の治水施設【水刎】
|

水刎
|
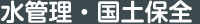
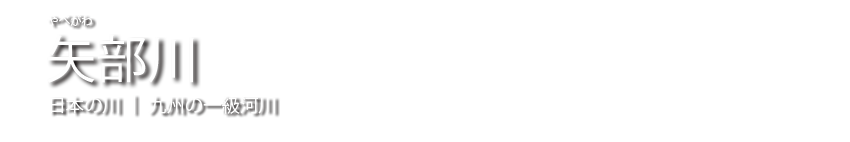

|
先人の治水施設【千間土居】
|

千間土居
|
|
先人の治水施設【水刎】
|

水刎
|