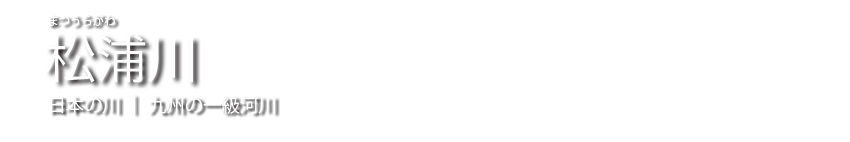
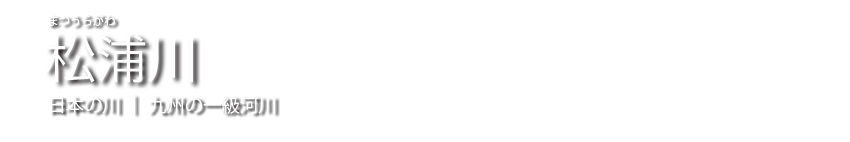

松浦川の歴史
|
近年の治水事業 ~松浦大堰~
|

松浦川3km付近(唐津市大土井)
|
|
近年の治水事業 ~駒鳴捷水路~
|

駒鳴捷水路
|
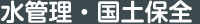
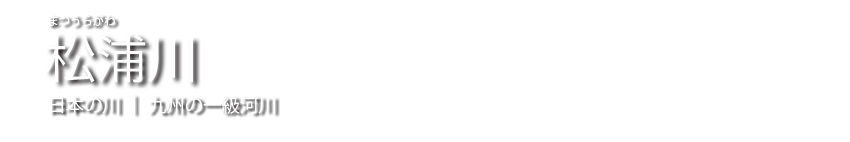

|
近年の治水事業 ~松浦大堰~
|

松浦川3km付近(唐津市大土井)
|
|
近年の治水事業 ~駒鳴捷水路~
|

駒鳴捷水路
|