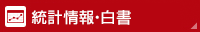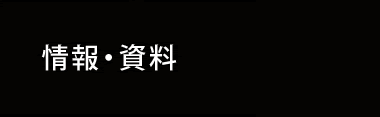
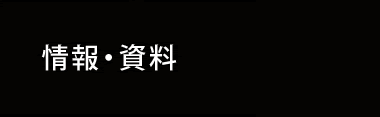
ページ本文




答えは、「現状ではできません」です。「あの地域と比べて観光込客数は多いのか、少ないのか」という疑問に答えられる観光統計は今までどこにもありませんでした。他のライバル地域をベンチマークすることができなければ、効果的な戦略を打つことができず、この比較が既存の統計の限界となっていました。
なぜ比較できないかというと、地域によって観光施設やイベントをどこまで調査対象に含めるのかという定義が違うからです。
また、客数自体に関する情報も、調査対象地点の入込客数を単純に足し上げる「延べ入込客数」だけを把握しているところもあれば、この「延べ入込客数」に「域内でいくつの訪問地をまわったか」という訪問地点数を別途把握し、それで割り戻すことにより域内における重複人数を省く「実入込客数」まで算出しているところもあります。さらに域内の「一人当たりの平均消費額」を上記「実入込客数」と掛け合わせて「観光における消費規模」まで把握しているところもあるというように、観光入込客数に関しては、各々の地域で把握・公表項目がバラバラなため、単純比較さえもすることができないという状況だったのです。
観光庁では、この大きな課題を解決すべく昨年12月、有識者の先生や自治体の観光統計担当者の協力をいただきながら、同一定義で観光入込客数を把握するための「観光入込客統計に関する共通基準」を策定し、本年4月より既に39都道府県において本基準に則った調査を開始しております。今年度中には45都道府県での導入が予定されています。この調査結果は観光庁において「全国観光入込客統計」として本年12月末頃に第一回の調査結果(平成22年4月~6月)を公表する予定であり、今後四半期毎に公表されるようになります。
この基準に則って調査を実施すれば、観光入込客、観光消費額をどんなエリアでも比較することができるようになります。
このように観光統計は地域における各種観光情報を定量的な数値として見える化し、他地域との比較や施策の効果を検証するために非常に有用なツールとなっています。このコラムが皆様の観光統計への興味や理解の一助となれば幸いです。

最終更新日:2010年10月18日

第4回 地域の観光統計ってどうなっているの?
今回のコラムは今年の9月末まで観光庁観光経済担当参事官室に勤務しており、現在南房総市役所に勤務している鈴木さんからの寄稿コラムです。
「民間であればデータを収集し、マーケティング分析をし、客観的な指標を元にして、適切にリソースを投入する」このプロセスが当たり前です。
私は、本年9月末日まで観光庁観光経済担当参事官室に出向をしており、現在南房総市役所に勤務する鈴木と申します。今は冒頭のようなことを言う私も先日までの出向先であった参事官室で観光統計に携わるまでは、「統計って地味だし数字が羅列されていてとっつきにくい」「そもそも良く分からないし、何の意味があるの」と思っておりました。しかし、統計は理解すると意外と簡単で、面白く、強力な武器となる。今はそう実感しております。
実際に、私の勤務先である千葉県の最南端にある「南房総観光圏地域」(館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町の3市1町)の宿泊者と入込客の状況について観光統計を活用して読み解いてみたいと思います。
まず、このエリアの宿泊者の状況を宿泊旅行統計調査から見てみましょう。
図1.平成21年の延べ宿泊者数の前年同期比変化率の推移(全国/千葉県/南房総)
「民間であればデータを収集し、マーケティング分析をし、客観的な指標を元にして、適切にリソースを投入する」このプロセスが当たり前です。
私は、本年9月末日まで観光庁観光経済担当参事官室に出向をしており、現在南房総市役所に勤務する鈴木と申します。今は冒頭のようなことを言う私も先日までの出向先であった参事官室で観光統計に携わるまでは、「統計って地味だし数字が羅列されていてとっつきにくい」「そもそも良く分からないし、何の意味があるの」と思っておりました。しかし、統計は理解すると意外と簡単で、面白く、強力な武器となる。今はそう実感しております。
実際に、私の勤務先である千葉県の最南端にある「南房総観光圏地域」(館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町の3市1町)の宿泊者と入込客の状況について観光統計を活用して読み解いてみたいと思います。
まず、このエリアの宿泊者の状況を宿泊旅行統計調査から見てみましょう。
図1.平成21年の延べ宿泊者数の前年同期比変化率の推移(全国/千葉県/南房総)

平成21年の延べ宿泊者数の前年同期比変化率の推移(平成21年/平成20年)です。グラフを見ると南房総地域の平成21年1月~3月に毎月前年同期比で15%を超えるマイナスと低迷しています。しかしながら、3月末に高速道路「休日上限千円」の料金制度が導入された時期には飛躍的に宿泊者数が回復しており、その効果が伺えます。また、9月にはシルバーウィークの影響により、更に宿泊客数が大幅な増加となりました。ただし、全国や千葉県と比較すると1~3月期や10月~12月期の落ち込みは激しく、経年で見ると南房総地域の宿泊者は、減少傾向にあります。その原因としては、都心からのアクセスの向上等により、来訪者が宿泊を伴う旅行ではなく、日帰り旅行にシフトしているといったことが考えられます。今回の増加を一過性のものとしないためにも、日帰り観光地から滞在型観光地へのシフトやリピーターを増やすための方策、需要の平準化への取組がまだまだ必要だと言えるでしょう。具体的には広域的な着地型観光商品の開発やそのような業務を担える仕組み作り・人材育成等、行政区に囚われない南房総を面で捉えた広域的な取組・情報発信が必要だと思います。これらの策については、現在南房総観光圏地域一体となって検討を進めているところです。
宿泊旅行統計調査では、このように地域別や都道府県別、全国との対比など、「あの地域に比べてうちの地域の宿泊客は、伸びているのか、減っているのか」といったことをつぶさに見てとることができます。
今度は、観光客の増減を平成21年の「千葉県観光入込客統計」から見てみましょう。
図2.平成21年延べ観光入込客数の前年同期比変化率の推移(千葉県/南房総地域)
宿泊旅行統計調査では、このように地域別や都道府県別、全国との対比など、「あの地域に比べてうちの地域の宿泊客は、伸びているのか、減っているのか」といったことをつぶさに見てとることができます。
今度は、観光客の増減を平成21年の「千葉県観光入込客統計」から見てみましょう。
図2.平成21年延べ観光入込客数の前年同期比変化率の推移(千葉県/南房総地域)

図3.平成21年全国路線網別・月別通行台数(日平均)前年同期比変化率の推移

図2は平成21年の延べ入込客数における前年同期比(平成21年/平成20年)です。こちらのデータからも、宿泊客数の場合と同様に3月からの高速道路の新料金制度導入の影響、9月のシルバーウィークの影響が如実に現れております。また、千葉県と南房総地域を比較すると、シルバーウィーク期間は大型連休により県も南房総も飛躍的に入込が増加しているのに対し、3月の高速道路の新料金制度導入の時期は南房総地域のみ大幅な増加になっております。これは、シルバーウィークに関して全国的な旅行需要の増加に伴い、県内全体の入込客数も増加したのに対し、3月から5月までの増加は、高速道路の新料金制度の効果により「アクアラインが安いなら南房総へ行ってみよう」と旅行先として南房総地域を選択した方が相対的に増えたことに起因していると考えられます。
図3は、NEXCO東日本の発表している「全国路線網(高速道路)別・月別通行台数(日平均)」のデータです。千葉県へ流入する高速道路である「京葉道路」および「アクアライン」の通行台数を比較しても、新料金制度が「アクアライン」の需要を誘発したことが伺えます。
さて、ここで一つ問題です。
図2で使用した「千葉県観光入込客統計」の増減率は宿泊旅行統計調査のように他地域と比較することができるでしょうか?
答えは、「現状ではできません」です。「あの地域と比べて観光込客数は多いのか、少ないのか」という疑問に答えられる観光統計は今までどこにもありませんでした。他のライバル地域をベンチマークすることができなければ、効果的な戦略を打つことができず、この比較が既存の統計の限界となっていました。
なぜ比較できないかというと、地域によって観光施設やイベントをどこまで調査対象に含めるのかという定義が違うからです。
また、客数自体に関する情報も、調査対象地点の入込客数を単純に足し上げる「延べ入込客数」だけを把握しているところもあれば、この「延べ入込客数」に「域内でいくつの訪問地をまわったか」という訪問地点数を別途把握し、それで割り戻すことにより域内における重複人数を省く「実入込客数」まで算出しているところもあります。さらに域内の「一人当たりの平均消費額」を上記「実入込客数」と掛け合わせて「観光における消費規模」まで把握しているところもあるというように、観光入込客数に関しては、各々の地域で把握・公表項目がバラバラなため、単純比較さえもすることができないという状況だったのです。
観光庁では、この大きな課題を解決すべく昨年12月、有識者の先生や自治体の観光統計担当者の協力をいただきながら、同一定義で観光入込客数を把握するための「観光入込客統計に関する共通基準」を策定し、本年4月より既に39都道府県において本基準に則った調査を開始しております。今年度中には45都道府県での導入が予定されています。この調査結果は観光庁において「全国観光入込客統計」として本年12月末頃に第一回の調査結果(平成22年4月~6月)を公表する予定であり、今後四半期毎に公表されるようになります。
この基準に則って調査を実施すれば、観光入込客、観光消費額をどんなエリアでも比較することができるようになります。
このように観光統計は地域における各種観光情報を定量的な数値として見える化し、他地域との比較や施策の効果を検証するために非常に有用なツールとなっています。このコラムが皆様の観光統計への興味や理解の一助となれば幸いです。
図3は、NEXCO東日本の発表している「全国路線網(高速道路)別・月別通行台数(日平均)」のデータです。千葉県へ流入する高速道路である「京葉道路」および「アクアライン」の通行台数を比較しても、新料金制度が「アクアライン」の需要を誘発したことが伺えます。
さて、ここで一つ問題です。
図2で使用した「千葉県観光入込客統計」の増減率は宿泊旅行統計調査のように他地域と比較することができるでしょうか?
答えは、「現状ではできません」です。「あの地域と比べて観光込客数は多いのか、少ないのか」という疑問に答えられる観光統計は今までどこにもありませんでした。他のライバル地域をベンチマークすることができなければ、効果的な戦略を打つことができず、この比較が既存の統計の限界となっていました。
なぜ比較できないかというと、地域によって観光施設やイベントをどこまで調査対象に含めるのかという定義が違うからです。
また、客数自体に関する情報も、調査対象地点の入込客数を単純に足し上げる「延べ入込客数」だけを把握しているところもあれば、この「延べ入込客数」に「域内でいくつの訪問地をまわったか」という訪問地点数を別途把握し、それで割り戻すことにより域内における重複人数を省く「実入込客数」まで算出しているところもあります。さらに域内の「一人当たりの平均消費額」を上記「実入込客数」と掛け合わせて「観光における消費規模」まで把握しているところもあるというように、観光入込客数に関しては、各々の地域で把握・公表項目がバラバラなため、単純比較さえもすることができないという状況だったのです。
観光庁では、この大きな課題を解決すべく昨年12月、有識者の先生や自治体の観光統計担当者の協力をいただきながら、同一定義で観光入込客数を把握するための「観光入込客統計に関する共通基準」を策定し、本年4月より既に39都道府県において本基準に則った調査を開始しております。今年度中には45都道府県での導入が予定されています。この調査結果は観光庁において「全国観光入込客統計」として本年12月末頃に第一回の調査結果(平成22年4月~6月)を公表する予定であり、今後四半期毎に公表されるようになります。
この基準に則って調査を実施すれば、観光入込客、観光消費額をどんなエリアでも比較することができるようになります。
このように観光統計は地域における各種観光情報を定量的な数値として見える化し、他地域との比較や施策の効果を検証するために非常に有用なツールとなっています。このコラムが皆様の観光統計への興味や理解の一助となれば幸いです。
答えは、「現状ではできません」です。「あの地域と比べて観光込客数は多いのか、少ないのか」という疑問に答えられる観光統計は今までどこにもありませんでした。他のライバル地域をベンチマークすることができなければ、効果的な戦略を打つことができず、この比較が既存の統計の限界となっていました。
なぜ比較できないかというと、地域によって観光施設やイベントをどこまで調査対象に含めるのかという定義が違うからです。
また、客数自体に関する情報も、調査対象地点の入込客数を単純に足し上げる「延べ入込客数」だけを把握しているところもあれば、この「延べ入込客数」に「域内でいくつの訪問地をまわったか」という訪問地点数を別途把握し、それで割り戻すことにより域内における重複人数を省く「実入込客数」まで算出しているところもあります。さらに域内の「一人当たりの平均消費額」を上記「実入込客数」と掛け合わせて「観光における消費規模」まで把握しているところもあるというように、観光入込客数に関しては、各々の地域で把握・公表項目がバラバラなため、単純比較さえもすることができないという状況だったのです。
観光庁では、この大きな課題を解決すべく昨年12月、有識者の先生や自治体の観光統計担当者の協力をいただきながら、同一定義で観光入込客数を把握するための「観光入込客統計に関する共通基準」を策定し、本年4月より既に39都道府県において本基準に則った調査を開始しております。今年度中には45都道府県での導入が予定されています。この調査結果は観光庁において「全国観光入込客統計」として本年12月末頃に第一回の調査結果(平成22年4月~6月)を公表する予定であり、今後四半期毎に公表されるようになります。
この基準に則って調査を実施すれば、観光入込客、観光消費額をどんなエリアでも比較することができるようになります。
このように観光統計は地域における各種観光情報を定量的な数値として見える化し、他地域との比較や施策の効果を検証するために非常に有用なツールとなっています。このコラムが皆様の観光統計への興味や理解の一助となれば幸いです。

観光庁観光経済担当参事官室
代表 03-5253-8111(内線27-213)
e-Mail:statistical_column@mlit.go.jp
代表 03-5253-8111(内線27-213)
e-Mail:statistical_column@mlit.go.jp