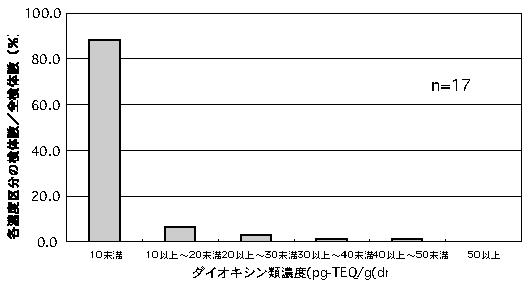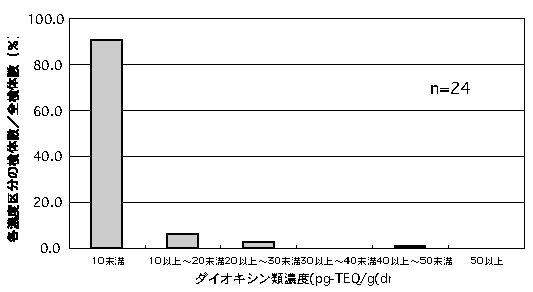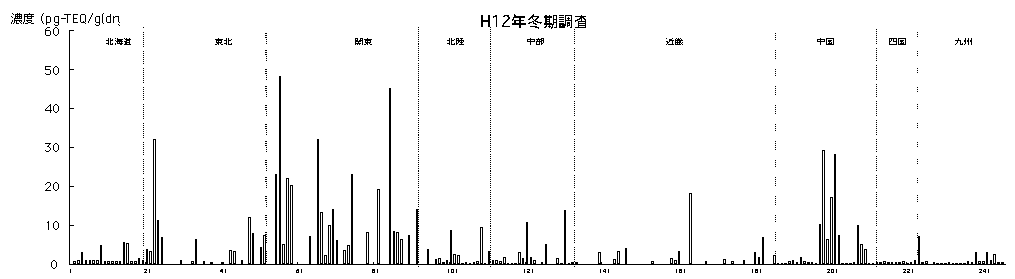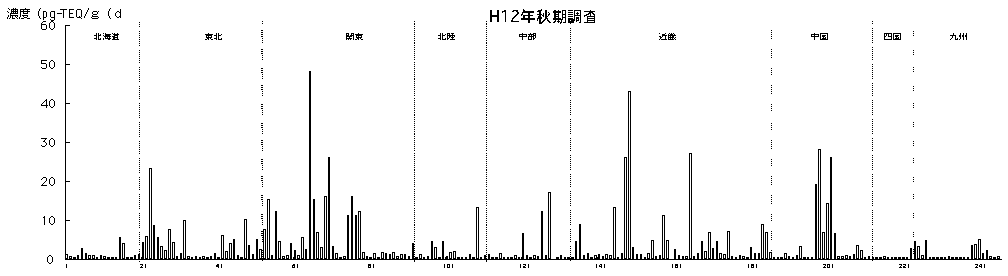|
5-2.底質調査結果
1)調査結果
全国の一級河川109水系(平成12年冬期調査 172地点、平成12年秋期調査 244地点)において実施した底質測定結果を表-5.2.1及び図-5.2.3及び図-5.2.4に、濃度分布図を図-5.2.1、図-5.2.2に示した。また、2回の調査結果の関係を示す散布図を図-5.2.5に、変動幅のヒストグラムを図-5.2.6に、ダイオキシン類濃度とTOC、強熱減量、粒度組成との関係を示す散布図を図-5.2.7に、縦断調査結果を図-5.2.8〜5.2.13に示した。
平成12年冬期調査では、平均値が4.4pg-TEQ/g(dry)で検出範囲は0.038〜48pg-TEQ/g(dry)であった。濃度分布は10pg-TEQ/g(dry)未満が最も多く、全検体の9割弱を占めていた。
平成12年秋期調査では、平均値が3.4pg-TEQ/g(dry)で検出範囲は0.23〜48pg-TEQ/g(dry)であった。濃度分布は10pg-TEQ/g(dry)未満が最も多く、全検体の約9割を占めていた。
代表12河川で実施した縦断調査の結果は、河川により傾向が異なっていた。
2)考察
底質の全国調査結果では、湖沼や湛水域で相対的に高い値を示す傾向にあった。また、平均値で見ると、平成11年度に環境省が二級河川等で実施した「ダイオキシン類緊急全国一斉調査」の結果と比較して、やや低いレベルであった。
今回の調査において全国の底質濃度の傾向は把握できたものの(図-5.2.3、図-5.2.4参照)、個々の河川、湖沼においては、2回の測定値に差異が見られた(図-5.2.5参照)。同一地点での2回の測定値の差は表-5.2.2から<0.01〜44pg-TEQ/g(dry)で、河川湛水域で濃度差が大きい地点がみられた。2回の調査の地点ごとの濃度の比注)をみると、2倍以上変動した地点数の割合は河川順流部、河川湛水部で約5から6割と大きく、河川感潮域では約4割であったが、湖沼では2倍以上変動した地点はなかった(図-5.2.6参照)。河川の底質は河床の堆積状況が変化することにより、同一地点であっても、空間分布の変化によるばらつきや採取時期で底質の性状の変化が考えられ、ダイオキシン類濃度に影響していると考えられる。
また、全国データでみるとダイオキシン類濃度とTOC,強熱減量、シルト・粘土分の含有率との間には相関は見られなかった。相関が見られないのは各河川、湖沼により、流入するダイオキシン類汚染とTOCや強熱減量の有機汚濁物質の発生要因が異なる他、河床の底質性状の違いも寄与していると考えられる(図-5.2.7参照)。
代表12河川で実施した縦断調査においては、底質のダイオキシン類濃度は粒子が堆積しやすい堰やダム地点で相対的に高くなる傾向を示した。感潮域は塩分による凝集沈降が考えられるが、底質のダイオキシン類濃度については明確な傾向は見られなかった。全体では、河川の流下方向における明確な傾向は見られなかった。また、平成12年冬期、12年秋期の比較では、同一地点での濃度及び縦断方向でのダイオキシン類濃度の傾向が異なる河川が見られ、堆積状況や河床の変化等による影響が考えられる。(図-5.2.8〜5.2.13参照)。
全国の直轄河川、湖沼の実態を把握するためには、2回の調査結果ではデータの蓄積が不十分なため、継続して全国調査の実施が必要と考えられる。
表-5.2.1 底質調査結果
| |
測定数 |
平均値
pg-TEQ/g(dry) |
中央値
pg-TEQ/g(dry) |
検出範囲
pg-TEQ/g(dry) |
| 平成12年 冬期調査 |
172 |
4.4 |
0.86 |
0.038〜48 |
| 平成12年 秋期調査 |
244 |
3.4 |
0.85 |
0.23〜48 |
(参考)
平成11年度
環境省調査結果 |
542 |
5.4 |
- |
0.066〜230 |
表-5.2.2 同一地点における底質濃度差による比較(平成12年冬期と12年秋期との差)
| |
差の最大値
pg-TEQ/g(dry) |
差の最小値
pg-TEQ/g(dry) |
平均値
pg-TEQ/g(dry) |
| 河川(順流部) |
22 |
<0.01 |
2.2 |
| 河川(感潮域) |
17 |
0.01 |
2.9 |
| 河川(湛水域) |
44 |
0.18 |
10 |
| 湖沼 |
12 |
0.17 |
3.6 |
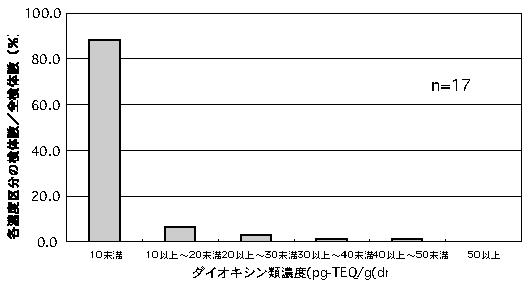
図-5.2.1 ダイオキシン類濃度ヒストグラム(平成12年冬期調査 底質)
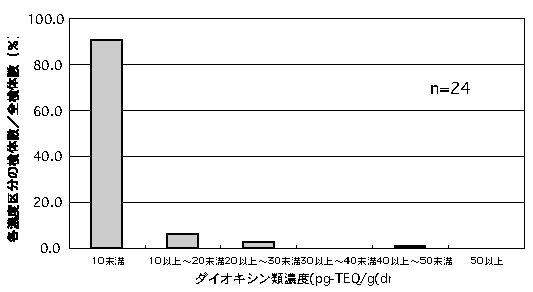
図-5.2.2 ダイオキシン類濃度ヒストグラム(平成12年秋期調査 底質)
|