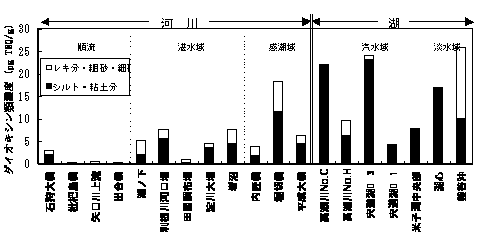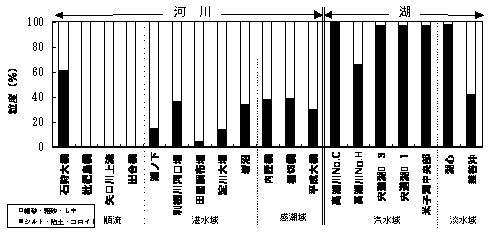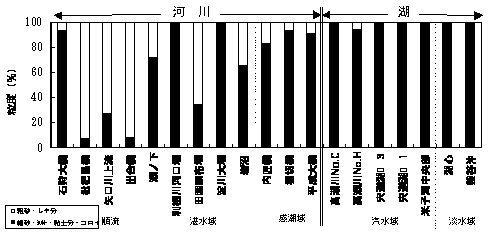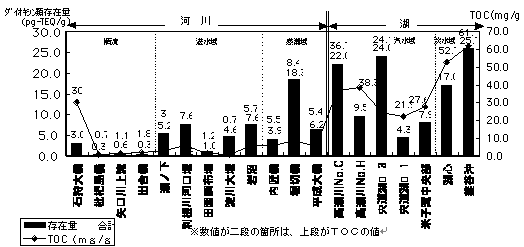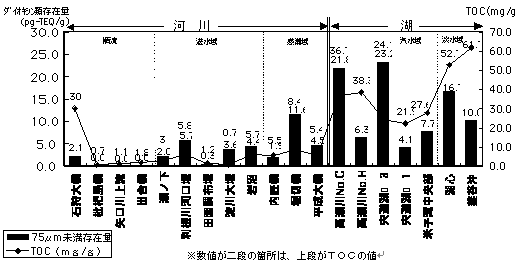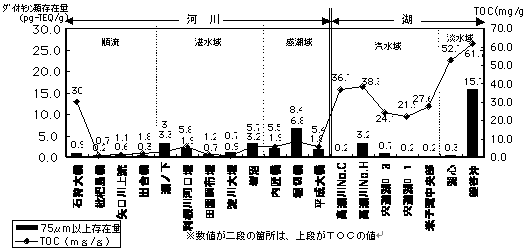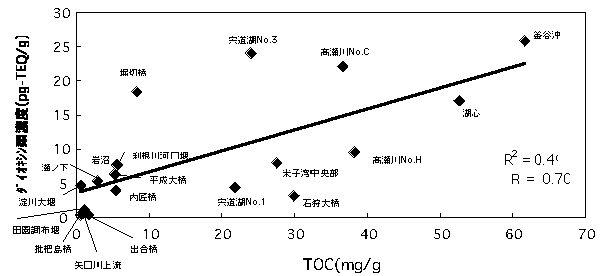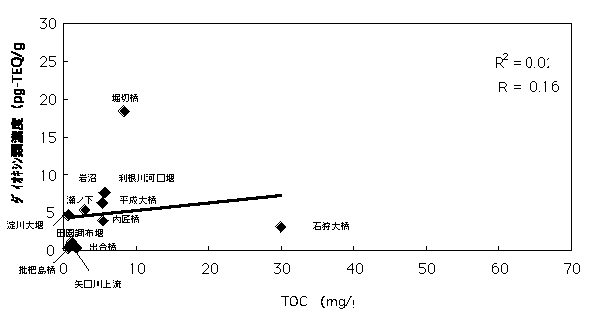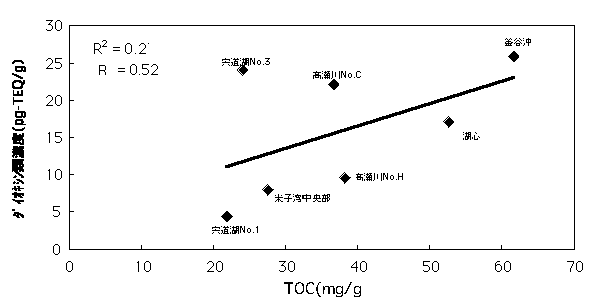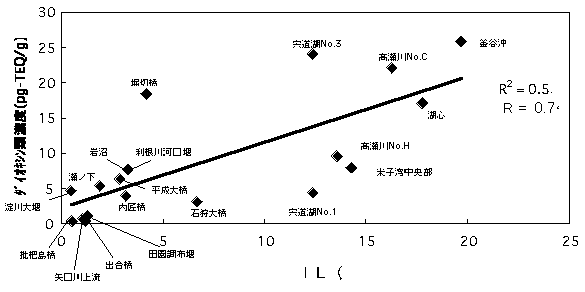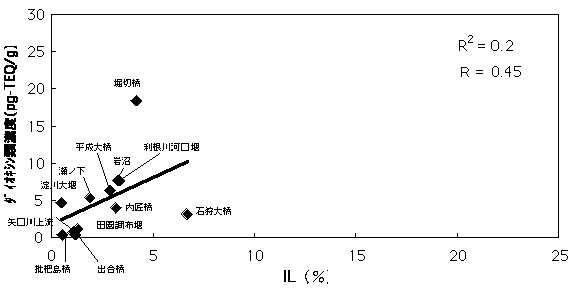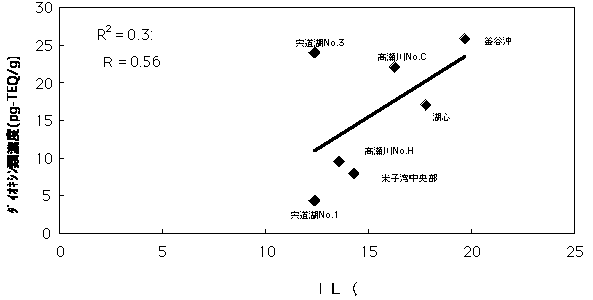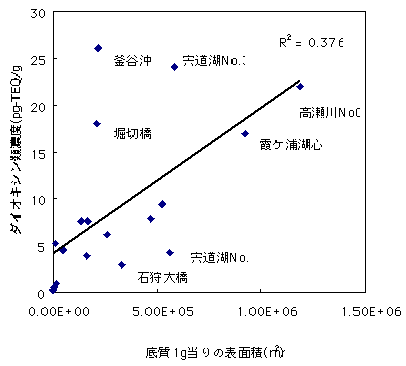|
5-3.形態把握調査
(2)底質
1)調査結果
底質のダイオキシン類については、レキ・砂質分(75μm以上)とシルト・粘土分(75μm未満)の粒度別にふるい分けを行い、分画試料それぞれのダイオキシン類の分析を行った。また、別途、試料の粒度組成、強熱減量、TOCを測定した。
底質の形態把握調査結果を表-5.3.3に示す。また、試料1g中のレキ・砂分及びシルト・粘土分に含まれるダイオキシン量を図-5.3.3に、各試料の粒度組成を図-
5.3.4に示す。
表-5.3.3の調査結果から、試料1g中に含まれるダイオキシン類の量は、0.25〜26pg-TEQ、試料1g中のシルト・粘土分に含まれるダイオキシン類の量は、0.0036〜23pg-TEQ、試料1g中のレキ・砂分に含まれるダイオキシン類の量は、0.17〜16pg-TEQであった。
2)考察
 |
ダイオキシン類濃度
<全体のダイオキシン類濃度>
ダイオキシン類濃度が他の地点と比べて高かった5地点(堀切橋、高瀬川No.C、宍道湖No.3、湖心、釜谷沖)の粒度組成の測定結果をみると、図-
5.3.4(1)に示すとおり、高瀬川No.C、宍道湖No.3、湖心の3地点では、75μm未満の粒子が95%以上存在しており、細かい粒子が多い地点であった。残りの2地点(堀切橋、釜谷沖)では、粒径75μm以下の粒子が39%〜42%であったが、75μm以上の粒子のほとんどが細砂であり、細砂(75〜425μm)とシルト・粘土を合わせると95%以上を占めていた(図-
5.3.4(2)参照)。
このことから、ダイオキシン類が比較的高濃度に存在する地点では、シルト・粘土分だけでなく、細砂に区分されるものにもダイオキシン類が含まれているものと考えられた。ただし、ここでいう細砂は粒度組成試験によって求められた75〜425μmの粒径をもつ粒子であり、鉱物質の砂だけを意味するものではない。
<シルト分及び砂分のダイオキシン類濃度>
シルト・粘土分と砂・レキ分に含まれるダイオキシン類の存在量を比較すると、河川において、底質の性状のほとんどが砂・レキ分である河川順流域(枇杷島橋、矢口川上流、出合橋)、河川湛水域(瀬の下、田園調布堰)では、単位重量あたりでは、シルト・粘土分にダイオキシン類が比較的多く含まれているものの、シルト・粘土分が僅かしか含まれないため、測定されるダイオキシン類含有量としては、砂・レキ分に含まれるものがほとんどとなった。それ以外のシルト粘土を含む地点では、シルト・粘土分に多く含まれる傾向にあった(図-
5.3.3、5.3.4(1)参照)。湖では、釜谷沖及び高瀬川No.Hを除き、シルト・粘土が95%以上を占める性状であり、砂・レキ分との比較はできなかった。釜谷沖及び高瀬川No.Hの地点においては、砂・レキの区分にもダイオキシン類が含まれていたが、粒度組成の測定結果によると砂・レキ分のほとんどが細砂に区分されるものであることから、細砂として区分されるものにもダイオキシン類が含まれていると考えられる(図-
5.3.3、5.3.4(1)(2)参照)。
|
 |
シルト分及び砂分に存在するダイオキシン量とTOCとの関係
シルト分及び砂分に存在するダイオキシン量とTOCとの関係をみると、ダイオキシン類の値の高い湖では、TOCの値も高い傾向がみられた(図-
5.3.5(1)(2)(3)参照)。
河川ではダイオキシン類の存在量に対しTOC濃度の値の変動は、微弱ではあるが同様の変動の傾向性はあった(河川順流:石狩大橋、堀切橋を除く)。
ダイオキシン類が微細な粒子への吸着だけでなく、TOC濃度の高い湖などの有機物にも含まれとすれば、このような傾向を示すと考えられるが、TOCは分画していない試料についてのみ分析しているだけであり、粒径毎の評価をすることはできなかった。
|
 |
各因子(TOC、強熱減量)との関係
ダイオキシン類濃度とTOC及び強熱減量(IL)の関係をみるために、全地点、河川、湖で相関をとったところ、TOCとILでは概ね同じ散布状況を示した(図-
5.3.6(1)、図-5.3.7(1)参照)。
全地点で相関を見た場合には、有機物が多いとダイオキシン類濃度が高い傾向が見られたが、河川、湖にわけると明瞭な関係は見られなかった(図-
5.3.6(1)(2)(3)、図-5.3.7(1)(2)(3)参照)。
|
 |
底質の総表面積との関係
ダイオキシン類の存在量(総量)と底質1g当たりの総表面積の相関をみると、一部地点を除き相関が見られた(図-5.3.8参照)。
単位重量当たりの底質粒子の総表面積が大きい(細かい粒子が多い)地点でダイオキシン類濃度が高くなる傾向が示唆されたが、釜谷沖、宍道湖No.3等で相関式からはずれる地点もあり、必ずしもダイオキシン類の底質への存在が粒子への吸着・付着だけではないことを示唆しており、他の要因の関与も考えられるが、今回の調査では要因の解析はできなかった。
|
表-5.3.3 形態把握調査(底質)結果
(地点数 19地点)
| 調査地点 |
総量
(pg‐
TEQ/g) |
濃 度
(pg‐TEQ/g) |
試料1g 中の存在量
(pg‐TEQ) |
粒 度
(%) |
存在比
(%) |
TOC
(mg/g ) |
IL
(%) |
| 75μm未満 |
75μm以上 |
75μm未満 |
75μm以上 |
75μm未満 |
75μm以上 |
| 枇杷島橋 |
0.25 |
3.6 |
0.25 |
0.0036 |
0.25 |
0.1 |
100 |
14 |
0.7 |
0.55 |
| 出合橋 |
0.32 |
6.7 |
0.29 |
0.027 |
0.29 |
0.4 |
100 |
21 |
1.8 |
1.2 |
| 矢口川上流 |
0.60 |
3.1 |
0.59 |
0.0062 |
0.59 |
0.2 |
100 |
5.2 |
1.1 |
1.1 |
| 田園調布堰 |
1.0 |
8.2 |
0.70 |
0.34 |
0.67 |
4.1 |
95.9 |
8.1 |
1.2 |
1.3 |
| 石狩大橋 |
3.0 |
3.5 |
2.3 |
2.1 |
0.89 |
61.4 |
38.6 |
1.2 |
30 |
6.7 |
| 内匠橋 |
3.9 |
5.1 |
3.1 |
1.9 |
1.9 |
37.7 |
62.3 |
1.3 |
5.5 |
3.2 |
| 宍道湖・1 |
4.3 |
4.2 |
7.5 |
4.1 |
0.21 |
97.2 |
2.8 |
0.98 |
22 |
12 |
| 淀川大堰 |
4.6 |
26 |
1.1 |
3.6 |
0.95 |
14.0 |
86.0 |
5.7 |
0.7 |
0.5 |
| 瀬ノ下 |
5.2 |
14 |
3.8 |
2.0 |
3.3 |
14.2 |
85.8 |
2.7 |
3.0 |
1.9 |
| 平成大橋 |
6.2 |
15 |
2.5 |
4.5 |
1.8 |
29.8 |
70.2 |
2.4 |
5.4 |
2.9 |
| 岩沼 |
7.6 |
13 |
4.8 |
4.4 |
3.2 |
33.7 |
66.3 |
1.7 |
5.7 |
3.3 |
| 利根川河口堰 |
7.6 |
16 |
2.9 |
5.7 |
1.9 |
35.8 |
64.2 |
2.1 |
5.8 |
3.3 |
| 米子湾中央部 |
7.9 |
7.9 |
6.9 |
7.7 |
0.17 |
97.5 |
2.5 |
1.0 |
28 |
14 |
| 高瀬川No.H |
9.5 |
9.6 |
9.3 |
6.3 |
3.2 |
65.5 |
34.5 |
1.0 |
38 |
14 |
| 湖心 |
17 |
17 |
18 |
17 |
0.31 |
98.3 |
1.7 |
1.0 |
53 |
18 |
| 堀切橋 |
18 |
30 |
11 |
12 |
6.8 |
38.6 |
61.4 |
1.6 |
8.4 |
4.2 |
| 高瀬川No.C |
22 |
22 |
25 |
22 |
0.18 |
99.3 |
0.7 |
1.0 |
37 |
16 |
| 宍道湖・3 |
24 |
24 |
23 |
23 |
0.74 |
96.8 |
3.2 |
1.0 |
24 |
12 |
| 釜谷沖 |
26 |
24 |
27 |
10 |
16 |
41.7 |
58.3 |
0.93 |
62 |
20 |
| 注) |
1 .濃度:分画それぞれの測定値
2 .1g 中の存在量:濃度×粒度÷100 |
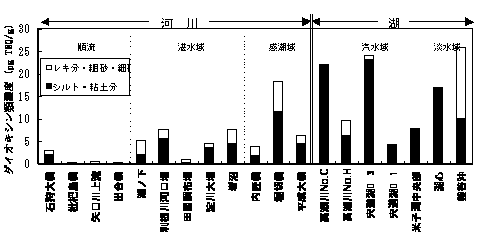
図-5.3.3 分画中のダイオキシン類濃度
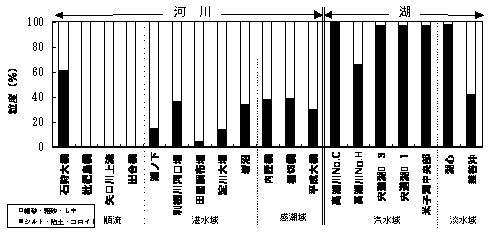
図-5.3.4(1) 細砂・粗砂・レキ分とシルト・粘土分の粒度組成
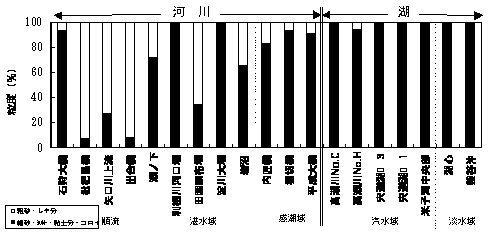
図-5.3.4(2) 粗砂・レキ分と細砂・シルト・粘土分の粒度組成
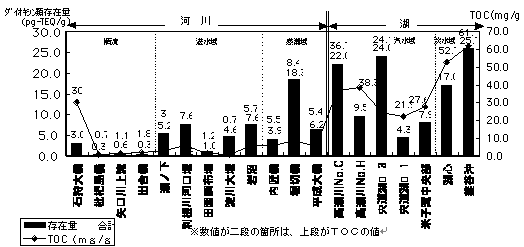
図-5.3.5(1) ダイオキシン類の存在量(総量)とTOC
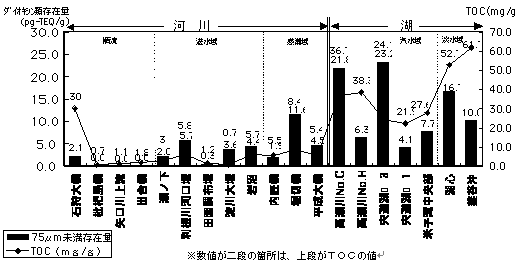
図-5.3.5(2) ダイオキシン類の存在量(75μm未満)とTOC
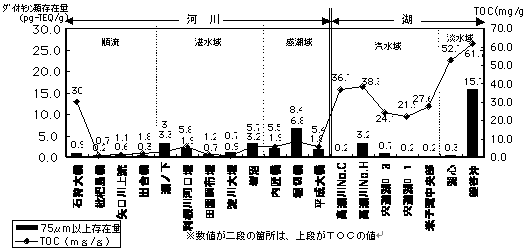
図-5.3.5(3) ダイオキシン類の存在量(75μm以上)とTOC
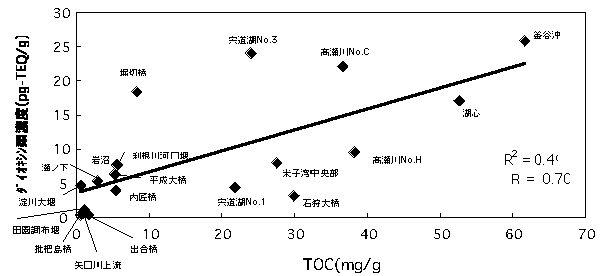
図-5.3.6(1) ダイオキシン類濃度とTOCの相関
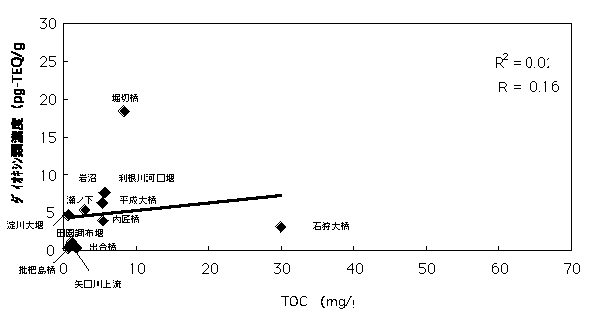
図-5.3.6(2) ダイオキシン類濃度とTOCの相関(河川)
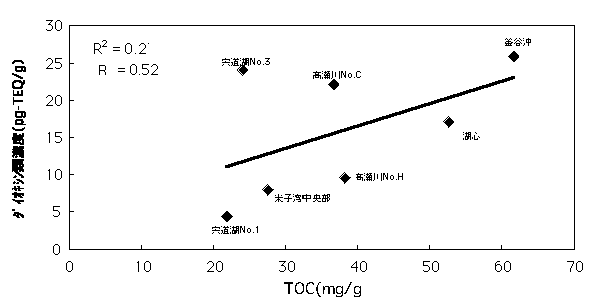
図-5.3.6(3) ダイオキシン類濃度とTOCの相関(湖)
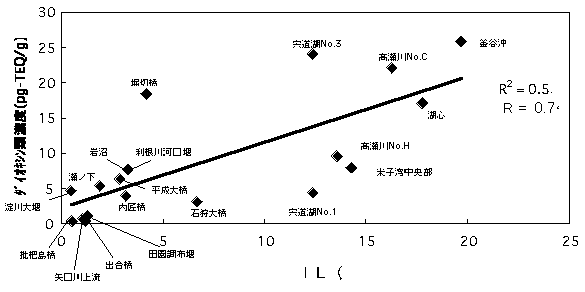
図-5.3.7(1) ダイオキシン類濃度とILの相関
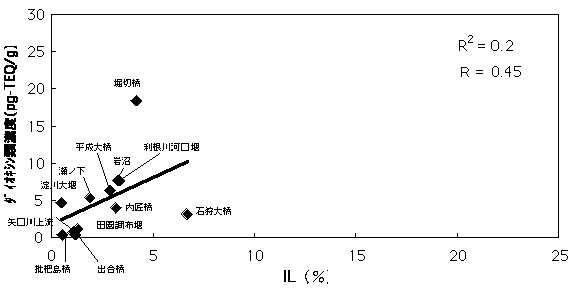
図-5.3.7(2) ダイオキシン類濃度とILの相関(河川)
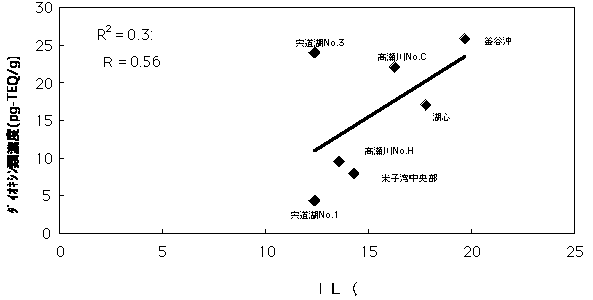
図-5.3.7(3) ダイオキシン類濃度とILの相関(湖)
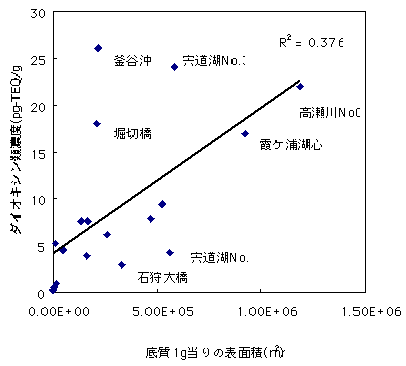
図-5.3.8 ダイオキシン類濃度と総表面積の相関
総表面積の求め方
粒子を球と仮定し、底質1g当りの表面積は次式により算出
Vi=(Wi/(100×ρ))×1000
Sa=Σ((si/vi)×Vi)
Vi:粒子の各粒径区分における体積(mm3)
Wi:各粒径区分における重量割合(%)
ρ:底質の密度(g/cm3)
Sa:総表面積(mm2)
si:各粒径区分における粒子1個あたりの表面積(mm2)
vi:各粒径区分における粒子1個あたりの体積(mm3)
粒径区分は、粒度組成より直径0.001〜2mmの間の14区分によった。
|