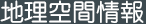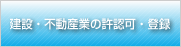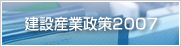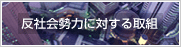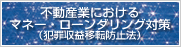地理空間情報課ラボ
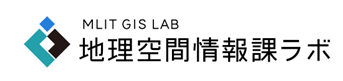
地理空間情報課ラボとは
国土交通省地理空間情報課では、様々な場面における地理空間情報の利活用を図るため、国土数値情報の整備・提供や不動産情報ライブラリの運営、データ連携環境の構築などに取り組んでいます。
近年の技術革新や社会・産業動向の変化は目覚ましく、生成AIの普及やビジネス・行政におけるデータ活用の深化など、地理空間情報を取り巻く環境やニーズは日に日に変化しており、私たちの取組も絶えずアップデートしていかなければ時代遅れのものとなってしまいます。
そのような想いから誕生したのが「地理空間情報課ラボ」です。このラボでは、地理空間情報を巡る最新の動向や技術を積極的に取り入れ、社会に眠るアイデアを掘り起こし、皆様との双方向のコミュニケーションを通じて、地理空間情報に関する取組をさらに進化させていきます。
スペシャルサポーター
「地理空間情報課ラボ」では、産学官の多様な分野でご活躍される皆様に「スペシャルサポーター」としてご協力いただき、多様な知識と経験を結集しながら活動を進めています。地理空間情報課ラボ スペシャルサポーター
令和7年度の取組
地理空間情報課では、令和7年度は以下のような取組を進めています。今後、このページで順次内容を紹介していきますので、ぜひご覧ください。
国土数値情報
令和7年度は、洪水浸水想定区域等の災害リスクデータの更新や、30年ぶりの道路データの更新、宅地造成等規制区域データの新規整備、AIを用いた土地利用データの整備手法の検討、建築基準法関連情報のGISデータ化ガイドラインの検討などを実施します。また、国土数値情報を活用したデータ分析コンペティション「第2回 国土交通省 地理空間情報データチャレンジ」を開催します。
現在、国土数値情報ダウンロードサイトの今後のリニューアルの検討に当たり、ご利用者様のニーズやご意見を参考にしたくアンケートを実施しています。
これまでのご利用状況や、感じている不便な点、今後期待する機能等を幅広くお伺いし、リニューアル時のサイト改善及びデータ改善につなげて参ります。
利用実態の把握にとどまらず、検索機能・データ形式・メタデータ・開発者向け機能等、将来的な提供方針を定める上で非常に重要な参考情報となりますので、ぜひ、忌憚のないご意見をお寄せください。
アンケートURL:https://forms.gle/YbuyYYqA11mYDiJUA【こちらのアンケートは、10/24(金)をもちまして終了となりました。ご協力頂きありがとうございました。】
不動産情報ライブラリ
不動産情報ライブラリは、令和7年度は・防災情報強化のため、災害履歴(水害・土砂災害・地震災害)、指定緊急避難場所(API)の追加
・ユーザのニーズが高い人口集中地区、都市計画道路の追加
・API操作説明の改良
を実施します。
不動産情報ライブラリはこちら↓
人流データ
令和7年度は、緯度経度に加えて高さ情報を持った三次元人流データの更なる利活用の拡大に向け、三次元人流データを用いた地域行政の課題解決を、いくつかの地域で試行的に実践します。また、地方自治体では、人流データの取得コストや理解不足が課題となり、利活用が進んでいない状況を踏まえ、AI等の先進技術を活用した取得・分析等コストの低廉化手法を調査し、実装可能性について検討します。土地境界データ
令和5年度に「登記所備付地図(不動産登記法第14条第1項)」がオープンデータ化されましたが、未整備の地域が多く残っています。そこで、多くの自治体が固定資産税の課税資料として作成している地番現況図に着目し、その利活用に向けた調査を進めています。また、自治体職員がこれれの土地境界データを活用し、不動産登記情報や自治体が保有する各種データと連携することで、課題解決するための手法を検討しています。
これまでの「地番現況図」を含む土地境界データと、不動産登記情報・ハザード情報・都市計画情報などを組み合わせた利活用アイデアの募集、土地境界データの利用状況や提供方法、仕様等に関するニーズについてのアンケートの結果を、結果を掲載しました。
また、自治体ごとに仕様が異なる地番現況図を共通の仕様に変換した10自治体分の試作データと、その作成プロセスを公開しております。
詳細は以下のリンクをご覧ください。
地理空間情報の連携環境
データを活用したまちづくりや、防災の高度化、新ビジネスの創出などを推進するため、PLATEAU(3次元都市モデル)、建築BIM(建物の3次元データ)、国土数値情報などの様々な地理空間情報を相互に連携させるツールの構築に向けた検討を行います。
令和7年度は、AI及びMCPサーバーにより、関係する多様なデータを簡易に取得できる環境の第一弾として、不動産情報ライブラリのAPIを対象としたMCPサーバ「地理空間MCP Server - MLIT Geospatial MCP Server -(α版)」の提供を行います。
土地履歴調査
土地履歴調査は、土地本来の自然地形やその人工的な改変状況、土地利用の変遷、過去に発生した災害履歴等の土地の災害リスクに関わる基礎的な地理空間情報の整備として、平成22年度から調査を開始し、これまでに三大都市圏や政令指定都市、一部の県庁所在地等の調査を実施しています。令和7年度は未整備となっている県庁所在地や中核市エリアのうち、東北、近畿、中国地方の整備を進めます。
令和6年度の取組
地理空間情報課の実験的取組紹介
地理空間情報課では、技術動向や社会のニーズを踏まえ、様々な実験的な取組や先進的な取組を行っています。
それらについて、検討過程が皆様から見えず、その結果のみが「報告書」等の形で公開されることが多くあります。
しかし、その過程を知ることで得られる示唆は多いと思います。また、課題にぶつかった際にはそれを皆様と共有し、皆様からご知見を頂くことで前に進めることもあると思います。
そこで、当課が行う実験的取組に関する情報提供と皆様との双方向のコミュニケーションを図る紹介ページを開設しました。
地理空間情報課の実験的取組紹介
データ連携に関する課題解決アイデア募集
地理空間情報の高度利用に当たり、様々な地理空間情報を正確かつ容易に連携させる必要性が高まっています。
一方、地理空間情報は位置情報の付与方法やデータ形式等が多様であり、特に情報の連携が困難であることから、地理空間情報課では、地理空間情報のデータ連携環境の構築に取り組んでいます。
データ連携については、研究者、エンジニア、データサイエンティスト、地理空間情報愛好家等、多くの方が独自の斬新なアイデアを持っていますが、その中には、まだ社会に眠るものも多くあります。
そのようなアイデアを政策に活かすため、地理空間情報課ラボの企画として「Geo Synergy Linkage Hub」を実施しました。
データ連携に関する課題解決アイデア募集 GeoSynergy Linkage Hub
地方公共団体様向け企画 デジタルマップをハブとした官民データの活用実装セミナー
地理空間情報は、不動産・建築・都市分野におけるDXを推進する上で不可欠なインフラデータであり、地方公共団体様におけるEBPMに基づく政策立案に不可欠となっています。
一方で、地理空間情報の整備・オープン化や利活用環境の構築はコストを伴うものであり、かつ、庁内外の多様な主体が関わるものであることから、予算や組織を整え、多様な主体を巻き込むことに困難を感じている地方公共団体職員様も多い状況です。
こうした状況を踏まえ、データの整備・オープン化、デジタルマップ整備及び民間とも連携した産学官におけるデータ利活用(サービスの創出)の一連のステップを2年間で実現した高松市都市整備局都市計画課主幹の伊賀大介氏(※スペシャルサポーターに就任いただいております)をお迎えし、マインドセット、ロードマップの設定から、予算の獲得や組織整備、多様な部局・事業者の巻込み方まで、地方公共団体様における官民データ活用を実装するための極意をお話いただきました。
地方公共団体様向け企画 デジタルマップをハブとした官民データの活用実装セミナー
国土交通省地理空間情報課X(旧Twitter)アカウント
国土交通省地理空間情報課のX(旧Twitter)では、 国土数値情報の整備予定や、整備を進めている不動産情報ライブラリ、人流データに関するイベント、「地理空間情報課ラボ」等に関する情報を発信していきます。
国土交通省地理空間情報課X(旧Twitter)アカウント
https://x.com/GIS_MLIT