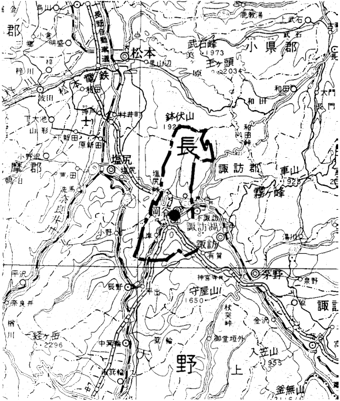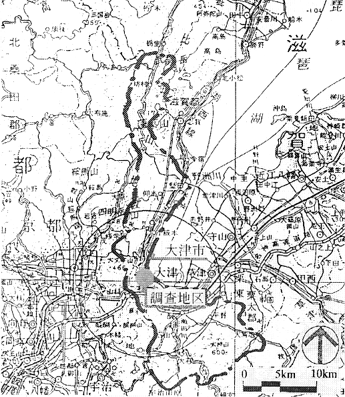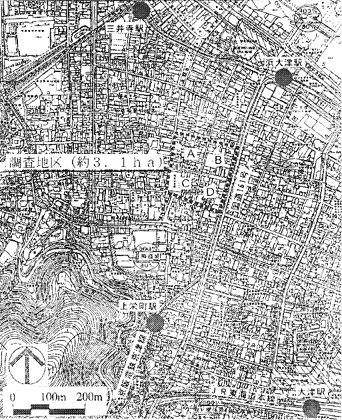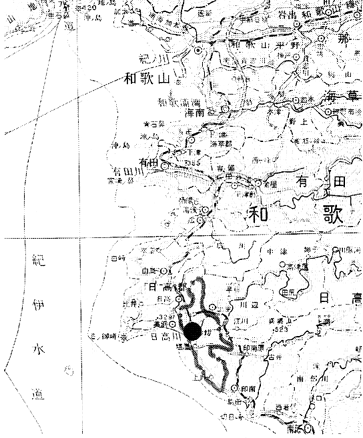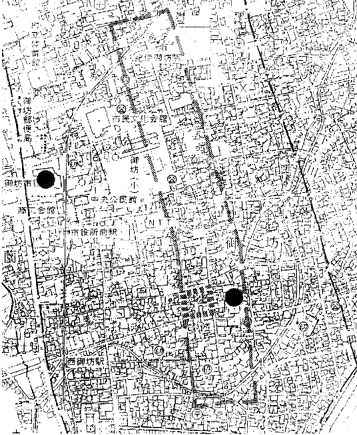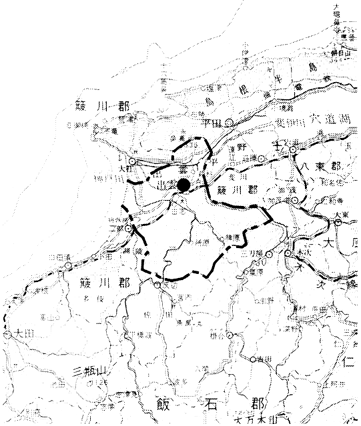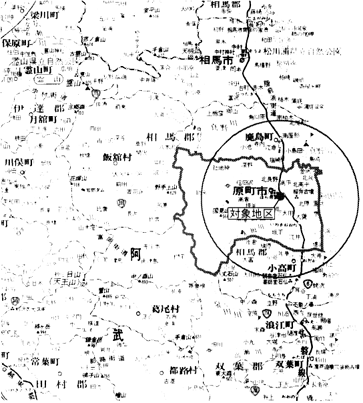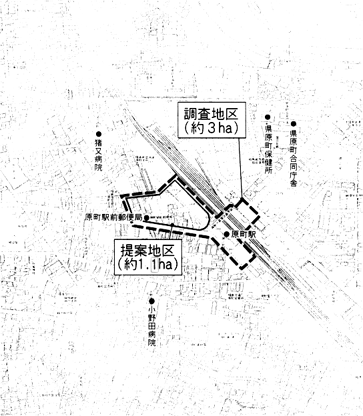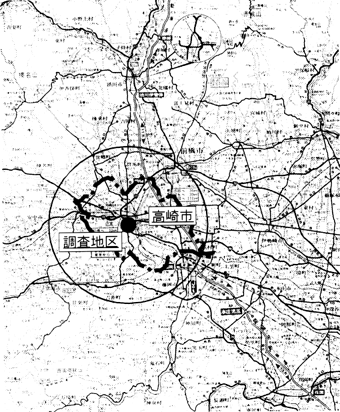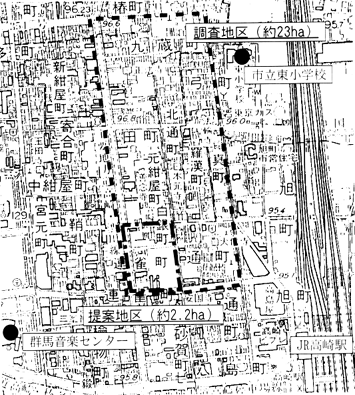土地利用
方向性
【中央通り4丁目商業会】
約15,000
住宅系用途10%
空き店舗、低・未利用地40%
(80%/400%)
準防火地域
都市計画道路 若宮線(未整備)
土地所有者
数53名
・商業機能の充実・強化とともに、都心居住機能や公共公益機能の導入等による都市機能の高度化をめざす。
【大津市】
30,850
住宅地28.2%
駐車場10.4%
社 寺3.8%
600/80
(一部500/80)
・大阪、京都への通勤には便利な位置にあるため、地区周辺で行われたマンション開発での販売状況は好調である。
【御坊商工会議所】
約190,000
住宅地46%
駐車場・空地6%
寺社4%
公共用地28%
農地2%
第一種住居地域200/60
・オークワ(店舗面積5,700㎡)が11月末に開店するのも上記のエリアである。
・調査地区の商店街沿いの路線価は下降傾向が続いているが、売地が発生しても買い手がつかない状況にある。
【高瀬川中央商店会】
約11,000
住宅地29%
駐車場・空地27%
道 路8%
その他14%
(400/80)
数32人
・開発の方向性は、商業系用途を基本としつつ、文化・コミュニティ機能と併設した複合型用途(一部、住宅の導入を検討する)である。
【原町市】
約30,000
住宅地5%
駐車場空地14%
道路22%
公的施設その他45%
近隣商業地域(300/80)
準工業地域(200/60)
借地権者3名
その他JR
・周辺街路の沿道商業機能整備
・駅東口の居住環境整備・交差点
・大型店・駅前等各拠点整備によるメリハリづけ
【高崎市】
約
230,000
住宅地3.8%
駐車場空地49.8%
道路23.8%
その他1.8%
一部(600/80)
土地所有者38名
借地権者6名
計44名
・機能構成は、商業と公共公益施設(市立図書館)を吸引の核とし、都市型住宅、駐車場などを検討する。また、商業施設内に、地元地権者によるチャレンジショップの配置などを盛り込むものとする。
2.調査の視点
(1)中心市街地活性化型の一般的な課題
①中心市街地の一般的な現状、問題点
・中心市街地を活性化することを念頭に置くためには、商業活性化上枢要な場所に位置していることとなる。
・本タイプにおける低・未利用地は、経緯からすれば、
○比較的大きな商業床を運営していた商業者の撤退
○商業者の経営的行き詰まりから来る空店舗化
○不良債権化した土地
○小規模老朽家屋の密集、狭隘な道路幅員、防災安全性、購買意欲の減衰の問題
○近年のモータリゼーションの進展、産業構造の変化、担い手の高齢化や後継者難等に伴う商業等のポテンシャルの低下、中心市街地内低未利用地のスプロール的な発生等が想定される。
・いずれにしろ、このような低未利用地ができたことは、商業環境の衰退が原因であり、その土地を商業活性化の視点で再活用しようということとなる。
・従来と同様の土地利用を単独で図るだけでは、活性化は不可能であり、地域社会一体としての改善を図ることを念頭に、対象地区でまず、何ができるかを考えることに他ならない。
・このような対応における共通かつ一般的な問題点としては、以下のように整理される。
a.地域の消費構造の変化
○地域消費人口の減少や地元商店街離れによる購買力の低下
○少子化、高齢化など消費属性の変化に対応できない商業環境
○消費に関する情報発信性や地域密着性・特異性の欠如
b.商業環境への対応
○商業環境の老朽化、均質化など買物客への購買アピール度の欠如
○郊外流出への歯止め策等の未対応
○商店街経営、個店経営上の問題、経済情勢、社会情勢への対応の遅れ
c.活性化に対する基盤施設
○自動車社会への未対応、歩行環境の未整備など消費購買力向上策の欠如
○地域社会の文化や歴史性の喪失、地元愛の欠如
○公共団体との連帯性や商工会等との連携方策
②中心市街地の一般的な課題
・対象地区は各都市の中心市街地において重要な位置にあり、当該地区のあり方が中心市街地活性化のカギを握っている。
・従って、以上の問題点を踏まえた上、中心市街地全体の魅力づくりを意識した整備が求められている。そのために地域の歴史性・文化性などの個性を生かし、商業の活性化を図ると共に地域のポテンシャルに見合った機能導入と景観形成が課題となっている。
・また、いかに地元住民や商業者の熱意・意識を向上させるか、地域一体となった取り組みのための組織づくりを行っていくかという点も課題としてあげられる。
(2)調査の視点
中心市街地活性化には、地元市民の自発的な活性化意欲の向上が不可欠である。そういった地元の意欲向上のためには、以下のような市民が活性化に参加できる仕掛けづくりが必要である。
○誰もが参加しやすい中心市街地活性化フォーラム等の組織づくり
○熱意ある商業者等から構成される、活性化に係わる取り組みを積極的に実行する部隊の結成
○組織の中でも先導役となるリーダーの育成
そういった組織が行政に依存する体質を協業へと転化させ、自助努力により実績を積んでいくことが成功体験となり、周辺へ波及していく。活動内容としては以下のようなものがあげられる。
○活性化のための積極的な企画提案
○まちづくり研究会、イベント等の取り組み
○企業の街づくりへの積極的な参加
また自発的に取り組んでいる地域に対し、行政も積極的に支援することが必要である。行政の活動としては以下のようなものが考えられる。
○まちづくりに関する相談窓口の設置
○組織づくりの先導、支援
○公共公益施設の中心市街地への設置
○まちづくりに関する教育の実施
本調査地区は、地区毎に衰退化の背景や地元の熟度が異なっているが、上記の点をうけて以下に重点をおいて調査を行なう。
①これまでの商店街を支えた歴史・文化を生かしたまちづくり
○現状のまち並み景観の問題点を明確にして、地域の歴史性・文化性等の資源を生かしたヒューマンスケールのコンパクトな(集約型のアクセシビリティの良い)歩いて暮らせるまちづくりや、歩いて楽しい歩行型商店街の形成を考慮する。
②導入機能の検討について
○中心市街地全体の活性化方策をうけて、活性化の先導的な役割を果たすための土地利用方針・導入施設方針を明確にする。その際、地域のポテンシャルを考慮し、将来像を見極めながら段階的な土地利用の形成についても検討する。
③事業手法について
○街区内の低未利用地を活用した建築物の整備について、a単独建築、b共同建築、c街区内の道路整備と共同建築、d道路等の基盤施設も含めた面的整備(土地区画整理事業)、e立体的共同建替え(再開発事業)等いくつかのケースについて検討する。また、公共的施設や公共的資金の導入についても検討する。
○敷地の整序と道路等基盤施設の整備を街区全体で一体的に行うことが困難なケースも考えられる。この場合、事業意欲のある地権者から段階的に建物の更新・共同化を図る方策も検討する。
④一店突破型まちづくり
○低密利用を維持しつつ、賑わい性、界隈性を持たせながら一店ずつ徐々に整備を行う。(一店突破型のまちづくりをスタートとする時間軸のシミュレーションの整理)
⑤合意形成について
○地元地権者の合意形成の図りやすさに視点を置いた計画案・事業手法の検討を行なう。また、合意形成を含めた今後の事業プログラムの検討と、当面の課題となる「核になる組織」の立ち上げ方策について検討する。
3.調査の方針
(1)調査の方針
本タイプでは中心市街地の活性化と低・未利用地有効活用の2つのアプローチから、中心市街地の魅力づくりのための低未利用地の有効活用を検討する。
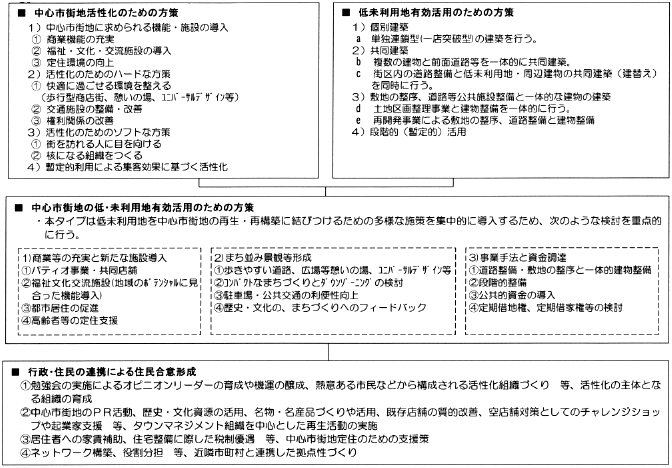
(2)タイプの類型化
中心市街地活性化方策として地区への導入機能、低未利用地の有効活用方策として整備方策の2つの視点から類型化を行う。
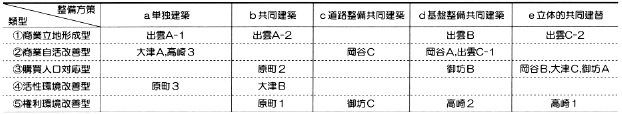
類型化の概要は以下の通り
①商業立地形成型
中心市街地の活性化を進める上で、他都市及び都市内での商業上の競合関係を考えたときに、競合先との商業戦争に勝ち、中心市街地への消費吸引力を向上させる見込みがある、つまり、新たな商業者の中心市街地への出店意欲があると考えられる場合、かつ、有効利用を図る土地が、中心市街地内での歩行者消費回遊動線に位置し、競合に打ち勝つだけの商業施設(駐車施設も含む)の規模が確保可能な土地面積を有している地区。
②商業自活改善型
新たな商業施設の出店による中心市街地の活性化を図るには、出店者の意欲が期待できず、また、そのための大規模な投資を、現時点で回収する見込みが薄い場合であり、経年で小売店の売上げを少しづつでも向上させていき、徐々に地元商業者の意欲の向上を期待しつつ、外部テナントの出店意欲の向上を進めていくことが必要な地区。内容としては空店舗を活用した一日学生体験店主、チャレンジショップの設置、地域密着型のイベント展開、消費者ニーズへの的確な対応、テナントミックス、協調建替・改修などによるリニューアルを進めるべき地区。
③購買人口対応型
地域商業を支える地域消費人口の減少、人口の高齢化に伴い減少する消費絶対量、少子化に代表される寝るだけ居住地など、商業活性化の前提として、消費人口のニーズに対応した商業環境形成のみでは成立できず、積極的に消費人口の増加を進める必要のある地区。都市居住の推進による定住人口の増加を進めるため、住宅施設を積極的に取り入れ、入居者属性に沿った商業環境の改善を進めること、居住者が永続的に住める居住に必要な各種施設を導入する、消費以外でも来街者を増加させるための各種施設を導入するなどにより活性化を支援すべき地区。
④活性環境改善型
商店街の佇まいはそれなりに整っているが販売額が減少している、来街者が目的消費のみであり街の滞留時間が短い、商店街に特徴や面白味がない、商店街に安らげる場所がない、消費者が集まりにくく歩きにくいなどのような、消費者側の商店街に対する不満が顕在化しているような場所において、消費者の立場に立って商店街の環境改善を進める必要のある地区。消費行動を誘発する歩道の色・構造や幅、店舗の統一感ある景観統制、歴史や文化と消費の関連性強化、巡回バスなどのアクセス性強化などといった対応が必要な商店街の中に存在する地区。
⑤権利環境改善型(土地権利整序型)
商業環境活性化を着実に、かつ、タイミングよく、進めることが必要であり、また、そのためには重要な場所を占める土地であるが、権利関係が複雑多岐にわたる状況であったり、目的とすべき施設が敷地条件的に確保できないなどの要件で土地の有効利用が進まなかったり、周辺の土地と一体で進めるほうが効果的であると思わるような地区において、その有効利用を図るべき規模とその効果を見極めながら、適切な手法を導入しなければ、中心市街地の活性化が進まないと考えられる地区。