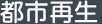まちなかの居心地の良さを測る指標(改訂版ver.1.1)
国土交通省は、「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成に取り組む地方公共団体や民間まちづくり団体等を支援するため、居心地の良い空間が形成されているかどうかをより人間らしい視点から把握し、改善点を発掘するツールとして「まちなかの居心地の良さを測る指標(改訂版ver.1.1)」(以下本指標)を作成*しました。
「まちなかの居心地の良さ」を様々な観点から計測し、皆さんの空間を見直してみませんか?ぜひ多くのエリアで活用していただければと考えています。
*令和5年度に公表した「まちなかの居心地の良さを測る指標(改訂版ver.1.0)」をベースに、複数の異なる特性を持つエリアで、実値計測、来街者へのアンケート、ワークショップを実施し、調査者と来街者の主観の乖離等を分析した結果等を踏まえ改訂
改訂版ver.1.0からの変更点は概要資料をご覧ください。
概要
○背景・経緯
-
令和元年6月26日、「都市の多様性とイノベーションの創出に関する懇談会」の提言として、『「居心地が良く歩きたくなるまちなか」からはじまる都市の再生』が取りまとめられ、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成に必要となる要素の一つとして「量に加え、交流・滞在など活動の質も重視する」ことが挙げられました。
-
さらに、令和3年4月6日、「デジタル化の急速な進展やニューノーマルに対応した都市政策のあり方検討会」の提言として、都市アセットを利活用して行われている活動の内容や都市の利便性に着目し、市民のQoL向上の度合いを可視化する評価指標を設定することが重要であると取りまとめられました。
-
これを受け、国土交通省では、居心地の良い空間が形成されているかどうかを、より人間らしい視点から把握するため、地方公共団体や民間まちづくり団体等のまちづくりの実践者に、まちづくりに取り組む場所でお使いいただくものとして本指標の作成に取り組みました。
○目的
-
これまで、都市空間の状態を把握する際、「滞在者・通行者の量」や、インフラ施設の整備状況や構造物/工作物の設置状況といった「ハード環境」より、その状態を定量的に把握する手法が一般的でした。
-
日本の都市が成熟期に入り、「新たにつくる」だけではなく「場を活用」するまちづくりが重要視され、都市は市民生活の最低限の機能を満たすものから、市民一人ひとりが輝ける舞台として、市民のQoL向上を下支えするものとなっていく必要があります。
-
そのため、施設の整備状況や交通量、滞在者・通行者数といった「量」の把握に加え、都市がどのように利用され、どのような活動が行われているかといった「質」に着目することが重要です。
-
本指標では「都市空間の質」について、「居心地が良く歩きたくなる」まちなかを目指し、空間の状態に加え、滞在者がどのように感じ【主観】、どのように利用しているか【活動】を把握することで 、これまで捉えることが難しかった「まちなかの居心地の良さ」を可視化しています。
-
本指標をKPIとして高頻度でPDCAを回すことで、本質的に居心地が良く、使われるまちなかになることが期待されます。また、本指標により、まちづくりの取組から得られた効果をこれまでよりもわかりやすく多角的に可視化することで、ステークホルダーとのコミュニケーションが充実し、活動意義と継続の必要性の共感の輪を広げることができます。
○本指標の構成
本指標は、居心地の良さを安心感・寛容性・安らぎ感・期待感の4つの要素にグルーピングし、対象地を要素ごとに把握します。居心地の良さの4要素には各項目の指標を設定し、項目ごとに【主観】と【活動】を計測します。
本指標で把握する対象は、以下のとおりです。空間の状態と関連する項目は、参考情報として記録します。
・居心地の良さ(安心感・寛容性・安らぎ感・期待感)
・空間の状態(沿道建物・土地状況、機能・設え状況)
・関連する項目(基礎情報、滞在者・通行者確認)
本指標を用いて測定した結果は、グラフで簡便に可視化することができ、対象地における居心地の良さを構成する4要素の各項目の現状を確認することができます。ただし本指標は、異なる都市間の比較のためではなく、特定のエリアで継続的に行う取組を向上させるためのツールですので、エリアの特性に応じて、まちづくりの実践者が自ら指標を設定することが重要です。
各種資料
・概要資料
・活用の手引き
・調査票
・分析ツール(記入用)
・分析ツール(記入例)
(参考)まちなかの居心地の良さを測る指標(改訂版ver.1.0)
まちなかの居心地の良さを測る指標(改訂版ver.1.1)以前の指標も引き続きお使いいただけます。
・概要資料
・活用の手引き
・調査票
・分析ツール(記入用)
・分析ツール(記入例)
- 国土交通省都市局まちづくり推進課
- 電話 :03-5253-8111(内線32554・32575)