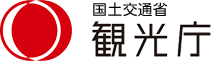サステナブルな旅アワード
最終更新日:2026年1月9日
実施概要
「サステナブルな旅アワード」は、コロナ禍を経て持続可能な観光への意識が高まる中、2023年に創設しました。優良な旅行商品・取組を広く表彰することで、我が国における持続可能な観光への取組を推進し、旅行業界や旅行者の意識醸成を図ることを目的としています。
本アワードをきっかけに、持続可能な旅行商品が増加し、旅行者にとって魅力的な旅行の選択肢が広がることを目指します。
本アワードをきっかけに、持続可能な旅行商品が増加し、旅行者にとって魅力的な旅行の選択肢が広がることを目指します。