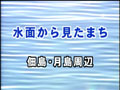



|
[オープニング(隅田川)]
東京の水辺は4つの段階を経て評価されてきたと言われています。
第1段階は、1970年代の隅田川から始まる水辺の復権です。東京オリンピックのころに悪くなった川の水質が少しずつよくなり、魚が戻り、自然が回復します。レガッタや花見、花火が回復し、屋形船が復活します。
|



|
[オープニング(隅田川)]
第2段階は、水辺に住宅を造ろうと、大川端のリバーシティ21が誕生しました。これが1980年代前半です。
第3段階は、ロフト文化と呼ばれています。その後、ウォーターフロントブームと呼ばれるようになります。芝浦の倉庫を利用したライブハウスに行く、レストランで食事をする、シーボートという船で東京湾に出かけていって結婚披露宴を水上で行うことが流行となりました。
第4段階は、それを追いかけるようにして訪れました。オフィスビルの建設ラッシュが1985年、86年のバブル期の現象でしたが、東京の水際にはたくさん倉庫があったため、それをオフィスビルとして建て替えるという現象が起きました。それが現在にも続いているのです。
しかし、熱っぽいブームが過ぎ去った結果、オフィスビルばかりが建ち並んだ空間が水辺に残りました。一般の人が水辺に来る、ヨーロッパやアジアに見られる活気ある水辺が、東京に実現することが期待されているのです。
|




|
[新月島川(浜前橋〜新島橋)]
隅田川の河口に近い月島は、かつて埋め立てによって造られたまちです。
この水辺には、懐かし東京の姿と最も新しい利用が重なり合って、若い人々を引きつける水辺の魅力を生み出しています。
新月島川の左側には、小さなマリーナがあります。
ここは、かつて、船の焼玉エンジンをつくっていた工場があった場所です。そのお陰で、現在も船が接岸でき、そこにはコーヒーショップがあり、若い人たちが集まる拠点となっています。こういう水辺の利用を広げることが、多くの人に望まれる時代になってきました。
[朝潮運河(黎明橋)]
これは、朝潮運河です。
運河も時代によって川幅が違います。江戸時代は船も小さく、掘割は狭いものでした。蔵も小さかったのです。
その後、掘割は、東京の外側に拡大し、埋立地を次第に増やしていきました。
その時に掘割や運河に囲われた埋立地を「島」として造ってきました。このようにして、東京の水際線は、次第に増えていきました。江戸の掘割は、その後、ずいぶん埋められましたが、一方では近代に造られた運河も多くありました。新たな埋め立て地は定規で引いたような真っ直ぐなラインとなり、区画も大きくなりました。そこには物流基地が造られましたが、現在は、また機能を変えつつあるのです。このように、水辺というのは大いに利用価値があったのです。ほどよい幅を持っている近代の運河は、現代のニーズにぴったりと合っています。
|




|
[(黎明橋)]
ここが、トリトン・スクエアです。
オフィス、商業、文化施設をミックスさせています。東京には、このような再開発のコンプレックスが、多く造られましたが、ここは現在、東京の人気スポットの1つです。水際を低層で押さえて、いろいろな商業施設を入れて、背後にオフィスが来るという工夫をしています。
[(晴月橋)]
この辺りは、大変おもしろい場所です。
フローティングの家があり、東南アジアに来たような風景です。アムステルダムやパリにはボートハウスがたくさんあります。そこには、電気もガスも水道もあって、郵便も届く、そういう優雅な生活を船の上でしている人達が多くいて、高級な船の家といった趣です。東京でもやってみるような思い切った可能性が、ここにはあります。
[(朝潮橋〜朝潮大橋)]
月島の教会です。
石垣も戦前の古いものが残っています。
月島は地域の歴史をとどめています。この内部には、路地を生かした庶民的な住宅が多く残っており、昔からの地域コミュニティも継続しています。
|




|
[晴海運河]
しかし、バブルの時代には、いわゆる地上げの影響を受けました。これに対して、佃島ではコミュニティの結束が非常に固く、地上げから地域を守り抜きました。自分たちの住まいの環境を守り切ったのでした。地上げに対しては、1軒も家を売らぬ見事な結束を示したのです。そのため、佃島では現在も路地と木造の古い住宅が残っており、緩やかな建て替えはあるものの、大規模な建設は行われませんでした。佃島は地域の個性を保ちました。
一方、月島は、明治中期以後の開発で造られた地域だったため、佃島ほどのコミュニティの結束が生まれませんでした。開発が進み、歯抜けになった空地が多くなり、そこには最近、ぞくぞくと新しいマンションが建てられています。人が都心に戻ってくるのは、望ましいのですが、やはりもとの水で囲われた島の環境、地域個性は守りたいものです。
|