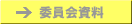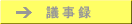道路行政マネジメントに関するこれまでの取組み(平成15年度業績計画書の策定、地域レベルでの策定、概算要求への反映など)について紹介し、各委員より下記の意見をいただいた。次回研究会においては、下記意見をベースに論点を整理し、具体的な課題に対する検討を行うこととされた。
(委員の主な意見)
|
| ○ |
業績予算と指標の関係について |
| ・ |
参考資料2-3の平成16年度の概算要求額について、対前年度比で合計1.10となっているが、これはシーリングを踏まえたものなのか。
(対前年度比3%削減となっているが、要求としては、その2割増まで要求できることとされている旨、道路局側より説明) |
| ・ |
資料2P.10の表によれば、業績予算の各費目が業績計画書の17指標とリンクしているが、各事業の効果は1つに限定されるものではない。成果指標による評価を行っている自治体の結果を見ても、狙い通りに改善する指標と悪化する指標が半々である。予算を立てる段階では良いかも知れないが、評価する段階で効果が別の指標に現れた場合等、思惑と違う結果となった場合にどうするのか、心配である。
(指摘のとおりであり、予算の費目と指標が必ず一対一で対応するものとは考えていない。しかしながら、道路行政の姿勢を見せる意味でも、一つの試みとして、取り組んだものである。ご指摘いただいた課題等については、引き続き検討する旨、事務局より返答)
|
| ・ |
行政マネジメントは、初めから完全なものを構築できるわけではなく、漸進主義で良いのではないか。予算と指標が一対一で対応しないのならば、一対多とすれば良いし、指標の設定等についても、常に見直しを行っていくべきである。
|
| ○ |
業績計画書について |
| ・ |
参考資料2-5の都道府県版業績計画書を見ると、予め実施するもの(事業)が決まっていて、それに対する理由付けを行っているという印象を受ける。それでも透明性の向上には寄与していると思われるが、本来はユーザーの問題意識に対し、より効果の高い手法(事業)を提案すべきである。今のアプローチだと、対応(解決)する事業がない問題については、対象から除かれる可能性がある。また、道路行政マネジメントに対する現在のアプローチは問題解決型であるが、未然に防ぐための方策についても検討する必要がある。
(以前、地元のニーズを適切に把握するためには、評価時点のみではなく、計画策定時点からの関係者の参画が不可欠だとのご指摘をいただいた。この点は今後の課題として取り組んでいく旨、事務局より返答)
|
| ・ |
利用の機会を評価する指標が少ない気がする。損失時間等は、負荷(需要)に対するアウトプットを表すものであって、需要が少ないところの評価は低くなってしまう。道路整備によって提供される利用機会についての観点で評価をすべきである。 |
| ・ |
コストに対する成果という視点――「効率性」が少ない印象を受ける。
(効率性についての意識は当然持っているが、まずは「成果」を前面に出したものである旨、事務局より説明) |
| ・ |
評価にあたって、「達成すること」に主眼を置くのならば、簡単な目標を設定すれば良いということになる。本当に道路に求められているものの中には、簡単には達成できないような問題もある。そのように、効果が上がりにくいが必要な指標等についても、検討すべきである。 |
| ・ |
どこまでやるかは行政の哲学にも結びつくが、手段志向ではなく、成果志向の行政マネジメントを行うべきである。地域の担当者の不安は、手段志向となっていることからくるものではないか。例えば、国民保険担当から健診率を高めることの発想は少ない。道路担当者は、交通安全も道路のことを考えがちとなっている。成果志向の手段を検討することで、各地域で本当に求められる道路整備を把握することができる。
|
| ○ |
職員の意識改革について |
| ・ |
効率性の向上に際しては、職員の意識改革が最も重要である。業績計画書を作ることが目的化されてしまってはいけない。自治体レベルでは、行政評価が導入されてから、ある程度経過しているところもあるので、自治体職員の意識との擦り合わせを行っていく必要がある。
(道路行政に対する本当のニーズは、現場の事務所の職員の方が却って正確に把握している。道路局では事務所と本省との間で人事異動もあり、その点ではニーズを把握しやすい体制にあると考えられる。今後、情報の循環のあり方についても検討する旨、事務局より返答)
|
| ・ |
意識や風土、習慣といったものは長年の間に構築されたものであり、一度に改革が行えるものではない。(行政評価に取り組んでいる)ある自治体の職員へのアンケートでは、「意義は認めるが、効果が上がっているとは思えない」という回答が多い。意識改革には時間とお金がかかるものであり、必要ならば予算化し、粘り強く浸透させていく必要がある。(研修、集会など行っているが、それだけで十分だとは思っていない旨、事務局より返答) |
| ・ |
日本の行政職員は、諸外国と比較してもモラルは高い方だと思う。しかしながら、ある程度の社会資本が概成した今日では、さらに1ステップ上の意識を持ち、行政マネジメントによる評価を行っていくべきである。 |
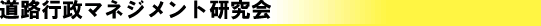
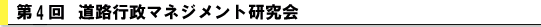
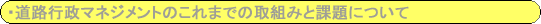
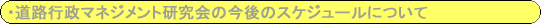

 第1回道路行政マネジメント研究会へ
第1回道路行政マネジメント研究会へ 第2回道路行政マネジメント研究会へ
第2回道路行政マネジメント研究会へ 第3回道路行政マネジメント研究会へ
第3回道路行政マネジメント研究会へ 第5回道路行政マネジメント研究会へ
第5回道路行政マネジメント研究会へ 第6回道路行政マネジメント研究会へ
第6回道路行政マネジメント研究会へ 第7回道路行政マネジメント研究会へ
第7回道路行政マネジメント研究会へ 第8回道路行政マネジメント研究会へ
第8回道路行政マネジメント研究会へ 道路局トップ
道路局トップ