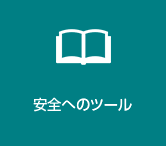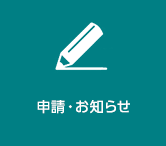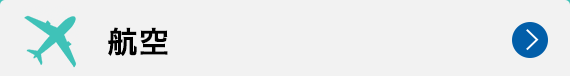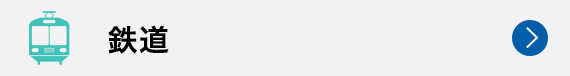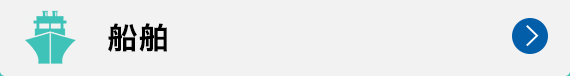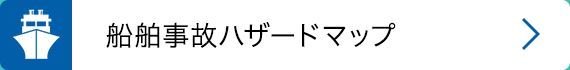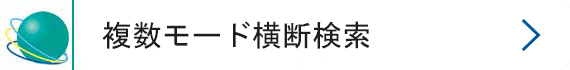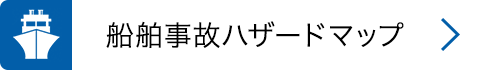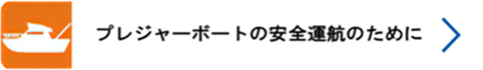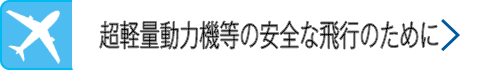委員長からのメッセージ
運輸安全委員会の更なる発展に向けて

運輸安全委員会は、昨年10月1日に満15年を迎えました。航空・鉄道・船舶の三つのモードにわたる事故等の原因を究明し、再発防止、被害軽減のための施策・措置を提言することにより、公正・中立の立場から運輸の安全を守る要となる重要な役割を担っていることを改めて自覚し、更なる発展のために努力を続けてまいります。
当委員会ではコロナ禍を経験する中で、近年発生していない大規模事故に対応する準備をしておく必要があるとの認識から体制作りを行ってきましたが、令和4年4月23日に発生し、令和5年9月7日に最終報告書を公表した旅客船KAZUⅠ沈没事故の調査に生かすことができました。今回は、海事部会が主体であるものの、航空部会、鉄道部会の全委員が参加し、様々な経験を生かしつつ多面的な分析、検討を行いました。
本事故では当初、船体調査ができず調査は困難を極めました。しかし、可能な範囲での初動調査は懸命に進め、本事故当日の本船の位置情報(GPS)や乗船者が撮影したと思われる写真等のデータについて、ご家族の方々からご提供頂くことができ、運航中の旅客船の位置情報を得ることができました。これにより、海象・気象シミュレーション結果と合わせ、旅客船の状況を科学的・定量的に推定することが可能となりました。また、船体が引き上げられ調査が可能となった段階で、委員を含む調査官が集中的に調査を行うことができ、船体外板に浸水経路となる損傷はないこと、ハッチの破壊状況、上甲板下の区画を仕切る隔壁に開口部があったこと、エンジン停止の原因推定等が共通認識として共有できたことは、効率的な調査を進める上で大きな一歩となりました。さらに、最近導入された3Dレーザースキャナー(固定型+ハンディー型)をフル活用し、船体寸法・形状の定量化ができたことも大きな成果でした。このデータは、その後のハッチの開閉、ハッチからの海水流入、旅客船の船体傾斜状況のシミュレーションによる科学的・定量的分析に繋がりました。
上記のハード的側面の調査・分析は、その後の多くの関係者への口述聴取により裏付けられ、主に事故のハード的側面を記述した経過報告(令和4年12月15日公表)に結実しました。また、これらのハード的側面の調査や定量的な分析を基礎に、ソフト的側面の検討が十分にできるようになったと考えます。ソフト的側面の検討については、人間や組織に関わる面が多く、表現方法を熟慮した記述も求められましたが、議論・検討を経て、最終報告書の取りまとめに至ることができました。また、これまでの報告書より一歩踏み込んで、早急の対応を期待する「今後期待される施策」と、地域・観光における継続性のある安全確保が必要な点を指摘した「地域における安全文化の醸成に向けて」を最後に記述しました。運輸安全委員会がどこまで踏み込んで提言していくかについては議論の余地があるとも考えますが、独立性を担保された当委員会でしか行えない提言は今後とも必要であると考えます。
さて、平成30年10月に発足10周年を迎えた運輸安全委員会は、それまでの皆様からの期待や要請を真摯に受け止め、確実に応えていくとともに、交通・運輸の安全確保をより一層推進するとの観点から、組織を挙げて「業務高度化アクションプラン」を策定し、取り組んできました。機能面で3つの柱、「分析力・解析力の強化」、「発信力の強化」及び「国際力の強化」を設定し、これらを実現するために「組織力・個人力の強化」の観点を加え、これまで以上に質の高い目標を設定して、新しい業務改善の取組を推進して参りました。この4つの取組は、旅客船KAZUⅠ沈没事故の調査にも生かされましたが、引き続き推進していく必要性も感じました。
ここ数年は継続的に、意欲のある行政系、技術系新卒職員の採用もあり、それら採用者の人材育成とともに、調査官・事務官についても継続的な能力向上のための国内・国外研修に努めたいと考えます。また、当委員会ならではの貴重な調査結果の統計、データ分析から事故等の傾向や共通要因などを取りまとめた「運輸安全委員会ダイジェスト」の発行やホームページにおいての周知啓発活動にも注力いたします。さらに、グローバルに連携した事故等調査にも貢献できる国際力の強化を推進いたします。
皆様のご理解とご協力を賜りますようにお願い申し上げます。
令和6年1月
運輸安全委員会委員長 武 田 展 雄