

<持続可能性>モビリティ
Project Member

吉田 有美子

山城 佑太

稲吉 裕俊

伊賀本 雅義

石川 雄基
日常生活を営む上で、
移動手段の確保は必要不可欠
人口減少により、交通サービスの需要の減少や労働力不足が深刻化し、地域公共交通は厳しい状況に置かれている。高齢者の運転免許の返納も増加する中、地域の生活の足の確保が喫緊の課題である。
国土交通省では、地方公共団体が交通事業者や利用者などの多様な関係者と連携し、地域公共交通のマスタープランを策定する制度を創設した。

過疎地では、自家用有償旅客運送、福祉輸送、スクールバスなどを総動員して、生活の足を確保する取組みを支援。同時に、地域のバス事業者間の運賃・ダイヤの調整や共同運行も可能にした。
オンライン予約やキャッシュレス決済を利用し、複数のモードやサービスを組み合わせて一人一人のニーズに最適化するMaaS(マース:Mobility as a Service)の推進。

AIオンデマンド交通やシェアサイクル、グリーンスローモビリティの導入。自動運転車両の安全基準の策定や、中山間地や高速道路での実証実験も進めている。日本全体を見渡すと、日本の大動脈である新幹線の整備、海外に目を向ければ、空港の運営や国際航空ネットワークの構築まで。
人々の移動をデザインする方法は、一つではない。

Project Member 政策に携わる職員紹介
-

吉田 有美子
航空局
航空ネットワーク部首都圏空港課
企画係長 -

山城 佑太
東北運輸局
交通政策部交通企画課長 -

稲吉 裕俊
物流・自動車局
車両基準・国際課 係長(自動運転・サイバーセキュリティ担当) -

伊賀本 雅義
総合政策局地域交通課
地域交通計画調整官 -

石川 雄基
鉄道局幹線鉄道課
課長補佐
日本をつなげるStory 首都圏空港の安全・安心のために
議論を重ねて必要な取組に繋げる
日本の国際競争力の強化や、訪日外国人旅行者の受入拡大などの観点から、首都圏空港(羽田空港・成田空港)の機能強化が必要です。そのためには、安全対策を講じること、安全対策等の取組についての情報提供が必要となり、日々どういった取組をすべきなのか、チームや他部署の関係者と議論を重ねています。
着任したての頃は専門用語が多く苦労することが多かったですが、日々勉強すること・分からないことを恥ずかしがらず質問することを心がけ、次第に議論に加わることが出来るようになっていきました。各部署の立場やチーム内で意見が異なることもありますが、丁寧に議論を重ねることや積極的に他部署とコミュニケーションを図ることで業務の調整を行うことが私の日々の仕事です。
この仕事に携わるまでは、飛行機が毎日安全に離発着するのは当たり前のように感じていましたが、実際は、安全・安心の確保に向けた取組が着実に実施され、あらゆる対策を講じながら運航されています。飛行機を飛ばすことに付随する様々な課題について真剣に考え、日々勉強しながら業務に取り組んでいます。
議論を重ねて必要な取組に繋げる
日本の国際競争力の強化や、訪日外国人旅行者の受入拡大などの観点から、首都圏空港(羽田空港・成田空港)の機能強化が必要です。そのためには、安全対策を講じること、安全対策等の取組についての情報提供が必要となり、日々どういった取組をすべきなのか、チームや他部署の関係者と議論を重ねています。
着任したての頃は専門用語が多く苦労することが多かったですが、日々勉強すること・分からないことを恥ずかしがらず質問することを心がけ、次第に議論に加わることが出来るようになっていきました。各部署の立場やチーム内で意見が異なることもありますが、丁寧に議論を重ねることや積極的に他部署とコミュニケーションを図ることで業務の調整を行うことが私の日々の仕事です。

この仕事に携わるまでは、飛行機が毎日安全に離発着するのは当たり前のように感じていましたが、実際は、安全・安心の確保に向けた取組が着実に実施され、あらゆる対策を講じながら運航されています。飛行機を飛ばすことに付随する様々な課題について真剣に考え、日々勉強しながら業務に取り組んでいます。


吉田 有美子
航空局航空ネットワーク部
首都圏空港課企画係長
平成31年入省(総合職事務系)
海上保安庁、不動産・建設経済局を経て現職。

日本をつなげるStory 現場で行う「顔の見える」仕事の面白さ
東北地方の地域公共交通の活性化を様々な形で支援
東北運輸局では、東北6県の地方公共団体や交通事業者など関係者の連携・協働による、鉄道、バス、タクシーなど地域公共交通の活性化に向けた取組を様々な形で支援しています。私たちの最大のミッションは、現場で法律・予算等の制度が適切に機能し、活用されるよう支援すること。さらに現場の困りごとを本省に届け、制度の運用に反映させることです。時には足を運んでその地域が抱える課題を聞き、活用できる制度を提案するなど、プッシュ型の支援を心がけています。
本省時代に広く一般を対象とした制度をつくる機会は多々ありましたが、運輸局では現場担当者とのコミュニケーションが重要な「顔の見える」仕事がほとんどです。また、自分次第でやれることは無数にあり、自分の仕事が地域の取組の後押しに直結します。そこに面白さを感じます。
様々な地域の現状もクリアに見えるようになりました。地方公共団体内部にもそれぞれ課題があり、「交通担当は一人しかいない」「新規支援策の活用まで手が回らない」等の話を聞いたときは衝撃を受けました。現場で制度を運用することは必ずしも容易ではなく、地域に寄り添った支援が重要であることを痛感しました。
その意味でも、地方運輸局という現場組織があることは国土交通省の大きな強みです。東北地方の「おでかけの足」の確保、ひいては、地域住民の豊かな暮らしの実現や地域の活性化に向けて、今後も現場の声を聞いていきます。
東北地方の地域公共交通の活性化を様々な形で支援
東北運輸局では、東北6県の地方公共団体や交通事業者など関係者の連携・協働による、鉄道、バス、タクシーなど地域公共交通の活性化に向けた取組を様々な形で支援しています。私たちの最大のミッションは、現場で法律・予算等の制度が適切に機能し、活用されるよう支援すること。さらに現場の困りごとを本省に届け、制度の運用に反映させることです。時には足を運んでその地域が抱える課題を聞き、活用できる制度を提案するなど、プッシュ型の支援を心がけています。
本省時代に広く一般を対象とした制度をつくる機会は多々ありましたが、運輸局では現場担当者とのコミュニケーションが重要な「顔の見える」仕事がほとんどです。また、自分次第でやれることは無数にあり、自分の仕事が地域の取組の後押しに直結します。そこに面白さを感じます。

様々な地域の現状もクリアに見えるようになりました。地方公共団体内部にもそれぞれ課題があり、「交通担当は一人しかいない」「新規支援策の活用まで手が回らない」等の話を聞いたときは衝撃を受けました。現場で制度を運用することは必ずしも容易ではなく、地域に寄り添った支援が重要であることを痛感しました。
その意味でも、地方運輸局という現場組織があることは国土交通省の大きな強みです。東北地方の「おでかけの足」の確保、ひいては、地域住民の豊かな暮らしの実現や地域の活性化に向けて、今後も現場の声を聞いていきます。

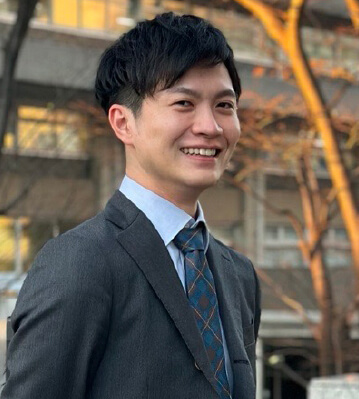
山城 佑太
東北運輸局交通政策部
交通企画課長
平成28年入省(総合職事務系)
住宅局、自動車局、大臣官房を経て現職。

日本をつなげるStory 前例のない世界を構築する
「自動運転」の安全基準策定というチャレンジングな課題に邁進
近年、自動運転車が発表され、地方部では無人自動運転移動サービスが開始されるなど、いよいよ「実用化」の段階へと進む自動運転技術。私のミッションは、自動運転の安全基準を策定し、安全性を確保した技術開発や社会実装を着実に推進することです。また、自動車は国際流通商品のため、各国の安全基準をそろえる必要があります。国連の自動車基準調和世界フォーラムにおいて日本の先進的な技術を国際基準に反映し、積極的な発信により国際的な議論をリードしていくことも私の大きな役割です。
今現在、完全な自動運転は実用化されておらず、その制度づくりはまだ誰も成し遂げていないブルーオーシャンな分野です。前例のない世界で、安全基準をどのように作り上げていくのか。構想力が求められるチャレンジングな課題であるとともに、将来の自動運転社会の姿を思い浮かべるとワクワクするテーマでもあります。このような分野の制度設計に最前線で携われることは大きなやりがいです。 新しい技術も、安全でなければ社会に受け入れられません。一方で、日本の安全基準をガラパゴス化させてしまっては、せっかくの技術が世界から取り残されてしまいます。時には現場に足を運びユーザ視点に立って考え、時には国際会議で世界の動きと調和を図りながら、自動運転の安全基準はどのようにあるべきか常に問い続けています。
「自動運転」の安全基準策定というチャレンジングな課題に邁進
近年、自動運転車が発表され、地方部では無人自動運転移動サービスが開始されるなど、いよいよ「実用化」の段階へと進む自動運転技術。私のミッションは、自動運転の安全基準を策定し、安全性を確保した技術開発や社会実装を着実に推進することです。また、自動車は国際流通商品のため、各国の安全基準をそろえる必要があります。国連の自動車基準調和世界フォーラムにおいて日本の先進的な技術を国際基準に反映し、積極的な発信により国際的な議論をリードしていくことも私の大きな役割です。

今現在、完全な自動運転は実用化されておらず、その制度づくりはまだ誰も成し遂げていないブルーオーシャンな分野です。前例のない世界で、安全基準をどのように作り上げていくのか。構想力が求められるチャレンジングな課題であるとともに、将来の自動運転社会の姿を思い浮かべるとワクワクするテーマでもあります。このような分野の制度設計に最前線で携われることは大きなやりがいです。 新しい技術も、安全でなければ社会に受け入れられません。一方で、日本の安全基準をガラパゴス化させてしまっては、せっかくの技術が世界から取り残されてしまいます。時には現場に足を運びユーザ視点に立って考え、時には国際会議で世界の動きと調和を図りながら、自動運転の安全基準はどのようにあるべきか常に問い続けています。


稲吉 裕俊
物流・自動車局
車両基準・国際課 係長(自動運転・サイバーセキュリティ担当)
平成31年入省(総合職技術系)
海事局、自動車局技術・環境政策課を経て現職。

日本をつなげるStory 「行きたいときに、行きたいところへ行ける社会」の実現を目指して
地域交通を「リ・デザイン」する
乗り合いバスやタクシー、地域鉄道などの地域交通は、人口減少による需要減や運転手等の不足により、厳しい状況に直面しています。所属部門のミッションは、「誰もが、行きたいときに、行きたいところへ行くことのできる社会」の実現。交通DX(※)・GX(※)、共創(地域の多様な関係者の連携・協働)などの取組を加速させ、利便性・生産性・持続可能性の高い地域交通ネットワークへの「リ・デザイン(再構築)」を図ります。そのための制度運用や施策の企画・立案が私の役割です。
地域交通のマスタープランである地域公共交通計画。そのアップデートを図るべく2023年12月には「地域公共交通計画の実質化に向けた検討会」を立ち上げ、月に一度、外部有識者8名と議論しています。検討会で扱う内容は、地域公共交通計画にかかわるKPI(重要業績評価指標)やデータの利活用など多岐に渡ります。各回の論点整理や関係自治体との調整等を行い、チームで議論を重ねて資料を作成するなど、すべきことは多くありますが、とりまとめに向けて、日々奮闘しています。
「当たり前のことが当たり前にできる世の中に」という入省時の思いを忘れずに、地域の実情に応じた「リ・デザイン」の実現に務めていきます。
※交通DX(デジタル・トランスフォーメーション)…自動運転やMaaSなどデジタル技術を実装。
※交通GX(グリーントランスフォーメーション)…車両電動化や再エネ地産地消など。
地域交通を「リ・デザイン」する
乗り合いバスやタクシー、地域鉄道などの地域交通は、人口減少による需要減や運転手等の不足により、厳しい状況に直面しています。所属部門のミッションは、「誰もが、行きたいときに、行きたいところへ行くことのできる社会」の実現。交通DX(※)・GX(※)、共創(地域の多様な関係者の連携・協働)などの取組を加速させ、利便性・生産性・持続可能性の高い地域交通ネットワークへの「リ・デザイン(再構築)」を図ります。そのための制度運用や施策の企画・立案が私の役割です。

地域交通のマスタープランである地域公共交通計画。そのアップデートを図るべく2023年12月には「地域公共交通計画の実質化に向けた検討会」を立ち上げ、月に一度、外部有識者8名と議論しています。検討会で扱う内容は、地域公共交通計画にかかわるKPI(重要業績評価指標)やデータの利活用など多岐に渡ります。各回の論点整理や関係自治体との調整等を行い、チームで議論を重ねて資料を作成するなど、すべきことは多くありますが、とりまとめに向けて、日々奮闘しています。
「当たり前のことが当たり前にできる世の中に」という入省時の思いを忘れずに、地域の実情に応じた「リ・デザイン」の実現に務めていきます。
※交通DX(デジタル・トランスフォーメーション)…自動運転やMaaSなどデジタル技術を実装。
※交通GX(グリーントランスフォーメーション)…車両電動化や再エネ地産地消など。


伊賀本 雅義
総合政策局
地域交通課地域交通計画調整官
平成30年入省(総合職事務系)
海事局、道路局、航空局を経て現職。

日本をつなげるStory
地方の大動脈を取り巻く
様々な課題に真正面から取り組む
「はやぶさ」への期待を肌で感じた私が整備新幹線にかかわるという縁
北海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線、九州新幹線の、いわゆる「整備新幹線」の仕事に取り組んでおり、新幹線の整備のための予算確保、政府・与党や地方公共団体との調整、今後の高速鉄道ネットワークの企画立案などが主な業務です。令和6年3月16日には北陸新幹線(金沢~敦賀)が開業。未着工の敦賀~新大阪については現在、環境影響評価を進め、詳細な駅位置やルートを決める作業を行っているところです。
平成23年3月6日、私は旅行先の仙台から東京まで東北新幹線に乗りました。その日は偶然、E5系と呼ばれる車両が「はやぶさ」としてデビューした翌日。ホームには子どもから大人まで多くの方が「はやぶさ」の写真を撮るため集まっており、こんなにも新幹線は人々に期待されているのかと驚いた記憶があります。学生だった当時は、まさか将来自分が北陸新幹線の延伸開業に立ち会うことになるとは思ってもおらず、大変感慨深いです。多くの関係者が長い年月をかけて携わる壮大なプロジェクトであることを理解できる今は、開業のタイミングで偶然担当できた幸運に感謝するとともに、改めて身を引き締めています。
多くの人の期待を背負った新幹線のような巨大インフラは、メリット・デメリットを含め常に多様な議論が起こります。行政官として、様々な利害を調整していくことが本務であり、これからも課題に真正面から取り組んでいきます。
「はやぶさ」への期待を肌で感じた私が整備新幹線にかかわるという縁
北海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線、九州新幹線の、いわゆる「整備新幹線」の仕事に取り組んでおり、新幹線の整備のための予算確保、政府・与党や地方公共団体との調整、今後の高速鉄道ネットワークの企画立案などが主な業務です。令和6年3月16日には北陸新幹線(金沢~敦賀)が開業。未着工の敦賀~新大阪については現在、環境影響評価を進め、詳細な駅位置やルートを決める作業を行っているところです。
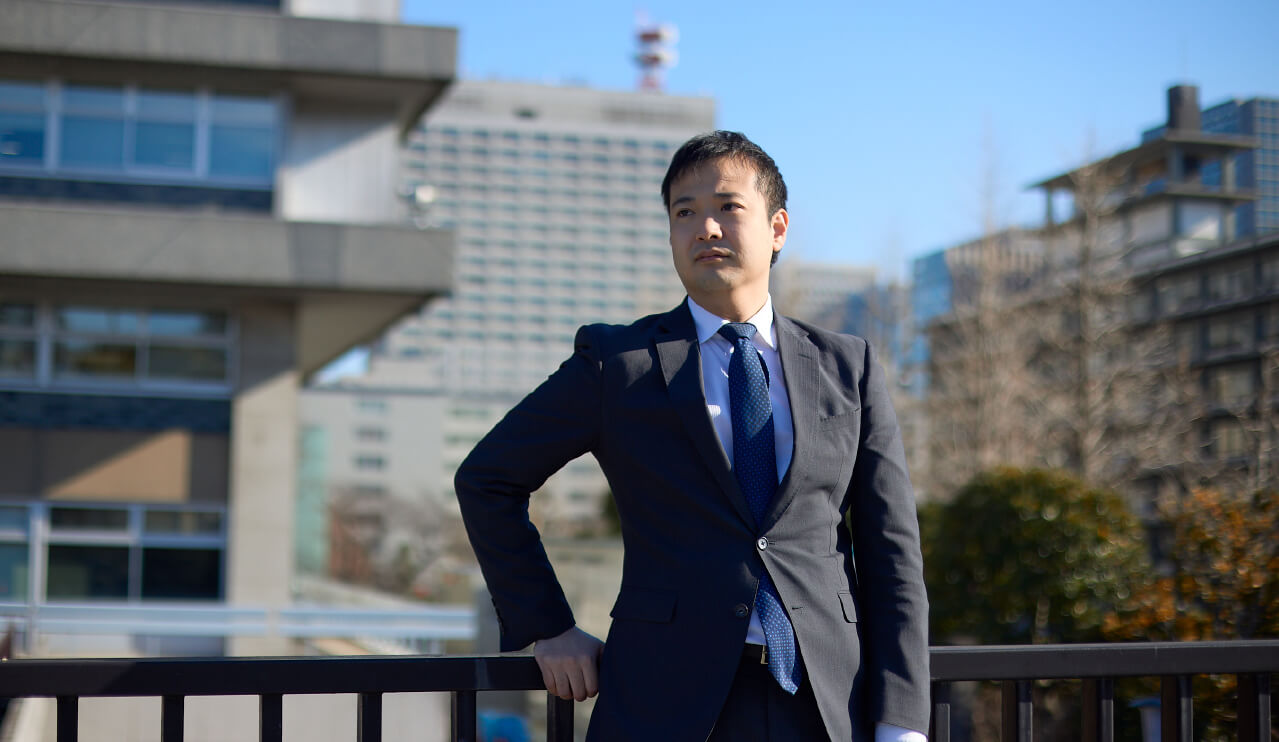
平成23年3月6日、私は旅行先の仙台から東京まで東北新幹線に乗りました。その日は偶然、E5系と呼ばれる車両が「はやぶさ」としてデビューした翌日。ホームには子どもから大人まで多くの方が「はやぶさ」の写真を撮るため集まっており、こんなにも新幹線は人々に期待されているのかと驚いた記憶があります。学生だった当時は、まさか将来自分が北陸新幹線の延伸開業に立ち会うことになるとは思ってもおらず、大変感慨深いです。多くの関係者が長い年月をかけて携わる壮大なプロジェクトであることを理解できる今は、開業のタイミングで偶然担当できた幸運に感謝するとともに、改めて身を引き締めています。
多くの人の期待を背負った新幹線のような巨大インフラは、メリット・デメリットを含め常に多様な議論が起こります。行政官として、様々な利害を調整していくことが本務であり、これからも課題に真正面から取り組んでいきます。
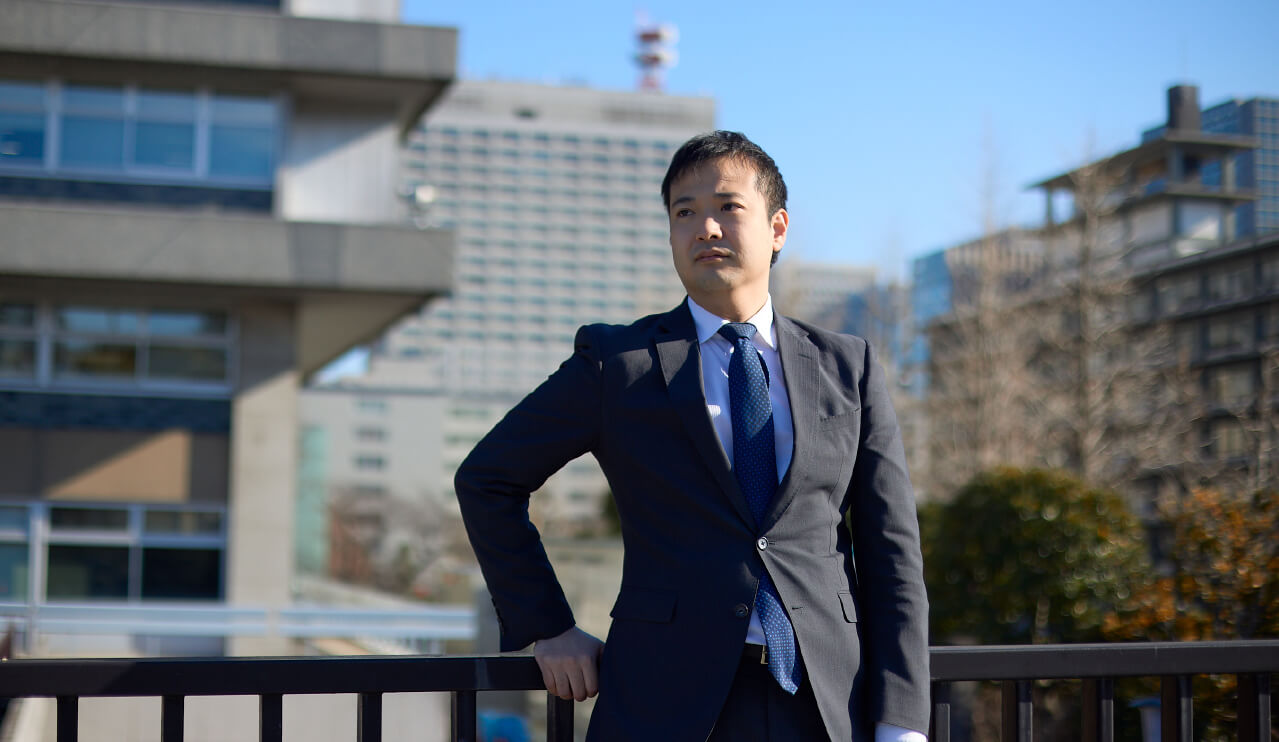

石川 雄基
鉄道局
幹線鉄道課課長補佐
平成25年入省(総合職事務系)
住宅局、総合政策局、航空局、近畿地方整備局、内閣官房等を経て現職。












