

<産業政策>建設業の生産性向上
Project Member

髙木 敬央

宇佐見 清

桝谷 有吾
建設業の生産性を向上させ、
社会経済の基盤を整備する
住宅、学校、オフィスビルや商業施設。そして、道路やトンネル、橋梁。形あるものを作り出すためには、建設工事が必ず必要になる。
そんな建設の現場で、今、人手不足や労働環境が課題となっている。そして、頻発・激甚化する災害や、インフラの老朽化に対応するため、建設業の進化が求められている。

国土交通省は、データとデジタル技術を活用して、建設業の生産性を向上させ、国民のニーズに合わせて建設業の仕事の進め方や業界・企業の文化や風土の変革に取り組んでいる。
建設の現場では、多様な人々が活躍している。優秀な担い手を育てていくためのキャリアアップシステムの構築から、女性の活躍の促進、外国人材の受入れまで。社会経済の基盤を支える人たちを、「支える」仕事がここにある。

Project Member 政策に携わる職員紹介
-

髙木 敬央
不動産・建設経済局
建設業課
入札制度企画指導室企画係長 -

宇佐見 清
不動産・建設経済局
国際市場課
建設産業海外ビジネス推進官 -

桝谷 有吾
大臣官房技術調査課
参事官(イノベーション)グループ
企画専門官
日本をつなげるStory
地方公共団体に入札契約制度の改善を促す
「ハンズオン支援事業」
個々の団体が抱える課題に寄り添う
持続可能な建設産業のための環境整備が課題となっている昨今、公共工事の入札契約の適正化が重要です。私が所属する室では、公共工事の発注者である地方公共団体を支援し、入札契約制度の改善を促しています。市区町村では、都道府県に比べて発注量は少ないものの、職員の体制上の制約等により事務負担が大きく、入札契約適正化の取組が遅れている傾向にあります。そこで、こうした団体に対する「ハンズオン支援事業」を令和5年度から開始しました。入札におけるダンピング対策や適正な工期設定といった重要項目に関する勉強会や、各団体が個別に抱える課題について情報提供を行っています。
発注量が少ないため、そもそも適正化の必要性を実感しにくい自治体や、人員不足などの事情から改善を進められない自治体など、抱える課題は様々です。国から最新の情報を通知として一斉に送る従来のやり方に加え、人員やノウハウなどのリソースを多く持つ都道府県と連携することで、さらに寄り添った支援を行っています。
地道に支援を行うことで入札契約の適正化が進めば、地方公共団体から工事を受注する建設業者が適正な利潤を確保できます。インフラ維持や災害からの復旧・復興の担い手である建設業界が今後も持続可能な産業であり続けるために、意義のある取組だと感じています。
個々の団体が抱える課題に寄り添う
持続可能な建設産業のための環境整備が課題となっている昨今、公共工事の入札契約の適正化が重要です。私が所属する室では、公共工事の発注者である地方公共団体を支援し、入札契約制度の改善を促しています。市区町村では、都道府県に比べて発注量は少ないものの、職員の体制上の制約等により事務負担が大きく、入札契約適正化の取組が遅れている傾向にあります。そこで、こうした団体に対する「ハンズオン支援事業」を令和5年度から開始しました。入札におけるダンピング対策や適正な工期設定といった重要項目に関する勉強会や、各団体が個別に抱える課題について情報提供を行っています。

発注量が少ないため、そもそも適正化の必要性を実感しにくい自治体や、人員不足などの事情から改善を進められない自治体など、抱える課題は様々です。国から最新の情報を通知として一斉に送る従来のやり方に加え、人員やノウハウなどのリソースを多く持つ都道府県と連携することで、さらに寄り添った支援を行っています。
地道に支援を行うことで入札契約の適正化が進めば、地方公共団体から工事を受注する建設業者が適正な利潤を確保できます。インフラ維持や災害からの復旧・復興の担い手である建設業界が今後も持続可能な産業であり続けるために、意義のある取組だと感じています。


髙木 敬央
不動産・建設経済局建設業課
入札制度企画指導室企画係長
平成24年入省(一般職事務系)
総合政策局、土地・建設産業局(現 不動産・建設経済局)、大臣官房、国土交通大学校等を経て現職。

日本をつなげるStory 「選ばれる建設業」であり続けるために
外国人材の国内での活躍と
日本企業の国外での活躍の、双方を支援
深刻な人手不足に直面する日本の建設業。国際市場課では外国人材の円滑な受け入れを支援する仕組みづくりや、外国人材が働きやすい環境整備を進めています。例えば、2023年度には「外国人材とつくる建設未来賞」を創設しました。日本で活躍する外国人技能者や外国人の受け入れを契機に新たな事業を展開する企業等を表彰することで、グッドプラクティスの普及を図っています。表彰式では、受賞者の日本で働くことへの想いや今後の目標等を聞く機会があり、これからも優秀な外国人材に「選ばれる建設業」であり続けるため、官民で連携していかなければと思いを新たにしました。
その一方、将来的に堅調な需要が期待できる海外建設市場への進出も後押ししています。例えば、日本企業やバングラデシュ政府から提案のあった官民連携プロジェクトについて、日本企業が優先交渉権を得られるよう相手国政府機関と調整・交渉しています。
私はこのように、外国人材の国内での活躍と、日本企業の国外での活躍の両方を支援する立場にあります。日本企業にとって外国人材は国内の担い手だけではなく、海外進出の際のキーパーソンともなり得るため、それぞれの取組を連携させることで相乗効果を生み出すことが私のミッションです。これらの業務を通じて、国内業務と国際業務は密接にかかわり合っていること、そして国土交通省はその結節点にあることを改めて実感しています。
外国人材の国内での活躍と
日本企業の国外での活躍の、双方を支援
深刻な人手不足に直面する日本の建設業。国際市場課では外国人材の円滑な受け入れを支援する仕組みづくりや、外国人材が働きやすい環境整備を進めています。例えば、2023年度には「外国人材とつくる建設未来賞」を創設しました。日本で活躍する外国人技能者や外国人の受け入れを契機に新たな事業を展開する企業等を表彰することで、グッドプラクティスの普及を図っています。表彰式では、受賞者の日本で働くことへの想いや今後の目標等を聞く機会があり、これからも優秀な外国人材に「選ばれる建設業」であり続けるため、官民で連携していかなければと思いを新たにしました。

その一方、将来的に堅調な需要が期待できる海外建設市場への進出も後押ししています。例えば、日本企業やバングラデシュ政府から提案のあった官民連携プロジェクトについて、日本企業が優先交渉権を得られるよう相手国政府機関と調整・交渉しています。
私はこのように、外国人材の国内での活躍と、日本企業の国外での活躍の両方を支援する立場にあります。日本企業にとって外国人材は国内の担い手だけではなく、海外進出の際のキーパーソンともなり得るため、それぞれの取組を連携させることで相乗効果を生み出すことが私のミッションです。これらの業務を通じて、国内業務と国際業務は密接にかかわり合っていること、そして国土交通省はその結節点にあることを改めて実感しています。

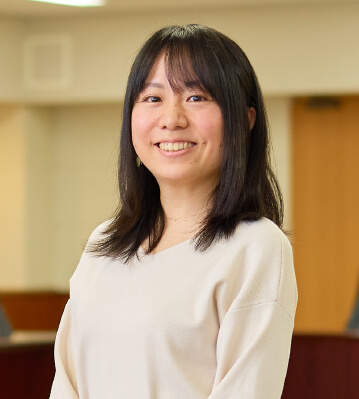
宇佐見 清
不動産・建設経済局
国際市場課建設産業海外ビジネス推進官
平成25年入省(総合職事務系)
自動車局、総合政策局、フランスHEC Paris経営大学院への留学、国土政策局、内閣府地方創生推進事務局等を経て現職。

日本をつなげるStory
インフラを支える建設業界に
最新デジタル技術でイノベーションを起こす
前例のない分野にチャレンジ
今後人口減少による働き手不足の深刻化が予想される一方で、災害対策や施設の老朽化対策などインフラの整備・維持管理へのニーズはさらに高まることが想定されます。私はi-Construction (※)、インフラDXといったデジタル技術を建設産業に取り入れ、生産性の向上や働き方改革を促進する取組を行っています。10年後、20年後の建設現場のあるべき姿を描き、その実現に向けたロードマップを検討したり、新しい技術を積極的に導入する旗振り役となったりするのが私のミッションです。具体的には、測量から維持管理に至るインフラ整備の全プロセスをデジタル化し、仕事の効率化を目指しています。そのため、3Dデータを活用するにあたってのルール作りや、官民が保有するインフラデータをオープン化しイノベーションを起こすためのプラットフォームを整備しています。
前例のないプロジェクトなので、新たなビジョンやアクションプランを作るのも大切な業務。インフラ分野のDXアクションプランの改定は、これまでのノウハウや道標がない中でのチャレンジングな仕事でしたが、その分、非常に思い入れの強いものになりました。現在も新たなアクションプランの作成に取り組んでいます。多くの人と議論を繰り返し、形にしていくプロセスに大きなやりがいを感じています。
※アイ・コンストラクション。ICT(情報通信技術)の活用などにより、建設現場の生産性向上を図る国土交通省の取組。令和6年4月には建設現場のオートメーション化を進めるi-Construction 2.0 を公表。
前例のない分野にチャレンジ
今後人口減少による働き手不足の深刻化が予想される一方で、災害対策や施設の老朽化対策などインフラの整備・維持管理へのニーズはさらに高まることが想定されます。私はi-Construction (※)、インフラDXといったデジタル技術を建設産業に取り入れ、生産性の向上や働き方改革を促進する取組を行っています。10年後、20年後の建設現場のあるべき姿を描き、その実現に向けたロードマップを検討したり、新しい技術を積極的に導入する旗振り役となったりするのが私のミッションです。具体的には、測量から維持管理に至るインフラ整備の全プロセスをデジタル化し、仕事の効率化を目指しています。そのため、3Dデータを活用するにあたってのルール作りや、官民が保有するインフラデータをオープン化しイノベーションを起こすためのプラットフォームを整備しています。

前例のないプロジェクトなので、新たなビジョンやアクションプランを作るのも大切な業務。インフラ分野のDXアクションプランの改定は、これまでのノウハウや道標がない中でのチャレンジングな仕事でしたが、その分、非常に思い入れの強いものになりました。現在も新たなアクションプランの作成に取り組んでいます。多くの人と議論を繰り返し、形にしていくプロセスに大きなやりがいを感じています。
※アイ・コンストラクション。ICT(情報通信技術)の活用などにより、建設現場の生産性向上を図る国土交通省の取組。令和6年4月には建設現場のオートメーション化を進めるi-Construction 2.0 を公表。


桝谷 有吾
大臣官房技術調査課
参事官(イノベーション)グループ
企画専門官
平成17年入省(総合職技術系)
中国地方整備局、水管理・国土保全局等を経て現職。












