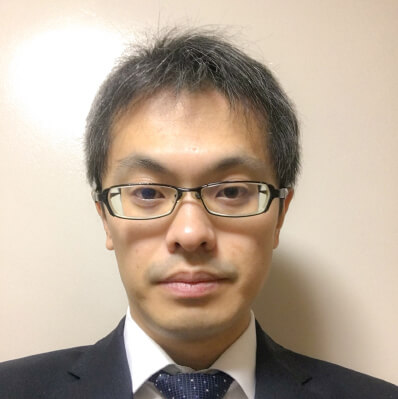<産業政策>物流の高度化
Project Member

内波 聖弥

淺野 洋武

伊藤 寛倫
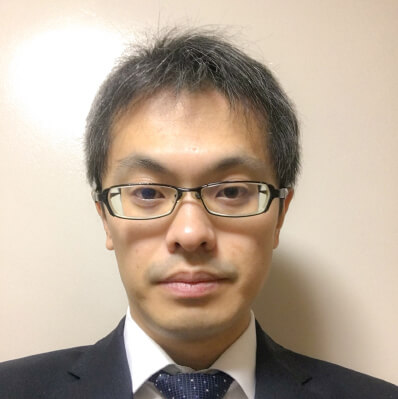
野村 文彦
モノの流れを効率化し、
経済を動かす
我々は、“物流は経済を回す血液である”と考えている。なぜなら、現代社会において、食品や日用品、部品、原材料、エネルギーなど、あらゆるものが輸送されているからだ。
日本の物流サービスは、トラック輸送を中心に、高い定時性や安全性を誇ってきた。しかしながら、人口減少による担い手不足、カーボンニュートラルへの対応、トラックドライバーの労働時間規制に伴い輸送力不足が懸念される「2024年問題」など、様々な課題が生じている。そこで、国土交通省では、荷主企業、物流事業者、一般消費者が協力して我が国の物流を支えるため、「商慣行の見直し」「物流の効率化」「荷主・消費者の行動変容」について、抜本的・総合的な対策を進めている。具体的には、「トラックGメン」による悪質荷主の監視強化、共同輸配送による積載率向上や、荷待ち・荷役時間の削減に資する即効性のある設備投資の促進、「物流DX」や「物流標準化」の推進によるサプライチェーン全体の最適化、再配達率「半減」に向けた対策など、経済や暮らしを支える物流の効率化・最適化に向けて取り組んでいる。

一方で、物流には土台となる道路ネットワークの整備が必要だ。全国の幹線道路網の強化や、三大都市圏環状道路、港湾・空港へのアクセス道路の整備。コンテナを積載する大型車両が、道路を安全・円滑に通行するためのルール策定も重要だ。1台でトラック2台分を輸送するダブル連結トラックの高速道路における実用化や、その先の自動運転の実現を見据えた新東名・新名神の6車線化も進行中である。
また港湾は、日本と海外を結ぶ玄関口として物流・人流の拠点であり、私たちの生命・財産を守るとともに、日本の経済成長や国際競争力の強化に向け必要不可欠なインフラである。
我々の国に輸出入される貨物の99.6%が港湾を経由している。コンテナ貨物については、阪神港及び京浜港を国際コンテナ戦略港湾として選定し、国際港湾のコンテナターミナルの整備や外航海運の国際競争力の強化にも奮闘している。

Project Member 政策に携わる職員紹介
日本をつなげるStory
私の考えた政策が
徐々に大きなムーブメントに
「2024年問題」に向け、
物流の効率化を実現するための法改正を
トラックドライバーの時間外労働規制が適用されることにより、いわゆる物流の「2024年問題」が懸念されています。物流の効率化のためには物流事業者側の取組に加えて、発注や受取を行う「荷主」の協力が必要不可欠です。そこで、荷主を所管する経済産業省や農林水産省と共同で有識者検討会を立ち上げ、サプライチェーン全体で物流の効率化を実現するための法律改正の方向性を打ち出しました。
検討会でのとりまとめがメディアで注目され、岸田総理も出席する関係閣僚会議の立ち上げにつながりました。それにより厚生労働省や警察庁、消費者庁、公正取引委員会など、さらに多くの関係省庁が加わり、政府全体で「政策パッケージ」を取りまとめることに。現在はこの政策パッケージに基づき、数多くの政策が実現・進行中です。自分の考えた政策が実現されること、それが徐々に大きなムーブメントになり、多くの関係者と一緒にその政策を実行していくことにとてもやりがいを感じました。チャレンジングな状況も数多くありましたが、真摯な努力とチームワークで乗り越えていきました。
あるトラック事業者と定期的に情報交換しています。社長から「いろいろ動いてくれているのがわかる。私たちの話をしっかり聞いて、物流のことを考えてくれてありがとう」と言われた時は、とても感動しました。熱意を持って動けば相手に伝わることを実感したエピソードです。
「2024年問題」に向け、
物流の効率化を実現するための法改正を
トラックドライバーの時間外労働規制が適用されることにより、いわゆる物流の「2024年問題」が懸念されています。物流の効率化のためには物流事業者側の取組に加えて、発注や受取を行う「荷主」の協力が必要不可欠です。そこで、荷主を所管する経済産業省や農林水産省と共同で有識者検討会を立ち上げ、サプライチェーン全体で物流の効率化を実現するための法律改正の方向性を打ち出しました。

検討会でのとりまとめがメディアで注目され、岸田総理も出席する関係閣僚会議の立ち上げにつながりました。それにより厚生労働省や警察庁、消費者庁、公正取引委員会など、さらに多くの関係省庁が加わり、政府全体で「政策パッケージ」を取りまとめることに。現在はこの政策パッケージに基づき、数多くの政策が実現・進行中です。自分の考えた政策が実現されること、それが徐々に大きなムーブメントになり、多くの関係者と一緒にその政策を実行していくことにとてもやりがいを感じました。チャレンジングな状況も数多くありましたが、真摯な努力とチームワークで乗り越えていきました。
あるトラック事業者と定期的に情報交換しています。社長から「いろいろ動いてくれているのがわかる。私たちの話をしっかり聞いて、物流のことを考えてくれてありがとう」と言われた時は、とても感動しました。熱意を持って動けば相手に伝わることを実感したエピソードです。


内波 聖弥
物流・自動車局
物流政策課長補佐
平成25年入省(総合職事務系)
港湾局、鉄道局、大臣官房、米国UCSDへの留学等を経て現職。

日本をつなげるStory
外航海運を支える
地道な作業の積み重ね
日本商船隊の国際競争力の確保と日本籍船の増加を図る
島国の日本において、輸出入貨物の99%以上の輸送を担う外航海運は、経済・国民生活を支える極めて重要な存在です。この輸送の軸となるのが日本の海運企業により運航される外航船舶群である「日本商船隊」。中でも日本籍船は経済安全保障等の観点から一定規模確保することが求められます。一方で、船籍や海運会社の所在国によって課される税や船舶運航上の規制等には違いがあります。「日本商船隊の国際競争力の確保」と「日本籍船の増加」を図るため、税制や諸制度の改善という観点からアプローチすることが私の所属チームの仕事です。その土台となるデータの収集・分析が私の役割。日本と他国との規制や税制の比較分析はもちろんのこと、船舶を供給する造船業や舶用工業、船舶投資を後押しする金融業、顧客となる荷主、航行に欠かせない海上保険など、様々な分野に目を光らす必要があります。
情報収集や分析は地道な作業の繰り返しですが、長い時間をかけて取り組んできた仕事が制度として実を結んだ時の達成感は格別です。しかし、国の政策は世に出た時がゴールではなく、むしろそこからが始まりです。政策が社会に貢献したか評価されるのは数年後、数十年後かもしれません。だからこそ絶えず政策(制度)を見直していく必要があると考えます。日々の積み重ねがゆくゆくは大きな成果につながることが、この仕事の醍醐味です。
日本商船隊の国際競争力の確保と日本籍船の増加を図る
島国の日本において、輸出入貨物の99%以上の輸送を担う外航海運は、経済・国民生活を支える極めて重要な存在です。この輸送の軸となるのが日本の海運企業により運航される外航船舶群である「日本商船隊」。中でも日本籍船は経済安全保障等の観点から一定規模確保することが求められます。一方で、船籍や海運会社の所在国によって課される税や船舶運航上の規制等には違いがあります。「日本商船隊の国際競争力の確保」と「日本籍船の増加」を図るため、税制や諸制度の改善という観点からアプローチすることが私の所属チームの仕事です。その土台となるデータの収集・分析が私の役割。日本と他国との規制や税制の比較分析はもちろんのこと、船舶を供給する造船業や舶用工業、船舶投資を後押しする金融業、顧客となる荷主、航行に欠かせない海上保険など、様々な分野に目を光らす必要があります。

情報収集や分析は地道な作業の繰り返しですが、長い時間をかけて取り組んできた仕事が制度として実を結んだ時の達成感は格別です。しかし、国の政策は世に出た時がゴールではなく、むしろそこからが始まりです。政策が社会に貢献したか評価されるのは数年後、数十年後かもしれません。だからこそ絶えず政策(制度)を見直していく必要があると考えます。日々の積み重ねがゆくゆくは大きな成果につながることが、この仕事の醍醐味です。


淺野 洋武
海事局
外航課調査係長
平成30年入省(一般職)
海事局内航課、総合政策局物流政策課を経て現職。

日本をつなげるStory
自治体と周辺産業をつなぎ、
脱炭素化に向け連携して取り組む
70を超える港湾で協議会が開催
現在、港湾における脱炭素化の施策「カーボンニュートラルポートの形成」を担当しています。この施策には大きく2つの視点があります。
①港湾・臨海部には多くの産業があり、これらが脱炭素化していくためには、化石燃料を水素・アンモニア等の低炭素なものに置き換えるなどの取組が必要。それをインフラ面で支えることを目指す。
②港湾物流の脱炭素化(例:低炭素型の荷役機械の導入)を通じて荷主企業のニーズに応え、港湾の競争力の強化を目指す。
ただ、これらの取組には課題もあります。例えばもともとディーゼルで駆動している荷役機械を脱炭素化するためには、ハイブリッド化や電動化、バイオ燃料の導入などの手法が考えられますが、いずれもコストがかかるのです。このような理想と現実のギャップを少しでも埋めるため、港湾管理者(自治体)と民間企業等が連携。脱炭素化を目指して取り組むプラットフォームとして、計画を作成する協議会制度を設けました。予算、税制等による支援も行っています。今では70以上の港湾において協議会が開催されています。これだけ広がりを見せているのは、各関係機関が脱炭素化に取り組む必要性を認識しているからでしょう。具体的な成果が出てくるのは数年後ですが、それが「カーボンニュートラルポートの形成」を土台としたものであれば、大きな達成感を得られると期待しています。
70を超える港湾で協議会が開催
現在、港湾における脱炭素化の施策「カーボンニュートラルポートの形成」を担当しています。この施策には大きく2つの視点があります。

①港湾・臨海部には多くの産業があり、これらが脱炭素化していくためには、化石燃料を水素・アンモニア等の低炭素なものに置き換えるなどの取組が必要。それをインフラ面で支えることを目指す。
②港湾物流の脱炭素化(例:低炭素型の荷役機械の導入)を通じて荷主企業のニーズに応え、港湾の競争力の強化を目指す。
ただ、これらの取組には課題もあります。例えばもともとディーゼルで駆動している荷役機械を脱炭素化するためには、ハイブリッド化や電動化、バイオ燃料の導入などの手法が考えられますが、いずれもコストがかかるのです。このような理想と現実のギャップを少しでも埋めるため、港湾管理者(自治体)と民間企業等が連携。脱炭素化を目指して取り組むプラットフォームとして、計画を作成する協議会制度を設けました。予算、税制等による支援も行っています。今では70以上の港湾において協議会が開催されています。これだけ広がりを見せているのは、各関係機関が脱炭素化に取り組む必要性を認識しているからでしょう。具体的な成果が出てくるのは数年後ですが、それが「カーボンニュートラルポートの形成」を土台としたものであれば、大きな達成感を得られると期待しています。


伊藤 寛倫
港湾局産業港湾課
CNP推進室長代理
平成16年入省(総合職技術系)
東北地方整備局、鉄道局、住宅局、航空局、港湾局、内閣府(防災)、在上海総領事館、内閣官房(オリパラ事務局)を経て現職。

日本をつなげるStory 未来の広域道路ネットワークシステムの実現に向け、日々精進
誠実さを忘れず、
地域とともに取り組んでいく
日本の広域道路ネットワーク計画は、四半世紀以上見直しがなされていませんでした。そこで道路局では令和5年7月に策定された新たな国土形成計画を踏まえて、同10月に「2050年、世界一、賢く・安全で・持続可能な基盤ネットワークシステム(通称:WISENET)」を構築する方針を掲げ、今後取り組む具体的な方向性をまとめた「WISENET2050・政策集」を作成。現在、実現に向けて様々な調査検討を行っているところです。
新たな国土形成計画では、「国土をめぐる社会経済状況は大きく変化しており、時代の転換期ともいえる重大な岐路に立っている」ことが示されています。このような状況の中、次世代を担う「WISENET2050・政策集」の作成に携われたことは光栄であり、大きなやりがいを感じました。また、アメリカやスイス、カナダにおける現地調査で海外の先進事例を学び、多角的な視点から将来の道路網のあるべき姿を分析する重要性を再認識しました。
さらに多くの関係者や有識者と議論する中で、高度医療へのアクセス向上や大規模災害時の対応など、交通量の多寡だけでは測れない、地域生活や国土を守るために必要な道路網が存在することを学びました。
今後も地域の皆さんとともに、よりよい政策づくりに誠実に取り組んでいきたいと考えています。
誠実さを忘れず、
地域とともに取り組んでいく
日本の広域道路ネットワーク計画は、四半世紀以上見直しがなされていませんでした。そこで道路局では令和5年7月に策定された新たな国土形成計画を踏まえて、同10月に「2050年、世界一、賢く・安全で・持続可能な基盤ネットワークシステム(通称:WISENET)」を構築する方針を掲げ、今後取り組む具体的な方向性をまとめた「WISENET2050・政策集」を作成。現在、実現に向けて様々な調査検討を行っているところです。
新たな国土形成計画では、「国土をめぐる社会経済状況は大きく変化しており、時代の転換期ともいえる重大な岐路に立っている」ことが示されています。このような状況の中、次世代を担う「WISENET2050・政策集」の作成に携われたことは光栄であり、大きなやりがいを感じました。また、アメリカやスイス、カナダにおける現地調査で海外の先進事例を学び、多角的な視点から将来の道路網のあるべき姿を分析する重要性を再認識しました。

さらに多くの関係者や有識者と議論する中で、高度医療へのアクセス向上や大規模災害時の対応など、交通量の多寡だけでは測れない、地域生活や国土を守るために必要な道路網が存在することを学びました。
今後も地域の皆さんとともに、よりよい政策づくりに誠実に取り組んでいきたいと考えています。

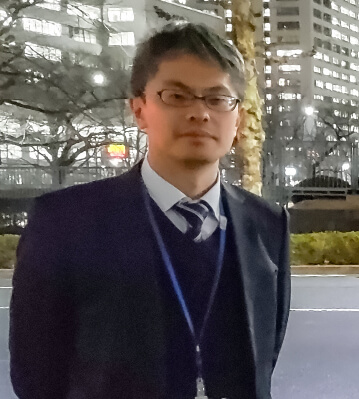
野村 文彦
道路局企画課
道路経済調査室課長補佐
平成22年入省(総合職技術系)
九州地方整備局、水管理・国土保全局を経て現職。