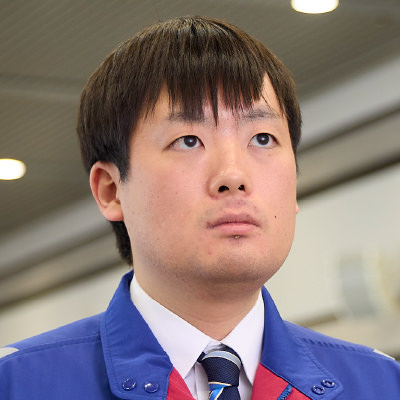<命を守る>防災
Project Member

柳田 穣

三浦 翔

田中 里佳
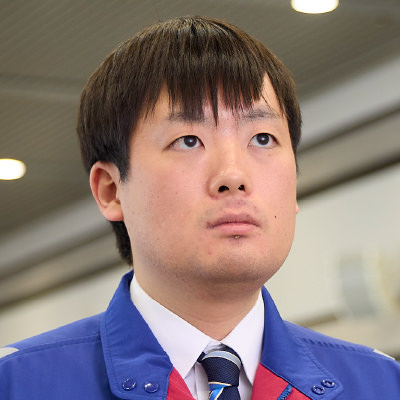
吉開 亮一
災害で苦しむ人を
少しでも減らしていくために、
国土交通省ができること
自然災害への対応は、我々が直面している最大の課題であると言っても過言ではない。国土交通省は、地震、風水害、火山活動など、あらゆる危機に対応し、事前防災・応急対応・災害復旧の3つの柱で、人々の命と暮らしを守ってきた。
一方で、気候変動により、大雨の頻度・強度の増加や平均海面水位の上昇などが予想されている。今後も、風水害をはじめとした災害の激甚化・頻発化は不可避であり、これまでのような河川整備だけでは、安全を守りきることはできない。

このため、従来の河川管理者等が主体となって、河川区域で行う対策をこれまで以上に充実・強化し、さらに集水域や氾濫域を加えた流域全体で、あらゆる関係者の協働により治水対策に取り組む「流域治水」を推進することが重要だ。
具体的には、集水域において、発電事業者等からの協力を得て行う利水ダムの活用、水田やため池での貯留、民間企業による貯留施設の整備促進などの対策を充実させている。さらに、氾濫域においても、まちづくりと連携した災害リスクの低い地域への居住誘導。そして、被害を受けても事業が継続できるBCPの策定。加えて、住民の確実な避難のための、高齢者福祉施設におけるスロープ等の改善や高台などの避難場所の確保など。このように、関係機関と連携し、対策案を議論することで、被害の回避・軽減を図っている。

Project Member 政策に携わる職員紹介
日本をつなげるStory より災害に強く魅力的な都市の実現を目指して
都市により異なる災害リスクを踏まえたまちづくりのために
都市計画課では、まちづくりの計画制度の企画立案や運用等を行っています。私は人口減少や少子高齢化、市街地の拡散、災害の激甚化・頻発化といった都市的な課題を踏まえ、災害に強く、住民や事業者にとって魅力的で持続的なまちづくりを支える「立地適正化計画・防災指針」の推進を担当しています。制度の創設から約10年が経ち、立地適正化計画は527都市、防災指針を作成した市町村は205都市(※)になりました。技術的助言や法律・財政支援制度等の改良を通じて、市町村をはじめとする地方公共団体が災害リスクを的確に把握・認知し、その軽減を図っていくことができるようにするのが、私の役割です。防災指針に基づく取組の実践により浸水被害の軽減が図られたケースもあり、やりがいを感じています。
一方で、多くの地方公共団体では都市計画を担う技術系職員の不足という課題を抱えています。また、都市計画は、防災の視点のみならず都市基盤の整備や産業、環境、賑わいの創出など多面的な視点が地方公共団体には求められます。この認識を前提として防災まちづくりに取り組む重要性を学びました。例えば、災害リスクが相対的に低いエリアへの居住誘導を図っていく際にも、多面的な視点に基づき地域の実情に精通する地方公共団体が適切に取り組むことができるよう、国が積極的に支援する必要性もあるのではないかと考えています。
2024年に入ってからも大きな災害が発生し、多くの尊い命や住居、都市機能が失われてしまいました。地方公共団体等と連携し、災害が発生しても暮らしや経済活動が守られるよう、業務に邁進する責任を強く感じています。
※いずれも令和5年7月31日時点
都市により異なる災害リスクを踏まえたまちづくりのために
都市計画課では、まちづくりの計画制度の企画立案や運用等を行っています。私は人口減少や少子高齢化、市街地の拡散、災害の激甚化・頻発化といった都市的な課題を踏まえ、災害に強く、住民や事業者にとって魅力的で持続的なまちづくりを支える「立地適正化計画・防災指針」の推進を担当しています。制度の創設から約10年が経ち、立地適正化計画は527都市、防災指針を作成した市町村は205都市(※)になりました。技術的助言や法律・財政支援制度等の改良を通じて、市町村をはじめとする地方公共団体が災害リスクを的確に把握・認知し、その軽減を図っていくことができるようにするのが、私の役割です。防災指針に基づく取組の実践により浸水被害の軽減が図られたケースもあり、やりがいを感じています。

一方で、多くの地方公共団体では都市計画を担う技術系職員の不足という課題を抱えています。また、都市計画は、防災の視点のみならず都市基盤の整備や産業、環境、賑わいの創出など多面的な視点が地方公共団体には求められます。この認識を前提として防災まちづくりに取り組む重要性を学びました。例えば、災害リスクが相対的に低いエリアへの居住誘導を図っていく際にも、多面的な視点に基づき地域の実情に精通する地方公共団体が適切に取り組むことができるよう、国が積極的に支援する必要性もあるのではないかと考えています。
2024年に入ってからも大きな災害が発生し、多くの尊い命や住居、都市機能が失われてしまいました。地方公共団体等と連携し、災害が発生しても暮らしや経済活動が守られるよう、業務に邁進する責任を強く感じています。
※いずれも令和5年7月31日時点


柳田 穣
都市局都市計画課
企画専門官
平成22年入省(総合職技術系)
港湾局、九州地方整備局、国土政策局、弘前市役所、等を経て現職。

日本をつなげるStory 災害の被害を少しでも小さなものに
被災者をゼロにするための適切な判断と常日頃からの備え
私が所属する水管理・国土保全局防災課災害対策室では、台風などの風水害や地震、火山噴火といったあらゆる自然災害が発生、または発生する恐れがある場合の国土交通省の災害対応を総括しています。災害が発生した直後には、私たち災害対策室職員は、国土交通省防災センターへ迅速に参集し、様々な対応を行います。各地のリアルタイムの被災状況等を官邸危機管理センターへ随時発信しており、各省庁から集められた情報は、総理大臣や官房長官から国民の皆さんへ発信されることとなります。
初動対応中は特に、様々な情報が交錯するため、正しい情報かどうかを十分精査したうえで発信する必要があり、迅速かつ的確な判断が常に求められます。
また、災害が大規模な場合には、速やかに国土交通省災害対策本部会議を開催し、被災地への支援や復旧方針などを検討します。この会議の運営にあたり、事務局として省内の幅広い関係者との調整を行います。
今年(令和6年)の元日16時10分頃、「令和6年能登半島地震」が発生した際には、テレビに映った緊急地震速報を見て、すぐに実家から防災センターに参集しました。万一、参集できないようなことがあると、国土交通省全体の初動対応に遅れが生じかねないため、災害対策室に在籍している限りは、日頃から備えを怠らず、常に防災行政の一端を担っていることを意識することが大事だと考えております。今後も全力で防災・減災に取り組んでいくことで、自然災害での被災者ゼロを目指します。
被災者をゼロにするための適切な判断と常日頃からの備え
私が所属する水管理・国土保全局防災課災害対策室では、台風などの風水害や地震、火山噴火といったあらゆる自然災害が発生、または発生する恐れがある場合の国土交通省の災害対応を総括しています。災害が発生した直後には、私たち災害対策室職員は、国土交通省防災センターへ迅速に参集し、様々な対応を行います。各地のリアルタイムの被災状況等を官邸危機管理センターへ随時発信しており、各省庁から集められた情報は、総理大臣や官房長官から国民の皆さんへ発信されることとなります。
初動対応中は特に、様々な情報が交錯するため、正しい情報かどうかを十分精査したうえで発信する必要があり、迅速かつ的確な判断が常に求められます。

また、災害が大規模な場合には、速やかに国土交通省災害対策本部会議を開催し、被災地への支援や復旧方針などを検討します。この会議の運営にあたり、事務局として省内の幅広い関係者との調整を行います。
今年(令和6年)の元日16時10分頃、「令和6年能登半島地震」が発生した際には、テレビに映った緊急地震速報を見て、すぐに実家から防災センターに参集しました。万一、参集できないようなことがあると、国土交通省全体の初動対応に遅れが生じかねないため、災害対策室に在籍している限りは、日頃から備えを怠らず、常に防災行政の一端を担っていることを意識することが大事だと考えております。今後も全力で防災・減災に取り組んでいくことで、自然災害での被災者ゼロを目指します。


三浦 翔
水管理・国土保全局防災課
災害対策室管理係
平成30年入省(一般職事務系)
水管理・国土保全局総務課、防災課、砂防部保全課等を経て現職。

日本をつなげるStory
既存ダムの運用高度化による
治水・利水の機能強化のプロジェクトに邁進
激甚化する災害への対応と
限りある水資源の有効活用を見据えて
日本には約1500のダムがあり、洪水調節を行う「治水」、水道・工業用水・農業用水等の供給や水力発電のための「利水」など、多様な役割を担っています。河川環境課では、近年激甚化する洪水等の災害への対応や、限られた水資源の有効活用を目的として、ダムの機能を最大限発揮させる事前放流(※1)やハイブリッドダム(※2)のプロジェクトに取り組んでいます。治水、利水、環境の観点から方策を考え、現場の実務につなげるのが私の役割です。
事前放流はダムに貯めた貴重な水を、利水者の協力により放水し洪水に備えます。万一、雨が降らずに水位が回復しなかった時のリスクも考えなければなりません。逆に、増電のためのダムの運用高度化により、洪水調節にリスクが生じるような事態は避けなければなりません。利害が相反しかねない取組を進める中では、実態を踏まえて課題を読み解き、関係者それぞれの思いに寄り添った対話を行うこと、また、大きな目標に対してもできることから小さく始め、まずは動くことが重要だと改めて学びました。
「令和6年能登半島地震」の際は、上下水道の復旧のマネジメント支援等のため珠洲市に入りました。現場を歩き、当たり前の日常がいかに尊いかを痛感しました。日々の暮らしを間接的、直接的に支えるのが国土交通省の仕事です。力及ばず悔しい思いをすることもありますが、この仕事に携われることを誇りに思います。
※1…大雨が降る前にダムの水を放流し、より多くの水を貯められるよう備えること
※2…治水機能の強化、水力発電の増強のため、気象予測を活用してダムをさらに活用する取組のこと
激甚化する災害への対応と
限りある水資源の有効活用を見据えて
日本には約1500のダムがあり、洪水調節を行う「治水」、水道・工業用水・農業用水等の供給や水力発電のための「利水」など、多様な役割を担っています。河川環境課では、近年激甚化する洪水等の災害への対応や、限られた水資源の有効活用を目的として、ダムの機能を最大限発揮させる事前放流(※1)やハイブリッドダム(※2)のプロジェクトに取り組んでいます。治水、利水、環境の観点から方策を考え、現場の実務につなげるのが私の役割です。
事前放流はダムに貯めた貴重な水を、利水者の協力により放水し洪水に備えます。万一、雨が降らずに水位が回復しなかった時のリスクも考えなければなりません。逆に、増電のためのダムの運用高度化により、洪水調節にリスクが生じるような事態は避けなければなりません。利害が相反しかねない取組を進める中では、実態を踏まえて課題を読み解き、関係者それぞれの思いに寄り添った対話を行うこと、また、大きな目標に対してもできることから小さく始め、まずは動くことが重要だと改めて学びました。

「令和6年能登半島地震」の際は、上下水道の復旧のマネジメント支援等のため珠洲市に入りました。現場を歩き、当たり前の日常がいかに尊いかを痛感しました。日々の暮らしを間接的、直接的に支えるのが国土交通省の仕事です。力及ばず悔しい思いをすることもありますが、この仕事に携われることを誇りに思います。
※1…大雨が降る前にダムの水を放流し、より多くの水を貯められるよう備えること
※2…治水機能の強化、水力発電の増強のため、気象予測を活用してダムをさらに活用する取組のこと


田中 里佳
水管理・国土保全局河川環境課
流水管理室企画専門官
平成16年入省(総合職技術系)
水管理・国土保全局、大臣官房、中部地方整備局を経て現職。

日本をつなげるStory 被災した「のと鉄道」の復旧に向けた支援
全員一丸となって早期復旧に尽力
元日に発生した「令和6年能登半島地震」は、鉄道施設にも大きな被害を及ぼしました。このうち、七尾市と穴水町を結ぶ「のと鉄道」は大きな被害を受け、斜面崩壊に伴う線路敷への土砂流入、広範にわたるレール湾曲、ホーム等の駅施設損傷など、多数の被害が発生しました。国土交通省では、発災後速やかに緊急災害対策支援隊(TEC-FORCE)を派遣し、(独)鉄道・運輸機構の鉄道災害調査隊(RAIL-FORCE)と連携して、被害状況調査や復旧策に関する技術的助言を実施しました。
復旧工事は、施設を保有するJR西日本と「のと鉄道」が密接に連携し実施することとなりましたが、復旧が円滑かつ迅速に進むよう、TEC-FORCEとして3名が「のと鉄道」に駐在。私もその一員として1月18日から2月3日にかけて関係者との連絡調整等の支援活動を行いました。
連絡調整の一例として、道路復旧工事との事業間連携が挙げられます。土砂流入箇所において、現場の状況、課題、ニーズを詳細に把握。その情報を鉄道局と共有することで、復旧作業において課題となっていた工事用資材の確保や土砂の搬出先について、道路局や北陸地方整備局との連携・調整が進みました。その結果、国道249号等の道路復旧工事で使用予定の砕石を、土砂流入箇所に進入するための仮設進入路の盛土材として一時利用できることに(※)。さらに、撤去した土砂は道路復旧工事で確保していた残土処理地に搬出できることになりました。
関係者全員が一丸となって早期復旧に尽力した結果、「のと鉄道」は2月15日に一部区間で、4月6日には全線で運転を再開。私はすでに現地を離れていましたが、報告を聞いて心から嬉しく思いました。桜咲く頃、必ず復旧した「のと鉄道」に乗りに行こうと考えています。
※使用した砕石は使用後に返却し、道路復旧工事に影響しないよう配慮。
全員一丸となって早期復旧に尽力
元日に発生した「令和6年能登半島地震」は、鉄道施設にも大きな被害を及ぼしました。このうち、七尾市と穴水町を結ぶ「のと鉄道」は大きな被害を受け、斜面崩壊に伴う線路敷への土砂流入、広範にわたるレール湾曲、ホーム等の駅施設損傷など、多数の被害が発生しました。国土交通省では、発災後速やかに緊急災害対策支援隊(TEC-FORCE)を派遣し、(独)鉄道・運輸機構の鉄道災害調査隊(RAIL-FORCE)と連携して、被害状況調査や復旧策に関する技術的助言を実施しました。
復旧工事は、施設を保有するJR西日本と「のと鉄道」が密接に連携し実施することとなりましたが、復旧が円滑かつ迅速に進むよう、TEC-FORCEとして3名が「のと鉄道」に駐在。私もその一員として1月18日から2月3日にかけて関係者との連絡調整等の支援活動を行いました。

連絡調整の一例として、道路復旧工事との事業間連携が挙げられます。土砂流入箇所において、現場の状況、課題、ニーズを詳細に把握。その情報を鉄道局と共有することで、復旧作業において課題となっていた工事用資材の確保や土砂の搬出先について、道路局や北陸地方整備局との連携・調整が進みました。その結果、国道249号等の道路復旧工事で使用予定の砕石を、土砂流入箇所に進入するための仮設進入路の盛土材として一時利用できることに(※)。さらに、撤去した土砂は道路復旧工事で確保していた残土処理地に搬出できることになりました。
関係者全員が一丸となって早期復旧に尽力した結果、「のと鉄道」は2月15日に一部区間で、4月6日には全線で運転を再開。私はすでに現地を離れていましたが、報告を聞いて心から嬉しく思いました。桜咲く頃、必ず復旧した「のと鉄道」に乗りに行こうと考えています。
※使用した砕石は使用後に返却し、道路復旧工事に影響しないよう配慮。


吉開 亮一
鉄道局参事官(新幹線建設)室
課長補佐
平成30年入省(総合職技術系)
鉄道局、大臣官房、(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構出向を経て現職。