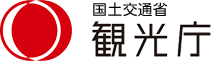持続可能な観光地域づくりに向けた取組
最終更新日:2025年6月17日
我が国の「住んでよし、訪れてよし」の観光地域づくりを実現するためには、地方公共団体や観光地域づくり法人(DMO)が中心となって、観光客と地域住民の双方に配慮し、多面的かつ客観的なデータ計測と中長期的な計画に基づく総合的な観光地マネジメントを行うことが重要です。観光庁ではこうした背景を踏まえて、様々な取組を行っています。
日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)
「住んでよし、訪れてよし」の観光地域づくりを実現するためには、観光客と地域住民双方に配慮し、多面的かつ客観的なデータ計測と中長期的な計画に基づく総合的な観光地マネジメントを行うことが重要です。
観光庁では、各地方自治体や観光地域づくり法人(DMO)が持続可能な観光地マネジメントを行うことができるよう、国際基準に準拠した「日本版持続可能な観光ガイドライン(Japan Sustainable Tourism Standard for Destinations,JSTS-D)」を開発しました。
各地域において、「日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)」が最大限活用されることにより、効果的で持続可能な観光地マネジメントへの取組がさらに加速することを期待しています。
持続可能な観光推進モデル事業
「日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)」を活用し、各地方公共団体や観光地域づくり法人(DMO)等が持続可能な観光地マネジメントを行えるように、モデル事業を実施します。
持続可能な観光の促進に向けた受入環境整備事業
観光スポット等において、自然・文化・生業等の地域の資源の保全・活用を通じて、地域・旅行者の双方が観光振興のメリットを享受できる好循環の地域づくりのための受入環境整備を図ります。
訪日外国人旅行者向けマナー啓発動画
文化や習慣の違いにより、日本人にとって「当たり前」のマナーでも、外国人旅行者にとってはそうとは限りません。こうした外国人旅行者に日本のマナー・文化・風習への理解を促し、より気持ちよく日本での旅行を楽しんでいただくために、地域で自由に放映できるマナー啓発動画を作成・公開しております。「データ利用届出書」を提出いただければ動画も使用可能ですので、是非ご活用ください。
持続可能な観光への意識調査
各地方公共団体等における持続可能な観光地域づくりの取組状況や持続可能な観光への意識を把握する事を目的として、地方公共団体等に向けて取組調査を行いました。
持続可能な観光の実現に向けた先進事例集
持続可能な観光に取り組むにあたっての参考として、先進事例を紹介いたします。
地域コミュニティとの共生等、各地の持続可能な観光に向けた取組をご参照ください。