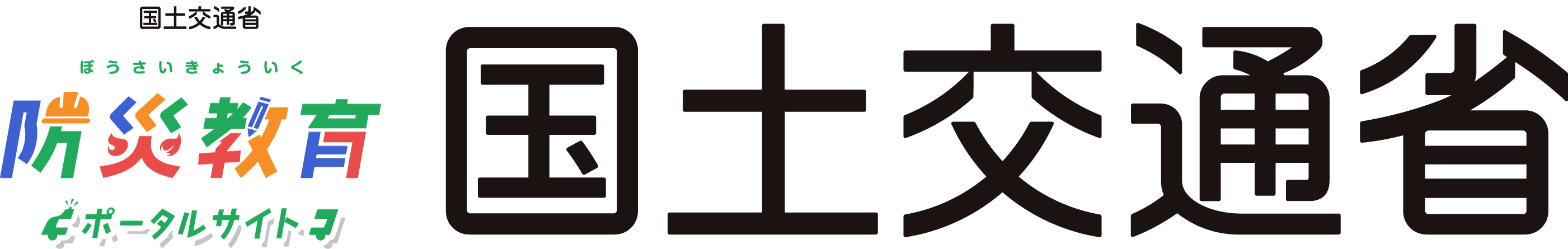ぼうさいきょういく
防災教育ポータルサイト
防災教育コラム 第2回
防災教育を重視した
SDGsの取組
町田第五小学校 校長 五十嵐俊子
Column
近年、気候変動等により、これまで経験したことのないような激甚災害が地球規模で発生している。国連サミットで採択された2030年までの目標、持続可能でよりよい世界を目指す17の開発目標「SDGs」の中でも、「11 持続可能な都市」と「13 気象変動」は、重要な課題である。学習指導要領に新たに設けられた前文の中にも「持続可能な社会の創り手」の育成が掲げられている。子供たちには教育を通して、今後の予測不能な時代を生き抜くために 必要な力を育成しなければならない。
本校は、「新時代を創造するための学びの改革」をビジョンに掲げ、子供たちに、未来社会を創造する担い手として「自律して行動する力」、「多様な仲間と協働して問題解決する力」を付けることを目指している。現行の学習指導要領への移行措置1年目から、SDGsの理念の下、地域に開かれた教科横断的なカリキュラムに編成し直し、「まちご エンジョイ ラーニング」というプロジェクト型学習を実施している。これは、地域をフィールドとし、 実社会につながる体験を通して見出した課題を、友達と楽しみながら探究する学習である。SDGsを意識して、最終的には未来の社会・世界に向けて、今の自分たちがすべきことを実践 ・提案し、保護者や地域に発信している。
以下に、防災教育を重視したSDGs理念に基づくプロジェクト型学習「まちご エンジョイ ラーニング」の取組を、低・中・高学年から一例ずつ紹介する。今後は「防災教育ポータル」も積極的に活用させていただき、児童が主体となった学びを一層深めていきたいと考えている。
低学年(第1学年)『きせつのおくりもの(15 陸上資源)』
校内や地域の自然に目を向け、季節を追って変化していく様子に気付き、豊かな自然を大事にしていこうとする感性と心を育てることを目的としたプロジェクト型学習である。年間を通して撮りためた季節の写真を用いて、本校の周辺や玉川学園の自然にかかわるクイズを作成して発表している。

観察結果をデジタルポートフォリオで記録する1年生
中学年(第4学年)『まちごキッズ防災レンジャー!(6 水・衛生、11 持続可能な都市、12 持続可能な生産と消費、13 気象変動 』
体育館での避難所宿泊・運営体験を通して、防災を自分達の身近な問題としてとらえ、未来を創るのは自分達自身であると自覚することを目的とした プロジェクト型学習である。多くの専門家や外部の施設から自然のメカニズムや災害時の取り組みを学び、自然災害の正しい知識と恐ろしさを知り、自分たちができる取組を実践する。発表会では自らをキッズ防災レンジャーとして来場者に情報提供し、地域の防災意識を高める啓発につながっている。

4年生の避難所宿泊・運営体験
高学年(第6学年)『わたしたちの未来社会(3 保健、5 ジェンダー、7 エネルギー、9 インフラ・産業化・イノベーション、11 持続可能な都市、13 気象変動、15 陸上資源)』
持続可能な地域、国、地球を守ろうとする意識を高めることを目的とした総まとめのプロジェクト型学習である。地域のよりよい未来のため、 SDGs の目標を踏まえて、自然環境維持 ・防災対策 ・ 先進技術を駆使したまちづくりの3つのプロジェクトに分かれ、フィールドワーク(地域だけでなく林間学校での自然体験も含める)・調査活動・市の担当課への取材、現状をよりよくするものづくりの制作(プログラミング)等を行い、課題解決のためにできることを実践する。調査結果、実践報告と未来への提案は、プレゼンで 保護者・地域・市の担当課に発信する。学習を通して経済活動と環境保全のバランスについて検討していくことの重要性にも気付くと同時に、福祉や人権問題にも意識が高まる。この学習は、地域から国へ、さらに地球全体に目を向け、世界の国々の現状と課題を知る活動に発展していく。

市長にプレゼンする6年生

地域の方に防災対策を提案する6年生
【令和2年10月21日掲載】