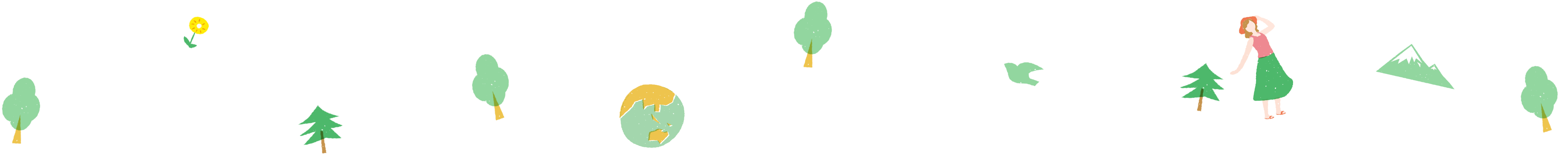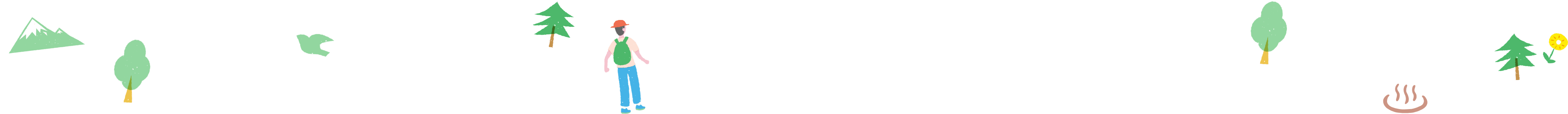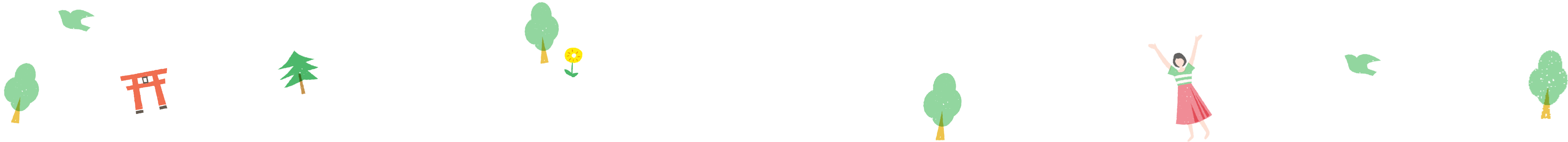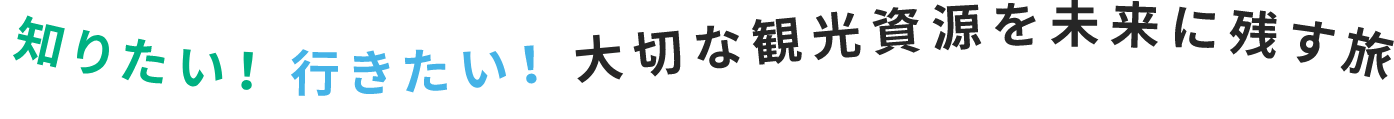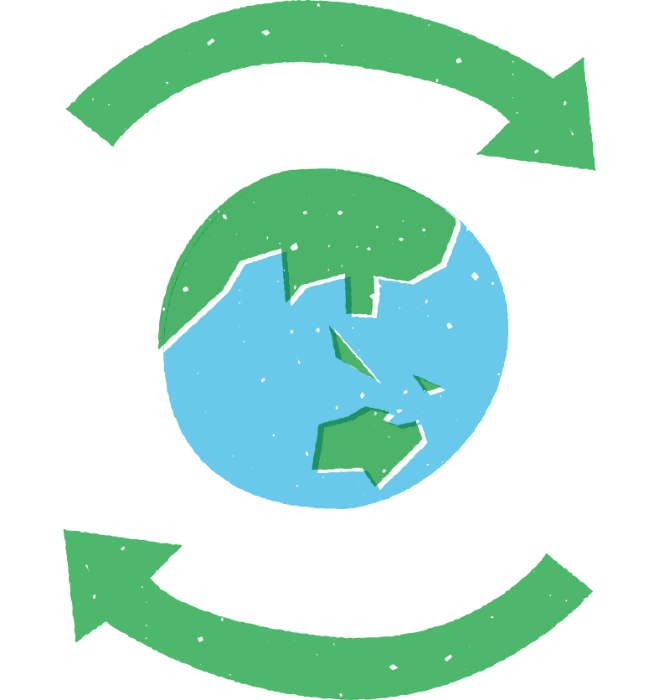
サステナブルな旅とは?
単に旅行を楽しむだけではなく、観光により旅行先の地域資源を持続的に保ちながら、そこに暮らす人々の生活も豊かになるように考えられた旅のことです。旅行先の文化や環境の保全を考え、現在および将来において持続可能な社会をつくることに寄与するような旅が重要になってきています。

サステナブルな旅アワードとは?
持続可能な観光を浸透させる目的として創設されたアワードです。海外ではサステナブル志向が高まっており、特に欧州においては持続可能な観光の取組を行っているかどうかが旅行者のプラン選択の基準になるほどです。日本でも「サステナブルな旅アワード」をきっかけに持続可能な旅行商品が増加し、旅行者にとって魅力的な旅行の選択肢が広がることを目指します。
くわしくみる
日本国内の旅行業者から寄せられたサステナブルな旅行商品について、持続可能な観光に対して様々な視点からの知見を持つ有識者が審査を行い、優秀な商品を選定しました。 大賞1点、準大賞1点、特別賞5点、奨励賞5点を紹介します。
(2023年の受賞者はこちら)
大賞
美しい山々と諏訪湖に囲まれ、諏訪大社や宿場の風情が残る町で、自然・歴史・文化が織りなす魅力を存分に味わうことができる、特別なプログラムです。日ごとにテーマを定め、各ジャンルに精通した現地ガイドがご案内します。個人では知り得ない学びある解説のもと町を巡り、地域で暮らす人々が見ている風景、大切にしている伝統や文化といった「下諏訪の本質」に触れることができる旅をお届けします。
準大賞
特別賞
-

世界文化遺産を散策する
ディープな天草の旅へ 世界遺産「崎津集落」をガイドとともに歩くサステナブルディナー付きツアー天草宝島案内人の会
公共交通機関が脆弱な天草地域において、それを補完し、来訪者の満足度を高めることを目的として2008年から「天草ぐるっと周遊バス」の運行を開始。当初からガイドが同乗してきました。その後、「崎津集落」の世界文化遺産登録前後には、特に教会の拝観と集落内の散策に注意を促すなどインタープリターとしての役割を担ってきました。
2023年から天草市内観光事業者間では「サステナブルツーリズム」に対する関心が高まりを見せ、「アマクササンタカミングホテル」がいち早く地元生産者のこだわりの食材による「サステナブルディナー」を開発。今回のツアー造成につながりました。 -

縄文Well-beingを実感する
奥津軽縄文Well-being滞在プラン1泊2日(春・秋)一般社団法人かなぎ元気村
縄文の暮らしの中心にあった縄文竪穴風住居のリフォームと縄文から続く青森ひばの森の中をマウンテンバイクで走り、山の幸を採取し、焚火を囲み、縄文時代に使われた素材での料理を実際に楽しみながら、古民家に泊まり、縄文Well-beingを実感する2日間。縄文の自然とともにある暮らしをイメージし、森の木漏れ日や渓流の魅力を実感するWell-being&アドベンチャー体験。食事は、縄文料理研究家監修の四季折々の縄文を意識した料理を提供。春は新緑、秋は紅葉が美しい。茅のぬくもりを次世代へ紡ぐプログラムになっています。
-

みんなで体感するネイチャーポジティブ入門!
コミュニティ型リジェネラティブツーリズム 旅するいきもの大学校!〜第1期シリーズ〜旅するいきもの大学校!事務局
(クラブツーリズム株式会社/合同会社HiTTiSYO/株式会社フューチャーセッションズ/株式会社大広/株式会社松本山雅/生坂村)テーマは「ネイチャーポジティブと何度も訪れたくなるふるさとづくり」です。単なる観光体験にとどまらず、自然環境の保護と再生について考え、共に行動することで、長野県生坂(いくさか)村の自然環境を未来にわたって守り続けることを目指します。また参加者を「生坂村公式自然研究員」として認定し、彼らが地域の自然保護活動に積極的に参加することを奨励します。地域の方々との交流も大きな目的にしており、まさに自身の「第2のふるさと」となっていくようなコミュニティづくりを目指します。
-

小豆島の中山地区を散策・体験
【ガイド付き】中山千枚田と農村歌舞伎舞台を満喫する散策&体験ツアー一般社団法人小豆島観光協会
「水を巡る中山千枚田の四季」をテーマに、小豆島の中山地区でしか体験できない散策体験型ツアー。中山千枚田を散策したり、普段公開していない農村歌舞伎舞台や道具小屋を見学したり、中山地区の美しい自然、400年を超えている歴史と文化、棚田の稲作などを体感いただけます。お昼は、大人気のこまめ食堂で中山千枚田のお米と小豆島の食材を活かした「棚田のおにぎり定食」。地元のガイドはもちろん、中山千枚田を巡りながら、地域の方と出会って交流を深めることもツアーの醍醐味です。
-

~「三方よし」から、「十方よし」へ~ 縁(えにし)の旅
ふくいヒトモノデザイン株式会社
禅の道場として名高い大本山永平寺を源流とする教えや息吹を自然に吸収し、文化として醸造してきた永平寺町。精通するガイドにより地域の生業にも触れながら、育まれてきた“縁(えにし)”に自ら縁を結び、限りない縁の世界に導かれていく。縁の中に在る実感が感謝へと変わる旅を提供いたします。
この旅の主要舞台となるのは、京都から越前に禅を伝える拠点を移された道元禅師が、新天地となる永平寺開創前の一年間を過ごされた吉峰寺です。今も永平寺の修行僧数名が地域住民とのご縁も大切にしながら修行に励んでいます。この地に身を委ね、坐禅や精進料理を体験し、地域の方との触れ合いを通じて、豊かな縁の世界に包まれてみませんか。
奨励賞
-

~佐久市内山で機織り・藍染め等の
文化体験~ 地元の猟師さんが獲った鹿・猪・熊 山のご馳走と世界遺産『荒船風穴』を巡る旅有限会社岩崎呉服店
渋沢栄一ゆかりの長野県佐久市内山で、「鶴の恩返し」で見られる機織りや、自然の川でTシャツを藍染め、川で魚捕まえて囲炉裏で焼いたり、薪割したりと里山の暮らしを体験いただけます。火吹き竹を使いかまどご飯焚いて、猟師さんと一緒に鹿猪鍋を堪能でき、地元の食材を使った料理体験や、世界遺産「荒船風穴」訪問などを通じて、伝統文化と自然の魅力を深く体感できる一泊二日のサステナブルツアーです。
明治時代から伝わる文化体験を楽しみながら、地域と自然の保護にも貢献。記憶に残る特別な体験をお届けします。講評
「“地域一体型ツアー”で地元ともに成長する持続可能な観光」
築110年の呉服屋の建物をリノベーションして「伝統文化体験の宿」として再生。地域の文化施設や伝統工芸の職人と連携して佐久市内山に残る伝統的な藍染体験やぼろ織り(裂き織り)体験などを行う。旅行者だけでなく地域や関係者との深い関係構築が成功のカギと考えている。例えば、旅行者には旅前の予備知識の提供、到着時に地域の紹介やツアー全体の説明を行うウェルカムイベントの実施、ツアー後はフォローメールを送り思い出や学びを振り返る場を提供。地域の関係者にはツアーの反響や感想などのフィードバックを行い目的の共有や地域連携を図る。地域全体で観光客を受け入れる「地域一体型ツアー」を意識することで、地元ともに成長する持続可能な観光を目指している。 -

“旅”の醍醐味を手ぶら体験
手ぶらで日本の精神浄化を実感できる京都の滝行株式会社エリアプロモーションジャパン
生命の重要な要素である水、古来大切にされてきた京都の清水をふんだんに浴び心身浄化、人生の転機での決意表明に最適な滝行。この千手の滝のある場所は御所から見て青龍という恵方に位置し、後白河法皇も熊野詣御出立前には必ず行われた歴史もあります。行を見守る荒々しい山の佇まいや不動明王像に心を解放し、社殿での御祈禱、御朱印授与もありまた新たな気持ちで前へ進む。そんな“旅”の醍醐味を手ぶら体験して頂けます。
講評
「手ぶらで歴史ある神社での滝行を体験し日本の精神文化に触れる」
後白河法皇に由来する歴史ある熊野若王子神社と協同して、地域に残る滝行を体験して日本の精神文化に触れてもらう企画。インバウンド客をも意識して滝行衣を用意するなど「手ぶら」での体験を可能にしているが、宮司さんによる神社の歴史講話や参拝のお作法など内容は本格的。同社は参道等の掃除への協力、周辺の飲食店への案内、地元の呉服商との協働など地域貢献も行っている。滝行後の朝食とうふ懐石付き商品展開など、新しい視点からの提案で京都観光の混雑緩和への貢献も期待される。 -

地元生産者との直接交流を通して
宮古島の自然と人が作り出してきた文化・歴史に触れるツアー農業生産法人株式会社オルタナティブファーム宮古
地元生産者との直接交流を通して、宮古島の自然と人が作り出してきた文化・歴史に触れるツアーです。
知るとさらにくなる!『食文化の見学』
→ 海ブドウなどの生産現場を見学
自分で作る出来立てが美味しい!『食文化の体験』
→ 地元のお母様の指導で郷土料理作りなど
豊かな文化・生活の知恵を実感する!『工芸・芸能』
→ 宮古上布、三線/木工芸の工房を見学など
自然と生活の繋がりが見えてくる!
→ マングローブ、鍾乳洞など、自然散策講評
「生産者を通して知る地域のリアルと魅力」
目的は、海ブドウやマンゴーなど地元の生産者と観光客を直接つなぐことで地域のリアルと魅力を知ってもらうこと。現在、島内に4分野15か所の訪問先があるが、いずれも地元民でないと作れない地元密着型のコンテンツである。島民には普通のことでも観光客が驚き感動してくれるので、地元の誇りを再認識する機会となっている。従来型の「消費する観光」から観光客の協力を得て宮古島の未来につながる新しい「創造する観光」を目指している。収益が上がれば子供たちの地域への誇り醸成のために小中学生向け無料ツアーも計画している。 -

自然の驚異・脅威から自然の力を感じ、
共存を考える旅 ~カーボンオフセットを活用した環境ツーリズム~熊本県旅行業協同組合
『令和2年の豪雨災害からの復興』を目指し、人吉球磨の自然・食・日本遺産を活用した旅行商品を開発。防災教育を盛り込み、カーボンオフセットも導入。球磨川ラフティングや特産品を使ったBBQ、植林体験、人力車でのガイドツアーなどが楽しめます。地元住民との交流や復興支援活動が組み込まれており、参加者が地域の現状を理解し復興の取り組みに参加することで、大自然の驚異と脅威を体感しながら持続可能な観光を実現します。
講評
「災害からの復興を組み込んだ共存を考える旅」
令和2年7月の豪雨災害を知ることから自然の驚異・脅威を感じてもらい、災害からの復興活動に地域住民と共に取組むことで理解や支援を得ることを目指している。関係者との交流を通じて持続可能な自然と共存する社会を一緒に考える。ツアーの企画段階から住民や関係者の参画をすすめているので、住民による案内ガイドや住民から学ぶ体験プログラムなど住民目線での人吉の魅力が詰まった内容となっている。「学び」の要素も多いので、教育旅行への展開も考えられる。 -

ひがし北海道 中標津町
冬の魅力と自然環境を考える旅 モアン山スノーシューハイキングと野付半島氷平線ミニウォークバスツアー一般社団法人なかしべつ観光協会
中標津(なかしべつ)町のモアン山でのスノーシューハイキングや、別海(べつかい)町野付半島大氷原でのトリック写真撮影を通じて、地域の冬の魅力を存分に体験できるプランです。自然を体感できるアクティビティ、地元素材を活かした昼食、そして地元の皆さんとの交流を一体化させ、雪道の運転が不安な方々に配慮したバスツアーです。道東にも押し寄せる温暖化について実感しながら、今後の私たちの行動について考える旅です。
講評
「中標津の山と別海町の海を同日に案内することでエリアの魅力を多面的に体験する旅」
雪道での運転が不安な旅行者には、移動、観光(アクティビティを含む)、食事、地元民との交流が 一つになったツアー内容は魅力的だ。山上から林で格子状に区切られた酪農地の文化景観を眺め、JAの協力を得て町の生業である酪農について知ってもらう。さらに、隣接する別海町野付湾の凍った大氷原を案内することでエリアの魅力を多面的に楽しむ企画内容。参加者の好反応から今後も継続の見込み。ツアー代金の一部を「北海道遺産『格子状防風林』等の森林保全 と環境保全」に充てる。
審査委員
-
審査委員長
北海道大学 観光学高等
研究センター
客員教授小林 英俊
-
審査委員
名城大学外国語学部
名誉教授
GSTC公認トレーナー二神 真美
-
審査委員
一般社団法人JARTA
代表理事高山 傑
-
審査委員
日本コンベンション
サービス株式会社
営業・マーケティング
戦略部 グローバル・
ゴール推進リーダー松原 努
-
審査委員
NPO法人
大雪山自然学校
代表理事荒井 一洋
-
審査委員
株式会社楽帆
代表取締役北村 尚武
審査委員総評
今回の申請書を読んでまず感じたのは、地域の特徴を活かしたいろいろな「サステナブルな旅」を創り出そうという動きが出てきたことです。サステナブルな観光づくり、地域づくりにたいする考え方が浸透してきていると感じられます。「サステナブルな旅」づくりで、大事なコトは地域資源の観光利用と保全・保護とが循環するしくみづくりです。
昨年度大賞の阿蘇市は、普段は入れない牧野をあるルールのもとで開放して新しい観光スタイルを創り出して滞在客を増やし収益の一部を牧野の保全に回すという仕組みを新たに作っています。今年度の大賞の下諏訪町は普段は入れない縄文時代の黒曜石の発掘遺跡を遺跡の発見者・発掘者同行の条件で特別に見学させてもらい、収益の一部を遺跡保存に回すという「利用と保全・保護」の好循環を生み出しています。これは、自然資源や文化資源だけでなく、「ヒト」にも言えることで、地域にいる在野の研究者や伝統芸能の伝承者に観光の光を当て外の人にも評価してもらう。これにより、ますます研究や芸能にも力が入り、地域の魅力が増すことになります。後継者や新たな支援者が現れる可能性も高まります。対象の下諏訪町では、案内・説明してくれる「ヒト」が皆さん生き生きと楽しく語ってくれるので引き込まれてしまいます。
今年の申請書をみると収益の一部を資源の保全や人材育成に使うのは当然と考えるようになってきたようで、地域の実情に合ったサステナブルな循環システムの創出が期待されます。
申請された「サステナブルな旅」の多くが住民の参画を促し、住民が案内役や解説者となるなど重要な役割を果たしています。住民との交流事業は地域でのサステナブルな旅の必須項目のようになりつつありますが、特別賞の長野県生坂村、奨励賞の人吉市のように住民から地域課題を聞いて一緒に「自然と共生する地域づくり」を目指すという新しい動きも出てきています。地域資源の観光による「利用と保全」のバランスを保つには、住民の地域資源に対する強い愛着とそれを理解する外部の人の存在が不可欠です。今回受賞した地域では、地域住民を主要メンバーにすることでこのバランスを保とうとしています。地域の旅行事業者や行政の役割は、それまでに培ってきたノウハウやネットワークをフル活用して住民を主役に立てながら裏でしっかりと関係者の役割をコーディネートしてサポートすることです。
では、大手旅行会社の出番がないかというと、2年連続特別賞のクラブツーリズム㈱のように旅行会社として仲間づくりやテーマ性の旅をつくってきたノウハウを活かしながら地域のために関係者をつなぐコーディネーターとして活躍している例もあります。
特別賞を受賞した小豆島には小豆島町と土庄町とがありますが、サステナビリティ(持続可能性)の概念を学んだことから「小豆島は一つ」と考えるようになり、2024年の国際認証(GD)には両町が協力して申請してシルバーアワードを獲得しています。昨年10月の東京・大阪での商談会も二つの町が一緒になり行っています。また、奨励賞の中標津町も隣の別海町と協力してエリアの魅力を訪ねるツアーにしています。特別賞の長野県生坂村でも、環境領域で同じ考えを持つ企業連携の可能性も出てきています。今回の申請書を読み解くと、これからサステナビリティ(持続可能性)の考え方が広まってくると従来の行政や企業の枠を超えた新しい結びつきによるエリア観光が生まれてくる可能性がみえてきます。
最後に、今年度の「サステナブルな旅AWARD」は2回目ですが、受賞地の多くが観光庁のいろいろな事業(持続可能な観光地モデル事業、魅力ある観光コンテンツ造成事業、持続可能な観光コンテンツ高度化事業、第二のふるさとづくり事業等)を上手く活用して商品づくりを進めていることが分かります。また、この「サステナブルな旅AWARD」を意識してツアー企画をしたというところが数か所ありました。持続可能な観光地づくりは、観光庁の主要3本柱の一つですが、この「サステナブルな旅AWARD」はその進捗状況を把握する一つの指標になるのでは思われます。
北海道大学
観光学高等研究センター 客員教授
審査委員長
小林 英俊