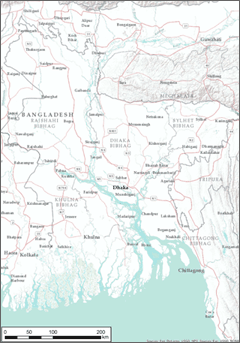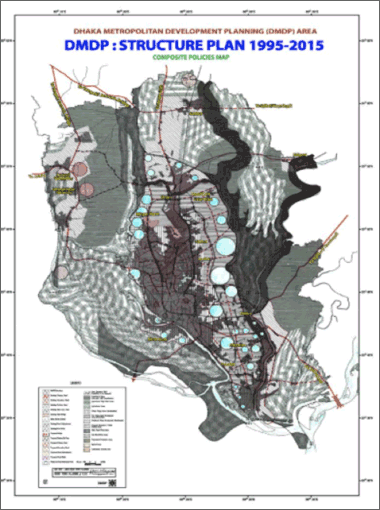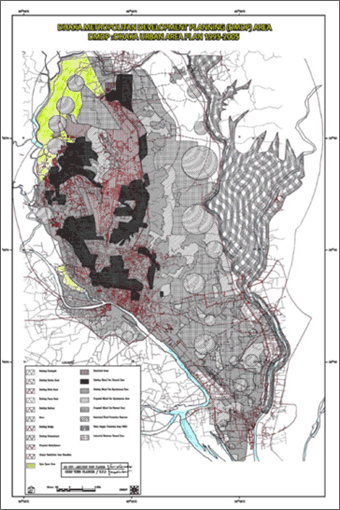概況
バングラデシュはインド洋・ベンガル湾の最奥部に位置し、パドマ川(上流のインド領内ではガンジス川)、ジョムナ川、メグナ川といった大河の下流あるいは河口部にあるため国土の約50%は標高6~7m以下で、約68%の土地が洪水や土壌浸食の危険にさらされている。国の3方はインドと国境を接しており、南東部の一部でミャンマーと国境を接している。
同国は、1947年にパキスタンの一部として独立し、その後1971年にバングラデシュとして独立した。約1.5億人の国民の約9割はイスラム教徒であるが、ヒンズー教徒、仏教徒、キリスト教徒もいる。
かつては、最貧国の一つと言われていたが、主要計画(Perspective Plan 2021など)で独立後50年に当たる2021年までに中所得国になる目標を掲げ、近年では年率6%程度の高いGDP成長率を維持している。一方で、急速な都市人口の増加や膨大な人口に対応した産業構造の高度化などの課題に直面している。
表国勢概要
| 国名 | バングラデシュ人民共和国 (People's Republic of Bangladesh) |
|---|---|
| 国土面積 | 14万7千km² (日本の約4割) |
| 人口 | 約1億5,940万人 (2015年10月:バングラデシュ統計局) |
| 人口密度 | 1,107人/km² |
| 都市人口比率 | 34.3%(2015年) |
| 実質GDP | 1,566億ドル(2015年:世界銀行) |
| 一人当たりGDP | 1,385ドル (2016年度:バングラデシュ統計局) |
| 産業別 就業人口比率 |
第一次産業15.1% 第二次産業28.6% 第三次産業56.3% (2016年推計) |
| 経済成長率(GDP) | 7.11% (2016年度:バングラデシュ統計局) |
(情報更新:2017年3月)
図バングラデシュの地形
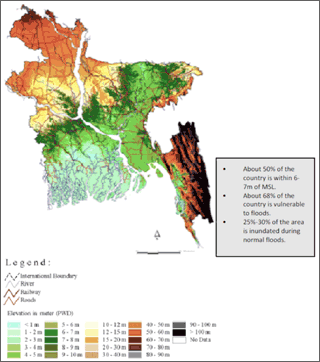
出典:Disaster Management Bureau, Disaster Management & Relief Division, National Plan for Disaster Management 2010-2015, April 2010
バングラデシュの地方制度
バングラデシュの行政区画は、管区(Division)、県(District/ Zilla/ Zila)、郡(Sub-district/ Upazilla/ Thana;以下ウポジラ)がおかれている。また、農村部ではその下にユニオン(Union)、都市部では市(大都市(City Corporation)、一般都市(Pourashava)がおかれている。バングラデシュ人民共和国憲法59条(1)項では、「全ての行政区域の地方政府は、法に基づいて選出された人々からなる組織に信託される」とされている。ただし、直接選挙で選ばれるのは、ユニオン議会及び大都市・一般都市の市長及び議会のみ。
図バングラデシュの地方制度
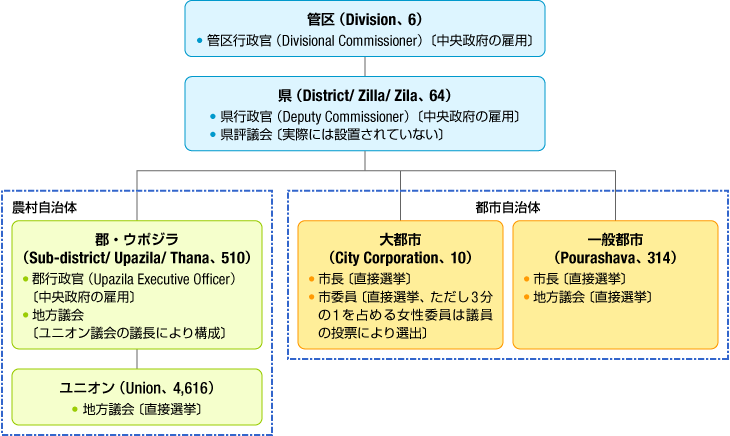
- *いずれの地方自治組織も条例を制定する権限はない。
- *なおチッタゴン地域では、少数民族への配慮から民族別の定数配分が行われている。
資料:粟津卓郎[『バングラデシュの基本法制に関する調査研究』法務省、2014年2月28日を参考に作成
(ただし、各地方政府の数は、バングラデシュ教科書、Civics and Citizenship、クラス9-10より)
国土政策に関わる政府機関等
| 計画名又は行政分野 | 担当機関 | ホームページ |
|---|---|---|
| 計画委員会 Planning Commission |
総合経済局 General Economics Division (GED) 〔計画委員会は、首相が議長を務める会議で、5カ年計画など最高レベルの国家計画を最終的に承認する。GEDはその事務局。〕 |
http://en.banglapedia.org/index.php?title=Planning_Commission |
国土・地域の整備に係る計画・政策
国全域を対象とした総合的な国土計画としては下記のものが上げられる。これらは経済計画としての色彩が強いが、インフラ整備などに関する記述も含まれている。
Vision 2021は、現政権を担うアワミ連盟が2008年の総選挙に先立ち、マニフェストとしてまとめた文書。2021年(独立後50年)までにバングラデシュを中所得国にするなどの目標が掲げられ、政府の文書ではないものの、各省の主要計画などにその考え方が反映されている。
Perspective Plan (2010-2021)は、Vision 2021を実現するために計画委員会(計画省総合経済局-General Economics Division, GEDが事務局)により2012年4月に策定された政府として最も基本となる長期計画。
第6次5カ年計画(Sixth Five Year Plan FY2011-FY2015 Accelerating Growth and Reducing Poverty, Strategic Directions and Policy Framework)は、上記Perspective Planの実現のため、同じく計画委員会により策定された計画。本計画は貧困削減戦略(Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP))として位置づけられている。
上記5カ年計画に即して年間開発計画(Annual Development Programme; ADP)が決められることになっている。ただし、必ずしも年間計画が5カ年計画に即していないとの指摘もある。
Perspective Plan及び5カ年計画は、計画委員会により決定される。
また、上記の諸計画の財政的裏付けのため、財務省により5カ年の中期予算フレームワーク(Medium-Term Budgetary Framework ; MTBF)が策定され、年間予算が決められている。
バングラデシュ・デルタ・プラン2100(BDP2100)は、計画委員会総合経済局で現在策定が進められている超長期計画。気候変動に適応し、災害リスクの軽減、水の安全を図り、国家の食糧安全保障と経済発展に貢献することを目標としている。
図バングラデシュの国土計画、予算・計画管理システム
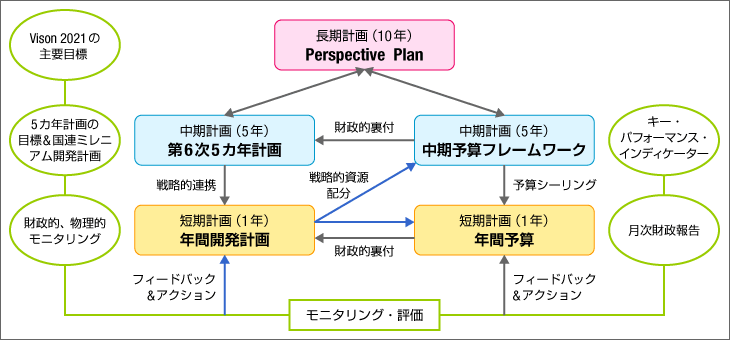
出典:バングラデシュ政府 計画委員会 総合経済局 資料をもとに作成
図下位貧困ライン以下の人口比率2010年及び社会的排除ポケット(ウポジラ)
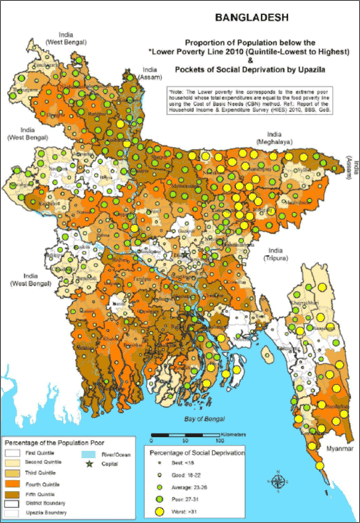
出典:Binayak Sen and Zulfiqar Ali, "Ending Extreme Poverty in Bangladesh During the Seventh Five Year Plan: Trends, Drivers and Policies", Background Paper for the Preparation of the Seventh Five Year Plan, General Economics Division (GED), Planning Commission, Government of Bangladesh, January 2015
- *下位貧困ライン(lower poverty line)とは、この調査では貧困ラインに使われている必要な栄養量(1,805kcal/日)を摂取するために必要な金額が全収入と同じ額。
- *社会的排除指標(social deprivation index)は、複数の非収入的指標を合成したもの。
地域政策の動向・現状と政策課題
<地域政策の方向>
地方自治制度の項で述べた通り、バングラデシュでは、地方政府が憲法で位置づけられているが、実際には地方政府の権限や実務能力は限られており、中央政府の各省庁が出先機関を通じて実務を行っていることが多い。
地方政府・農村開発・協同組合省(Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives)は、様々な形で地方政府を支援することを任務とした省で、主に下記の分野を所管している。
- -地方政府への補助。地方政府支援プロジェクト(Local Governance Support Project; LGSP)により補助を行っている。また、近年では同省がユニオンを対象として基礎的包括補助金(Basic Block Grant)及び業績評価により支給されるパフォーマンス包括補助金(Performance Block Grantの形で補助を行っている。
- -ウポジラ(郡)道路及びユニオン道路等の地方道路、水路などの整備・維持。
- -上下水道の整備・維持。大都市においては同省が直轄する上下水道公社が整備・維持を担っている。
- -村落の市場の整備・維持。
- -村落警察に関する事項。中央政府が管轄する警察とは別に、職員数10人程度の村落警察(village police)があり、同省が管轄している。
同省の中の地方政府技術局(Local Government Engineering Department; LGED) は、地方道路整備をはじめとした実務を担っているが、きわめて効率的な運営が行われているとの評価がある 。なお、LGEDのみの予算額392億タカ(2009-10会計年度)はバングラデシュ政府の総予算額の14%を占める。また、総職員数は1万人超で、その99%のスタッフは地方レベル(District-県及びUpazila-郡)で勤務している。組織的には、64の県に対してそれぞれ一つのオフィスが配置され、所長のもとに12~13人の職員が配置されている。また、国全体で482の郡にオフィスがあり、ぞれぞれの郡のオフィスに所長及び約18人のスタッフが配置されている。LGEDの任務は、地方レベルにおける道路、橋、上下水道などのインフラ整備などの実施が中心。
<不利益地域の現状>
バングラデシュは、パドマ川、ジョムナ川、メグナ川といった大河によって分断されており、近年まで東部地域に比べ西部地域で貧困率が高いとされてきた。しかし、近年ではそうした格差は縮小方向にある(ただし、南西部・南央部・北西部の一部が比較的貧困率が高い地域が残されている)。また、1998年のジョムナ橋の完成、現在建設中のパドマ橋の建設などにより、さらに格差の縮小が期待されている。
一方で、広域的に見れば比較的豊かな地域でも、「貧困ポケット」とも言える小さな貧困地域が残されており、そうした地域への対応が課題となっている。
現在準備中の第7次5カ年計画の策定過程では、こうした地域間不均衡に関する調査が行われた。
大都市圏計画(ダッカ)
<大都市圏計画>
| 名称 | ダッカ大都市圏計画及び関連計画 (バングラデシュの計画体系は、基本的にストラクチャープラン、アーバンエリアプラン、詳細地域計画(DAP)の3層になっている。ダッカ大都市圏の場合、これら3つに加え大都市圏計画がある。) |
|---|---|
| 計画期間 |
|
| 策定機関 | RAJUK(Rajdhani Unnayan Kartripakkha, バングラデシュ首都整備庁) (UNDPの支援のもとに策定) |
| 計画の法的位置付け | RAJUKそのものの法的根拠は、Dhaka Improvement Trust (Allotment of Land) Rule of 1969 及びd The Town Improvement Act of 1953) |
| 計画の目標と開発戦略 | <詳細地域計画の目的>
|
| 主な特徴 | 詳細地域計画の策定を通じて、下記の方法によりストラクチャープランなどの実施が促進された。
|
出典:RAJUK(バングラデシュ首都整備庁HPより)
<首都整備庁について>
RAJUK(バングラデシュ首都整備庁)は、中央政府によって指名された委員長及び5人の委員による委員会によって管理されている。上級機関は住宅・公共事業省(Ministry of Housing & Public Works (mohpw))。
RAJUKは、ダッカ大都市圏の計画と開発管理について責任を負っている。
- -計画:同庁は各種の計画策定並びに実際の道路、橋梁などの建設を実施している。
- -開発管理 (Development Control):下記の法律等に基づく開発管理の実施。
The Town Improvement Act 1953
The East Bengal Building Construction Act 1952(全ての建設工事には許可が必要とされている。)
同庁が所管するのは、ダッカ市及び周辺のDistricts(面積1,528km²)。
なお、バングラデシュの大都市(City Corporations)には全てRAJUKのような開発庁がおかれていて、空間計画及び開発管理を行っている(現行では、地方政府はこうした空間計画計画及び開発管理事務に関与しておらず、本来は地方政府が行うべきという意見もある)。
地方計画
<中央政府による地方計画>
バングラデシュでは地方政府・農村開発・協同組合省)により、農村道路・橋梁・暗渠の整備・維持、市場などの整備、上下水道整備など地方開発の大きな部分が担われている。
同省関連の主要地方計画等としては下記のものがある。
- -農村開発戦略1984(Rural Development Strategy 1984)
- -農村インフラ戦略研究1996(Rural Infrastructure Strategy Study 1996):農村地域の成長センターとして特定した場所への集中投資する戦略(後の第6次5カ年計画では全国で2,100の成長センターが特定されている)。
- -国家農村開発ポリシー2001(National Rural Development Policy 2001)
- -農村道路・橋梁メンテナンスポリシー2013(Rural Road and Bridge Maintenance Policy 2013)
- -国家都市セクターポリシー2011 (National Urban Sector Policy 2011):分散化・階層化された都市システムにより地域的にバランスの取れた都市化の実現
上記の上位計画である、Perspective Plan及び第6次5カ年計画でも農村道路の整備をはじめとした地方でのインフラ整備の推進などが位置づけられている。特に、農村道路整備が生産コストを減少させ、雇用の拡大につながること、医療や教育へのアクセスが改善され人的資源開発に貢献することが強調されている。
<地方政府による計画>
近年、ポルシャバ(一般都市)レベルにおけるマスタープランの策定が進められている。
また、ウポジラ(郡)法1998(Upazila Parishad Act 1998)23条では、ウポジラが5カ年計画及びそれ以外の期間の諸計画を策定する義務を負うことが明記されており、マスタープランの策定が進められている。
ただし、ポルシャバ、ウポジラにおけるマスタープランの策定については、地方政府・農村開発・協同組合省などの中央政府の省庁が関与している。
また、5カ年計画などの国レベルの計画とリンクしていないとの指摘がある。(大都市では、各市におかれた都市整備庁によりマスタープランが策定されている。これらは空間計画ではあるが、各開発庁は住宅・公共事業省の所管の下にあり、地方政府によるものではない。また、これらのマスタープランも5カ年計画とリンクされていないとの指摘がある。)
社会資本整備
バングラデシュはパドマ川はじめとした多数の大河により国が分断されているため、橋梁の建設が課題となっており、現在首都ダッカに近い場所でパドマ川への橋梁建設が進められている。
バングラデシュ政府が優先的に整備するとしているインフラプロジェクト(fast track projects)としては、上記のパドマ橋以外に、ダッカメトロレイル、ランパル石炭火力発電所、ルーパー原子力発電所、深水港湾、LNGターミナルの整備があげられている。
上記の内、ダッカメトロレイルに日本政府は約2,500億円の支援を行っている。また、南東部のマタバリ石炭火力発電所にも約3,000億円の支援を行っている。
国境を越えて広域化した空間政策課題
<近隣諸国との交通について>
バングラデシュはインドとミャンマーに国境を接しており、インドを挟んでネパール、ブータンとも比較的近い位置にある。
バングラデシュ政府は、インド、ネパール、ブータンなどとの貿易拡大やインドの東部諸州、ネパール、ブータンなどがバングラデシュの港湾を利用することを望んでいるが、道路状況、出入国管理、関税などが障害となり、実現していない。
バングラデシュ、中国、インド、ミャンマー(中国の昆明からインドのコルカタ)を高規格の道路を結ぶ構想(BCIM構想)がある。
<パドマ川の水資源利用ついて>
パドマ川は雨期には流量が増加し、洪水をバングラデシュにもたらす反面、乾期には水量がきわめて減少する。
パドマ川の上流はインド領内となるが、インドはバングラデシュ国境手前に堰を建設し、乾期にはインド領内への水利用に当ててしまうため、バングラデシュでは乾期の水量が極端に減少している。
(情報更新:2015年3月)