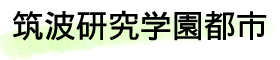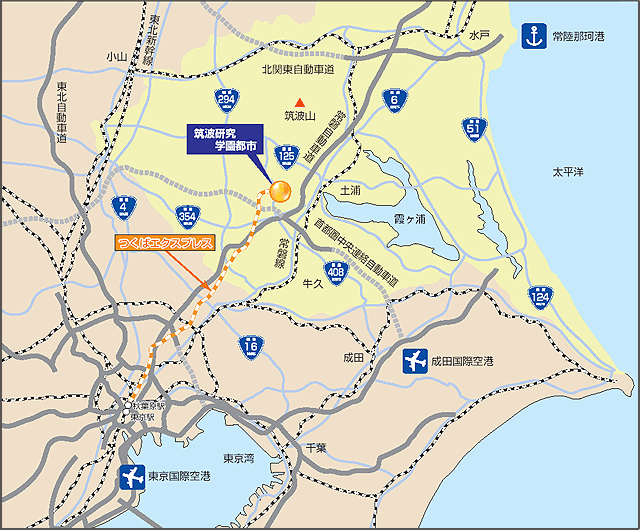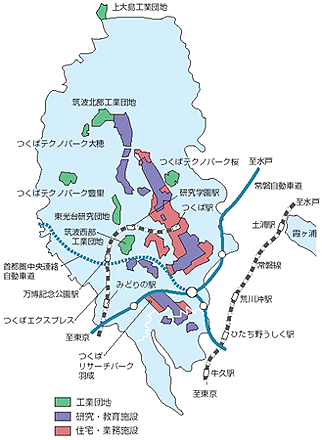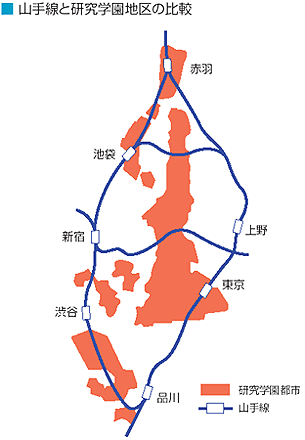- | »国土交通省トップ
| »国土政策局トップ | »大都市圏整備トップ |
筑波研究学園都市は、昭和38年9月の閣議了解により、その建設が決定された。昭和55年3月までには、予定されていた国の試験研究機関、大学等の 施設が移転・新設されるとともに、基幹的な都市施設もほぼ完成した。
その後、都心部の施設整備が進むとともに、周辺部の工業団地等への民間企業の進出も活発化した。
現在、筑波研究学園都市は、人口約20万人弱、国、民間合わせて約300に及ぶ研究機関・企業、約1万人以上の研究者を擁する我が国最大の研究開発拠点と なっている。
目的
筑波研究学園都市は、二つの目的により建設された。
その一つは、科学技術の振興と高等教育の充実に対する時代の要請にこたえることである。
東京及びその周辺から移転した国の試験研究機関と新設した筑波大学を中核として、高水準の研究と教育を行うための拠点を形成し、それにふさわしい環境を整 備することである。
もう一つは、東京の過密対策である。
必ずしも東京に立地する必要のない国の試験研究・教育機関を研究学園都市に計画的に移転することにより、首都圏既成市街地への人口の過度集中の緩和に役立 たせるとともに、その跡地の適正な利用を図り、首都圏の均衡ある発展に寄与することである。
位置と区域
筑波研究学園都市は、東京の中心から北東約60km、新東京国際空港の北西約40kmの距離にあり、北に関東の名峰筑波山を、東にわが国第二の湖 霞ヶ浦をひかえた茨城県南部に位置している。
都市の区域は、茨城県つくば市の1市全域で、面積は約28,400ha(東京都区部面積の約2分の1)、その大部分は標高20〜30mの台地である。
都市構造
都市の中心部に、東西6km、南北18kmにわたり、約2,700haの区域を「研究学園地区」として開発し、国の試験研究・教育施設、商業・業務 施設、住宅等を計画的に配置している。
また、研究学園地区以外の区域は、「周辺開発地区」として研究学園地区と均衡のとれた発展を図るよう整備を進めている。
|
|
|
|
|
|
<筑波研究学園都市 メニュー>
- 土地利用
- 開発の方式
- 推進体制
- 都市の現状
人口/都市整備/国の試験研究・教育機関/民間研究機関・企業 - 筑波研究学園都市における建設・整備状況の点検・評価結果等について(調査報告) [H21.6.22報道発表]
- 筑波研究学園都市の建設推進状況調査について(H19年度)
- 資料(過去の計画など)
<つくば関連リンク集>
- 筑波研究学園都市に立地する大学・研究機関や研究活動の情報、都市情報については、次のサイトをご覧下さい。
つくば市役所
http://www.city.tsukuba.lg.jp/jigyosha/machinami/kenkyugakuen/index.html
茨城県つくば地域振興課
http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/tsushin/kenkyugakuentoshi.html
文部科学省研究交流センター
© 国土交通省 国土政策局 広域地方政策課 All rights reserved.