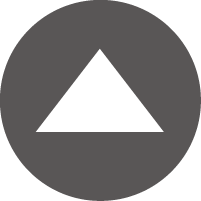- アジア・中東
- 北米・中南米
- 欧州・アフリカ・大洋州

フランス民法典で基本的な土地や不動産の所有などについて定めている。
フランス民法典第2編第2章において、所有権絶対の原則が規定されており、土地の私有が認められている。不動産所有権の範囲については、「土地の所有者は、地上及び地下の所有を含む」とされている(552条1項)。また、土地と建物は一体の不動産として扱われる。
外国人は原則自由に土地・不動産を所有することができる。
建物は土地の附合物とされ、建物単独に権利を設定することや、登記や取引を行うことはできない。登記は第三者の対抗要件(公信力なし)とされ、公示する資料は全て、公正証書の形式で作成される。
フランス土地登記所において登記される。Ministry of Economy and Financeが土地登記を管理しており、公式の土地登記システムはオンラインで利用可能である。オンライン上でユーザーは、登記の仕方や必要書類の詳細の確認、土地や建物の区分の閲覧、土地の測定などができる。
フランスの鑑定士には2種類の資格がある。鑑定評価基準についても、フランス自国の評価基準とヨーロッパ基準のものがある。
不動産を売買、賃貸仲介することで報酬(登録料、書類作成、付随するサービスなども含む)を得るには、知事の営業許可が必要である。これらの業を行う者はImmobilierと呼ばれる。Immobilierは仲介のみを手掛けることがほとんどである。
許可を受ける要件は、政令によって必要な学歴や実務経験の期間等が定められている。営業許可の有効期間は10年間とされ、業者は更新手続きを行う必要がある。また、費用や業務内容の正確な説明、全ての情報提供、不動産業社と依頼者の間で利益相反が起こりうる場合の書面提示、利益に反する行為の禁止等が、業務倫理規定に細かく指定されている。
〔不動産関連法・制度の現状、土地・不動産の所有権〕
Legifrance.gouv.fr「Code Civil」
〔土地・不動産の登記〕
Lawyers France「Land Registry in France」
法務省「我が国と諸外国の不動産登記における登記の真正担保のための方策について」
〔不動産の鑑定評価〕
フランス不動産専門家商工会議所(CEIF-FNAIM:Chambre des Experts Immobiliers de France
The European Group of Valuers' Associations(TEGoVA)
〔不動産事業を行う際の免許制度〕
NNA調べ(2016年11月)
物件購入の正式な契約を締結する前に、事前契約を結ぶのが一般的となっている。事前契約にはクーリングオフ制度が設けられており、締結から7日間以内は取り消しが可能である。事前契約確定後、買主は不動産業者または公証人に、購入価格の5%~10%のデポジットを支払う。
契約前に売主は買主への情報提供として、物件についての技術的な診断書を作成しなければならない。診断書には、消費電力量、電気系統やガス管の状態、建築材内の石綿の有無などが明記されている。
売主が作成した診断書と、買主が用意した戸籍謄本や本人の身分を証明する書類は、買主の公証人に提出される。本契約までの間に、公証人は物件の調査をし、名義変更や登記などの法的手続きを行う。一方、買主は仮契約書をもとに、銀行からの借り入れ手続きなど資金調達を行う。
仮契約後、公証人から、クーリングオフ期間の証明書が送付される。
消費者法典において、不動産取得のための融資に関する消費者保護が規定されている。ローン契約、関連不動産販売契約、ローンの期限前償還等が項目として挙げられる。
また、物件購入の際の仮契約後、7日間のクーリングオフ制度が設けられており、仮契約締結後に公証人から買主に、クーリングオフ期間の証明書が送付される。
賃貸物件の供給を増やすことを目的にした減税措置。最大12年間にわたり、トータルで物件価格の21%に当たる金額を所得税額から減額することができる。ピネル減税措置を利用できるのは、物件価格(購入価格+公証人の費用)のうち 300,000ユーロの金額まで、との上限が定められている。
国が利息を肩代わりする融資で、生活の拠点となる住居を初めて購入するケースが対象となる。中古、新築住宅の両方に適用される。ゼロ金利ローンで借りる金額が、購入価格の40%まで利用できる。世帯の所得額が一定額未満でなければならないが、その上限額が更にアップし、より多くの人が利用できるようになった。例えばパリ市内で 2人子供を持つ夫婦世帯の場合、世帯の所得が 74,000ユーロ以下であれば、ゼロ金利ローンを利用できる
持家の取得・改良等のために利用者が自助努力で貯蓄を行い、貯蓄した金額に応じた融資が比較的有利な金利で利用者に供託され、国が補助金を提供する制度。貯蓄に対する利息および国の補助金は一定に免税の対象となる。貯蓄期間の長短によって、積立式住宅貯蓄(PEL)と通帳式住宅貯蓄(CEL)の2つの制度がある。
2016年6月より政府は家庭による省エネ暖房器具や、暖房のエネルギー効率強化につながる断熱材・断熱(二重)窓などの購入に対し、税額控除を認めている。
ピネル減税措置、ゼロ金利ローン等国による政策の他、金融機関が独自に提供している様々な住宅ローンがある。固定金利、変動金利、当初固定金利があり、固定金利が多い。 返済期間は最長30年までとしている商品が主だが、平均的な償還期間は約15年となっている。またフランスでの住宅ローンの特徴としては、抵当権を設定せず、第三者の補償をつけてローンを実行する場合が多い点があげられる。
一次取得者の典型的な融資率は9割程度とされている。
〔不動産を取引する際の制度〕
Le site officiel de l'administration francais「Quels sont les diagnostics immobiliers a fournir en cas de vente?」
French Law 「Buying/Selling A Property in France - French Property Law」
〔消費者保護〕
Le site officiel de l'administration francais「Credit immobilier : la protection du consommateur renforcee a partir du 1er juillet 2016」
〔不動産行政の方向性〕
Le site officiel de l'administration francais「Aides et prets pour l'amelioration de l'habitat」
〔不動産金融〕
不動産購入時、公証人費用(購入価格の2.5~7%)を支払う必要がある。これには、不動産取得税、県税、市税、その他登記に必要な諸経費、公証人への謝礼費用1%が含まれている。
売主に課税される。所有期間5年未満の場合は32.50%、5年目から毎年2%ずつ、17年目から4%、24年目から8%下がり、30年目にゼロになる。また、自分で居住していた物件の売却にはキャピタルゲイン税はかからない。
所有者、賃貸人等、個人は居住している住宅(別荘も含む)について課税される。別荘については、居住していなくても居住可能の場合、居住の権利を有する者に課税される。居住可能であるにもかかわらず、5年以上空家だとペナルティ、10年以上空家だとさらにペナルティが課せされる。課税標準は、物件の台帳賃貸価格から、一定の控除を差し引いたもので、台帳賃貸価格は、通常の条件下で、当該物件がもたらすであろう理論上の賃料に基づいて決定される。
その所有者に対して課せられる。課税標準は、台帳賃貸価額から50%の概算経費控除をして、その後さらに一定の居住用不動産について30%の控除をしたものである。
主に農地に対して課税される。これは土地の所有者、使用収益権者に対して課税される。台帳賃貸価額から概算費用控除20%を行ったものが、課税標準となる。
事業用不動産について、個人、法人の利用者に対して課税される。
保有する不動産の資産価値(1月1日時点)が130万ユーロ超の場合、次の不動産富裕税が課税される。
1996年3月に発効した「二重課税防止に関する日仏協定」について、日仏政府は2007年1月に改定議定書に署名、同年12月に発効した。これにより、配当、利子、使用料など投資所得に対する源泉地国における課税が軽減・免除された。
NNA調べ(2016年11月)
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る フランス税制」
外国人や外国企業はは原則自由に土地・不動産を所有することができ、規制を受けない。
ただし、不動産投資において1,500万ユーロを超える直接投資に該当する場合は、フランス銀行(中央銀行)に届け出る必要がある。
原則、労働許可がなければフランスでは就労できない。
就労のためフランスに滞在する場合は、事前に在日フランス大使館で就労ビザを取得する必要がある。
短期滞在ビザ(90日以下)と長期滞在ビザ(90日超)がある。
原則、外国人は自由に不動産の売買ができる。
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る フランス 外資に関する規制」(2018年1月15日)
全国で約7000の不動産業者が加入する業者組合であるFNAIMが、各不動産業者の売出情報や成約情報をデータベース化している。
また、French-Property.comでもフランス各地の物件情報などを閲覧することができる。
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る 投資コスト比較」
NNA調べ(2016年11月)
※データベースについては、関係機関等から収集した情報を掲載しており、必ずしも正確性または完全性を保証するものではありません。掲載情報の詳細については、出典元にお問い合わせいただくようお願いいたします(掲載情報以外の内容については、国土交通省としてお答えできません)。また、閲覧者が当データベースの情報を用いて行う一切の行為について、国土交通省として何ら責任を負うものではありません。