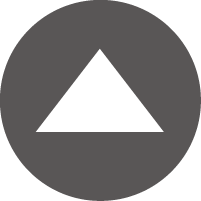- アジア・中東
- 北米・中南米
- 欧州・アフリカ・大洋州

カナダ政府は3月27日、2023年1月1日に施行した「カナダ人以外による住宅用不動産の購入禁止に関する規則」の改正を発表した。就労許可保持者に対する購入禁止要件を緩和するとともに、国内の住宅供給不足問題に対処すべく、カナダ人以外による宅地開発を目的とした住宅用地の購入を認める例外規定を設けた。加えて、住宅と複合用途に区画された全ての土地を購入禁止とする規則を撤廃し、それらの用途に区画された空き地のカナダ人以外による購入を認めたほか、法人が外国人によって支配されると定義する閾値を3%から10%に増加した。規則の改正は同日付で施行した。
政府は、オフショア資金の流入によって大都市圏の住宅価格が上昇したことから、2022年4月の予算案で外国人によるカナダでの非レクリエーション用の住宅用不動産購入を2年間禁止する法規制の整備を発表し(2022年4月12日記事参照)、2023年1月1日から2年間の期限付きで購入禁止措置を導入していた。
しかし、新規則の適用によって外国資本の宅地開発業者が新規住宅建設事業を中止せざるを得なくなったり、住宅や複合用途に区画された土地の商業開発が滞ったりするなど、意図せずに商業用不動産の取引や開発に支障を来す事例が明らかになり、業界団体からは規則改正を望む声が上がっていた。
土地所有権の確認および所有権登記は、州の土地登記制度を使って行われている。
● 2023 年 1 月 1 日より、カナダ人以外による住宅用不動産の購入禁止法(Prohibition on the Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act)および施行規則に基づき、2 年間の時限措置として、カナダ人以外は、カナダ国内の住宅用不動産を直接的または間接的に購入することが禁じられた。この禁止措置は、同法およびその施行規則が定める条件に基づき、特定の自然人には適用されない。これらの自然人に含まれるのは、移民・難民保護法(Immigration and Refugee Protection Act)に基づく難民、所定の条件を満たす一時居住者、および母国で迫害を受ける恐れのある者である。
● カナダ人以外の購入者および投資家は、カナダの住宅用不動産にかかわる取引については慎重を期し、必要に応じて法的助言を求めることが望ましい。
・不動産の登録は公共の信頼に似たものであり、登録された所有者は不動産や土地の譲渡が可能。登録手続きは、公共サービスを提供する特定機関や弁護士を通じて実施される。
・カナダでは外国籍のメンバーに対しても比較的に柔軟な対応がなされており、不動産投資の面においては平等な機会が与えられており、特に不動産登録における簡便な手続きが魅力である
・注意すべき点は、アメリカと同様に、州により不動産の規定が異なる
・また、生活水準が高く、不動産市場のインフレーションに気を付けるべきである。特に、これらの地域に居住する農家や移住した農業従事者は、原材料や建築物のインフレ率によって大きな影響を受けている
・土地所有権の取消しや賃貸契約の停止、が時折発生しており、その割合は外国籍の方に限っては50%以上と比較的高い水準にある
・土地の取得手続きは容易であるものの、インフレーションにより資産の維持には相当な負担が伴う
鑑定士が国家資格ではないカナダでは、The Appraisal Institute of Canada (The AIC)が鑑定関連の主要な団体として存在し、約4,500人の会員がいる。このThe AIC が独自基準としてCanadian Uniform Standards of Professional Appraisal Practise (CUSPAP)を定めており、国内で広く認識されている(鑑定士が国家資格でないこともあって必ずしも法的に強制適用されるものではない)。The AIC は IVSをレビューし、AIC会員がCUSPAPに従っていればIVSに整合した評価レポートを作成できるようにCUSPAPの修正を行っている。従ってCUSPAPはIVSへのコンバージェンスが非常に進んでいると言える。
不動産業界におけるキャリアに必要な教育およびライセンス要件は、州の規制当局によって定められている。大学では、不動産関連のさまざまなコースが提供されている。州でライセンスを取得すると、地元の委員会やCREAのメンバーになることができる。ライセンス要件はカナダ各地で異なるが、すべての州と準州で将来のセールスマンやブローカーは試験に合格する必要がある。多くの州と準州では、不動産の専門家が最新の問題などを把握できるように、継続教育が義務付けられている(その他の州と準州でも受講可能である)。
〔不動産関連法・制度の現状〕
日本貿易振興機構(JETRO)「政府、カナダ人以外の住宅用不動産購入禁止規則を改正」
〔土地・不動産の所有権〕
日本貿易振興機構(JETRO)「カナダにおける事業運営および資金調達ガイド-2024 年改訂版-」
〔土地・不動産の登記〕
PwCコンサルティング合同会社調べ(2024年11月)
〔不動産の鑑定評価〕
公益財団法人 日本不動産鑑定士協会連合会「各国の国際評価基準(IVS)導入状況」
〔不動産事業を行う際の免許制度〕
Canadian Real Estate Association (CREA) 「Become a REALTOR」
不動産業界でのキャリアに必要な教育およびライセンス要件は、州の規制当局によって定められている。大学でも、不動産関連のさまざまなコースを提供している。州でライセンスを取得すると、地元の委員会やCREAのメンバーになることができる。ライセンス要件はカナダ各地で異なるが、すべての州と準州で、将来のセールスマンやブローカーは試験に合格する必要がある。多くの州と準州では、不動産の専門家が最新の問題などを把握できるように、継続教育も義務付けられている(その他の州と準州でも受講可能)。
カナダは、政府の権力と責任が連邦政府と州政府の間で分担される「連邦国家」であり、消費者の相談、苦情に対しては、製品・サービスによって連邦政府、もしくは州政府に管轄が分かれ、それぞれ担当の政府機関が対応する。なお、準州の権力は、州に比べて限定的であるが、近年自治の範囲が広がってきている。
カナダ政府の関与は少なく、公的団体であるCanada Mortage and Housing Corporation (CMHC)が住宅購入者に住宅融資保険を提供。発足当初は任意での制度だったが、現在では10州中5州、人口の8割程度の地域で州法により付保が義務付けられている。保証事業者には、他に民間の事業者も参入している。
CMHC はカナダの住宅制度の健全化に貢献している。住宅金融ソリューションを提供し、貸し手に住宅ローン資金への信頼できるアクセスを提供している。
公的団体であるCanada Mortage and Housing Corporation (CMHC)より、住宅ローン保証や低所得者向けの住宅支援が行われている。
住宅ローンが借りられるか否かは、保険市場で9割のシェアを持つ公的団体であるCanada Mortage and Housing Corporation (CMHC)の基準に合致するかが判断基準となっている。
賃貸契約の解除については、独自の賃貸法を持っており、政府手数料である高額な罰金が求められるケースがある。
〔不動産を取引する際の制度〕
Canadian Real Estate Association(CREA)「Become a REALTOR」
〔消費者保護、住宅保証・保険制度・不動産行政の方向性〕
消費者庁「カナダ・消費者政策体制等に関する基本的事項」
Canada Mortgage and Housing Corporation
〔不動産金融〕
PwCコンサルティング合同会社調べ(2024年11月)
〔不動産のリース〕
PwCコンサルティング合同会社調べ(2024年11月)
カナダの固定資産税は、全ての州において土地・建物に課税される。多くの州において償却資産に課税されるが、その取扱いは州によって様々であり、オンタリオ州では製造業や農業等で利用される機械設備は課税されない。課税ベースは資産の市場価値(market value)を示す資産評価額である。多くの州において資産を評価するのは州政府や独立した州機関である。市町村が州の標準的な評価マニュアルを使用して行う州もある。評価替えの期間は州によって様々であり、評価を毎年行う州もあれば、2年や3年おきに行う州もある。
固定資産譲渡税は、州もしくは市などの地方自治体が管轄している税金である。
日本との二国間租税条約がある。源泉税率は親子会社間配当5%または15%、利子は0%または10%以下、ロイヤルティーは10%以下となる。
〔不動産取得〕
一般財団法人自治体国際化協会「カナダの地方自治」(2024年6月)
〔不動産保有、その他の税制〕
Province of British Columbia「Property Taxes」
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る カナダ 税制」(2023年10月24日)
就労許可証(Work Permit)取得義務以外なし。
在留許可取得には、ほとんどのケースで事前に就労許可証の取得が必要。
不動産の売買や開発は州法の規制下に置かれる。
アルバータ州、サスカチュワン州、マニトバ州、ケベック州では、市民権または永住権を有しない人による農地などの土地所有は、一部制限されている。
またプリンス・エドワード・アイランド州では、非カナダ人を対象としたものではないが、同州非居住者、および同州法人を含めたカナダ国内外の法人による土地所有には制限がある。
カナダ国内での住宅価格高騰問題に対処するため、連邦政府は2023年1月1日から2年間の時限措置として「非カナダ人による住宅用不動産の購入禁止法および規則(the Prohibition on the Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act and Regulations)」を施行した。同法では、カナダ人以外によるカナダでの住宅用不動産購入を禁止するとともに、法人やその他の団体を利用した購入禁止回避を制限し、違反に対する罰則を設定する。禁止事項に違反し有罪判決を受けた場合、1万カナダ・ドル以下の罰金に処される。
2023年3月に同規則の一部が即日緩和、施行され、就労許可証保持者が同購入禁止規則の適用対象外となるためには、[1]住宅購入時にカナダの就労許可証の有効期間が183日以上残っている、[2]カナダで住宅用不動産を複数購入していない(つまり、購入が認められるのは住宅用不動産1軒のみ)の2点を満たす必要がある。つまり、就労許可証保持者は、住宅用不動産購入時に就労許可証の有効期限が183日以上残っていれば、1軒のみ購入が認められる。
〔外国人による不動産の取引について〕
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る カナダ 外資に関する規制」(2023年11月28日)
174.07~945.77米ドル
8.24~82.39米ドル/月
管理費込み(電気代、駐車場代別)
管理費込み(電気代、駐車場代別)
〔主要都市等におけるマーケット情報〕
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別情報 投資・コスト比較」(2024年11月)
〔取引履歴・物件情報などのデータベース化〕
PwCコンサルティング合同会社調べ(2024年11月)
※データベースについては、関係機関等から収集した情報を掲載しており、必ずしも正確性または完全性を保証するものではありません。掲載情報の詳細については、出典元にお問い合わせいただくようお願いいたします(掲載情報以外の内容については、国土交通省としてお答えできません)。また、閲覧者が当データベースの情報を用いて行う一切の行為について、国土交通省として何ら責任を負うものではありません。