よくあるご質問
- 自賠制度と制度改正について
- 自賠責保険・共済について
- 政府保障事業について
- 請求に関するよくある質問
- 自賠責保険金(共済金)に
関するよくある質問 - 損害保険会社(組合)が決定した
自賠責保険金(共済金)に不服が
ある場合に関するよくある質問 - 国土交通大臣に対する
申出制度について - 契約に関するよくあるご質問
- 譲渡・引っ越しなどに関する質問
- 解約に関するよくある質問
- 紛失に関するよくある質問
- 国土交通省における
無保険車対策(警告はがき)に
関するよくある質問 - 類似サイトについて
- 政府保障事業への請求に
関すること - 政府保障事業の債権回収に
関すること
自賠制度と制度改正について
Q1. 「自動車損害賠償保障制度」とはどのようなものですか?
A.1 「自動車損害賠償保障制度」は、自賠責保険・共済と被害者等への支援・事故防止対策が相まって、相互に補完し合うことで、自動車事故による被害者を支えるとともに、自動車事故で苦しむ人を一人でも減らす取組みを進め、安全な交通社会の実現を目指しているものです。
Q2. どの法律に基づいて実施されますか?
A.2 令和4年6月15日に公布された「自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第65号)」により改正された自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づいて実施されます。
Q3. 「自賠責保険・共済〔強制保険〕」とは、どのようなものですか?
A.3 交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を担保することにより、最低限の対人賠償を確保することを目的とした保険(共済)であり、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車(※)に加入が義務付けられているものです。
(※)なお、農耕用小型特殊自動車(農耕トラクタや田植機等で時速35km未満のもの)は自賠責保険の対象外です。
Q4. 政府が行っている「自動車損害賠償保障事業(通称「政府保障事業」)とはどのようなものですか?
A.4 政府が行っている政府保障事業は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険・共済の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険(共済)事故」にあわれた被害者に対し、自動車損害賠償保障法施行令で定められている金額の範囲内で、健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付(他法令給付)や加害運転者等本来の損害賠償責任者の支払によっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、政府(国土交通省)がその損害を塡補する(支払う)制度です。 なお、この損害の塡補は、本来の損害賠償責任者に代わって、被害者に立替払いをするものですので、その支払金額を限度として、政府が本来の損害賠償責任者である加害運転者等に対して求償いたします。
Q5. 国土交通省では、被害者やその家族、遺族の方を対象としたどのような支援を行っているのですか?
A.5
国土交通省では、自動車事故被害者やその家族、遺族の方への支援として、(独)自動車事故対策機構(ナスバ)とともに、遷延性意識障害(脳損傷により自力移動等が不可能な状態)の方を対象とした自動車事故被害者専門の病院の設置・運営、在宅療養の方のための介護料の支給、介護者なき後の生活の場を確保するための環境整備に向けた支援、脊髄損傷や高次脳機能障害(脳損傷による記憶障害等により日常生活に制約がある状態)を負われた方の社会復帰に向けた支援、交通遺児等への生活資金の融資等を行っています。詳細については、以下のリンク先をご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/jikotai/victim_support/index.html
Q6. 国土交通省では、事故防止対策としてどのような取組みを行っているのですか?
A.6
国土交通省では、自動車事故を未然に防ぐための対策として、(独)自動車事故対策機構(ナスバ)とともに、自動車の安全性能を評価する「自動車アセスメント」を実施しているほか、自動車運送事業者に対する先進安全自動車(ASV)やドライブレコーダー等の導入支援に取り組んでいます。詳細については、以下のリンク先をご確認ください。
【自動車アセスメント】
https://www.nasva.go.jp/mamoru/about/about.html
【先進安全自動車(ASV)の導入支援】
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/01asv/index.html
【ドライブレコーダー等の導入支援】
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/jikoboushi.html
Q7. 「自賠責保険に含まれる賦課金」とはどのようなものですか。また賦課金の単価はどのように決まるのですか?
A.7 すべての自賠責保険・共済に加入される皆様を対象に、自賠責保険料・共済掛金の一部としてお支払いいただくものです。賦課金のうち、従前よりご負担いただいている保障事業(「無保険(共済)事故」にあわれた被害者の方への支援)に充てられるものの単価は、用途・車種などによるリスク(事故が発生する頻度や被害の程度)の差異に応じ、将来、保障事業としてどのくらい支払うことが必要となるかを推測し、設定しています。令和5年4月より新たにご負担をお願いしている被害者支援等に充てられるものの単価は、被害者等に対する支援や事故防止対策にどのくらいの事業費が必要かを推測し、自動車の台数や用途・車種などによるリスクの差異を考慮した上で、設定しています。
Q8. 「自動車事故対策事業賦課金」は、どの会計で管理されることになるのですか?税金と一緒に管理されるのですか?
A.8
「自動車事故対策事業賦課金」は自賠責保険料・共済掛金と合わせて損害保険会社・組合に納付いただいたのち、損害保険会社・組合より国土交通大臣の管理する「自動車安全特別会計自動車事故対策勘定」に組み込まれ、管理されることとなります。
税金等の財源を管理する一般会計とは明確に区分の上、管理されますので、ご負担いただいた「自動車事故対策事業賦課金」はその趣旨・目的に即して、自動車事故被害者を支援するための対策や新たに自動車事故の被害にあわれる方を一人でも減らすための対策(事故防止対策)に活用しています。
Q9. 交通事故は減少しているのに、なぜこのタイミングで被害者支援等に充てる賦課金を設けることとしたのですか?
A.9 自動車事故は減少傾向にあり、自動車事故により亡くなられる方も大きく減少してきていますが、その一方で、常時の介護が必要となるような重度の後遺障害が残る方はこれらの減少と比較して、横ばいに推移しています。また、若年期に自動車事故の被害にあわれた方も相当数いるなど、今後も長期にわたって支援を必要とされる方が存在し続けることが見込まれます。一方で、その支援を継続していくための財源である積立金はこのままのペースでも15年ほど、早ければ10年ほどで枯渇してしまうおそれがあります。このような状況の中で、自動車事故の被害にあわれた方々の将来に対する不安を少しでも軽減するとともに、一日でも早く、自動車事故によって被害にあわれる方がいなくなる社会の実現を目指すため、賦課金を新設いたしました。
Q10. 自動車安全特別会計から一般会計に繰り入れたものがあるとのことですが、どのような経緯で繰り入れたのですか?一般会計から自動車安全特別会計に繰り戻されるのですか?
A.10
自動車安全特別会計(当時:自動車損害賠償責任再保険特別会計)から一般会計に平成6年度に8,100億円、平成7年度に3,100億円の合計1兆1,200億円が繰り入れられました。これは、バブル崩壊に伴う景気後退局面の中、赤字国債の発行をゼロとする目標を達成しつつ、税収減に伴う歳入不足を穴埋めするため、直ちに活用することが見込まれない特別会計に存する積立金を一時的に活用することにされたことに伴い、法律(※)に基づき、講じられた措置です。このときに一般会計に繰り入れられたものは、当該法律に基づき、後日、予算で定めるところにより自動車安全特別会計に繰り戻すことが法律上明記されており、令和7年度補正予算において5,741億円の全額繰戻しが措置されました。
(※)平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成6年法律第43号)、平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成7年法律第60号)
Q11. 全額繰戻しにより、被害者支援事業等はどうなりますか?
A.11 自動車事故が後を絶たない中、自動車事故の被害者支援事業等を安定的かつ継続的に行うことは極めて重要です。今回の全額の繰戻しにより、自動車安全特別会計の財政基盤が強化され、将来にわたって本事業を安定的に継続することができるようになります。ナスバが設置・運営する療護センターの老朽化対策等、更なる支援の強化を検討いたします。
Q12. 毎年度の繰戻しがなくなると事業の実施に必要な財源が無くなってしまうのではないですか?
A.12 5,741億円の全額繰戻しは、特別会計に関する法律等関係法令に基づき財政融資資金に預託(積立金)することとされています。預託による運用益収入や、令和5年4月の法改正により拡充した賦課金等を主たる財源として、被害者支援事業等を安定的かつ継続的に行うこととしています。
Q13. 全額繰戻しにより、自賠責保険料は下がりますか?
A.13 自賠責保険料は、ノーロス・ノープロフィットの原則のもと、金融庁において設置されている自賠責保険審議会において審査が行われ毎年の保険料が決定されています。なお、自賠責保険料は、①被害者の方にお支払いする自賠責保険金、②保険会社の経費等である社費により構成されています。他方で、今回の全額繰戻しは、交通事故被害者への支援事業等に充てられるものであり、自賠責保険料の引き下げに直接影響するものではありません。
Q14. 自動車ユーザーは税金や車検のための手数料などすでにさまざまな負担をしていますが、他の歳入を活用することはできなかったのですか?
A.14 自動車関係諸税、車検時の検査登録手数料等のご負担を自動車ユーザーの皆様にはお願いをしており、それぞれの使途・目的に応じて、必要な金額を設定しています。このため、それぞれの財源を自動車事故の被害者支援等に活用することはしないこととさせていただいております。
自賠責保険・共済について
Q1. 「自賠責保険・共済〔強制保険(共済)〕」とはどのようなものですか?
A.1 交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を担保することにより、最低限の対人賠償を確保することを目的とした保険(共済)であり、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車(※)に加入が義務付けられているものです。
(※)なお、農耕用小型特殊自動車(農耕トラクタや田植機等で時速35km未満のもの)は自賠責保険の対象外です。
Q2. 「自賠責保険・共済〔強制保険(共済)〕」で支払われる損害と限度額は、いくらですか?
A.2 自賠責保険・共済で支払われる支払限度額は、被害者1名につき、
傷害による損害 120万円
死亡による損害 3,000万円
後遺障害による損害 神経系統の機能又は精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、介護を要する後遺障害
・ 常時介護を要する場合(第1級)4,000万円
・ 随時介護を要する場合(第2級)3,000万円
上記以外の後遺障害
・ (第1級)3,000万円 ~(第14級)75万円
注)限度額は等級別に定められています。
Q3. 「自動車保険(共済)〔任意保険(共済)〕」に加入していれば「自賠責保険・共済〔強制保険(共済)〕」はいらないのですか?
A.3 「自動車保険(共済)〔任意保険〕」では対人賠償に関し、「自賠責保険・共済〔強制保険〕」の補償範囲までは「自賠責保険・共済〔強制保険〕」による保険金の支払いが行われ、「自動車保険(共済)〔任意保険〕」は「自賠責保険・共済〔強制保険〕」の補償範囲を超えた部分に限って、保険金の支払いが行われております。従って、任意保険(共済)に加入していれば自賠責保険・共済は不要、ということではありません。
このため、仮に自賠責保険・共済を「任意保険(共済)と一本化」する場合、
■ 自賠責保険・共済の補償範囲までを新たに任意保険(共済)でカバーする必要があるため、自賠責保険・共済の保険料率(共済掛金)が上昇し、自動車ユーザーに負担増を強いる可能性
■ 事故リスクが高いユーザーほど保険料率(共済掛金)が大幅に上がり、無保険車が増加する可能性
があり、被害者保護に支障が生じる可能性があることから、現行制度の仕組みが適当であると考えております。
Q4. すべての者が「自動車保険(共済)〔任意保険(共済)〕」に加入している訳ではない中、「自賠責保険・共済」の補償内容を充実させて、「自動車保険(共済)〔任意保険(共済)〕」加入しなくていいようにしたらいいのではないですか?
A.4 自賠責保険・共済は強制保険であることに鑑み、補償範囲を対人賠償に絞り込み、かつ、最低限必要な補償内容とすることで、自動車を保有する誰もが加入しやすい(=抑制した最低限の保険料)制度としています。
自賠責保険の「補償内容を充実」させる場合、
■ 保険料率が上昇し、自動車ユーザーに負担増を強いる可能性
■ 事故リスクが高いユーザーほど保険料率が大幅に上がり、無保険車が増加するおそれ
があり、被害者保護に支障が生じる可能性があることから、現行制度の仕組みが適当であると考えております。
政府保障事業について
Q1. 政府が行っている「自動車損害賠償保障事業(通称「政府保障事業」)とはどのようなものですか?
A.1 政府が行っている政府保障事業は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険・共済の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険(共済)事故」にあわれた被害者に対し、自動車損害賠償保障法施行令で定められている金額の範囲内で、健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付(他法令給付)や加害運転者等本来の損害賠償責任者の支払によっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、政府(国土交通省)がその損害を塡補する(支払う)制度です。
なお、この損害の塡補は、本来の損害賠償責任者に代わって、被害者に立替払いをするものですので、その支払金額を限度として、政府が本来の損害賠償責任者である加害運転者等に対して求償いたします。
Q2. 「政府保障事業」と「自賠責保険・共済〔強制保険(共済)〕」は何が違うのですか?
A.2 政府保障事業による塡補金(支払額)は、自賠責保険・共済の支払基準に準じて支払われます。しかし、政府保障事業は、自賠責保険・共済では救済されない被害者の最終的な救済制度であることから、次のような点が自賠責保険・共済とは異なります。
①請求できるのは被害者のみです。加害者から請求はできません。
②健康保険、労災保険などの社会保険からの給付を受けるべき場合、その金額は差し引いて塡補します。
③被害者への塡補額については、政府がその支払金額を限度として、加害者(損害賠償責任者)に求償します。
詳しくは以下、URLをご確認をお願いいたします。
なお、政府保障事業への請求は損害保険会社(共済組合)で受け付けていますので、詳しくは損害保険会社(共済組合)の窓口におたずねください。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/jikotai/public_payment/index.html
Q3. その他、「政府保障事業」について不明な点はどこを見ればいいですか?
A.3 政府保障事業についてをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/public_payment/index.html
請求に関するよくある質問
Q1. 物損事故は自賠責保険・共済で補償されますか?
A.1 自賠責保険・共済の補償の対象は、人身事故による損害のみです。車両等の物的損害は対象になりません。
Q2. 物損事故に対する損害についてはなぜ、自賠責保険金が支払われないのでしょうか?
A.2 自賠責保険・共済は自動車損害賠償保障法に基づき、自動車の運行による人身事故の被害者を救済するため、全ての自動車に保険契約を義務づけ、損害賠償責任の履行を確保する事を目的にしている保険です。したがって、物損事故に対しては自賠責保険・共済から自賠責保険金が支払われることはありません。
Q3. 車の修理代は自賠責保険・共済からは支払われないのでしょうか?
A.3 車の修理代は支払われません。自賠責保険・共済は自動車の運行によって他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険です。自動車のみならず、洋服、自転車等の物的損害は支払の対象になりません。
Q4. 自賠責保険・共済に請求できるのはいつまでですか。時効はあるのですか?
A.4 加害者請求は被害者に賠償金を支払った日から3年以内です。被害者請求は事故が起こった日から3年以内です。ただし、死亡の場合は死亡日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日から、それぞれ3年以内です。何らかの理由で請求が遅れる場合は、各損害保険会社(共済組合)にお問い合わせ下さい。
※平成22年3月31日以前に発生した事故については、すべて3年ではなく2年となります。
Q5. 自賠責保険金(共済金)の請求方法には、どのようなものがありますか?
A.5 加害者から請求する方法(加害者請求)と被害者から請求する方法(被害者請求)があります。
<加害者請求>
加害者が被害者に損害賠償金を支払ったうえで、その領収証、その他必要書類を添えて自賠責保険金の請求を行います。
<被害者請求>
被害者が加害者の加入している損害保険会社(共済組合)に直接、必要書類を添えて損害賠償額の請求を行います。
Q6. 加害者側から賠償が受けられていないのですが、他に請求の方法はありますか?
A.6 加害者の加入している自賠責損害保険会社(共済組合)へ被害者の方が直接請求する方法があります。(被害者請求)
Q7. 自賠責保険・共済に被害者請求したいのですが、加害者の自賠責損害保険会社(共済組合)を調べるためには、どのようにしたら良いですか?
A.7 交通事故証明書に当事者の自賠責損害保険会社(共済組合)や証明書番号が記載されています。
同証明書は、事故が起きた場所を管轄する「自動車安全運転センター」が発行しています。同証明書の申請用紙は、最寄の警察署、派出所及び自動車安全運転センターに備え付けてあります。
申請方法等については、こちら(自動車安全運転センターのホームページ)をご覧ください。
Q8. 事故にあった被害者ですが、保険金の請求はどこにしたらいいですか?
A.8 加害者が加入している自賠責損害保険会社(共済組合)または任意損害保険会社(共済組合)に対して請求することができます。
Q9. 一括払いとは何ですか。またその役割は何ですか?
A.9 自賠責保険・共済と任意保険(共済)は、保険契約を異にするものであるため、保険金の請求に当たっては、自賠責保険・共済は自賠責損害保険会社(共済組合)に、任意保険(共済)は任意損害保険会社に、それぞれ請求することが原則ですが、被保険者の利便、被害者救済の迅速化を図るため、任意損害保険会社(共済組合)が自賠責保険金(共済金)を含めて被保険者等に一括して支払を行い、後日、任意損害保険会社(共済組合)が自賠責損害保険会社(共済組合)に対し請求を行う制度です。
Q10. 事故の相手が加入している任意損害保険会社(共済組合)と示談交渉をしています。自賠責保険・共済への請求はどうなるのでしょうか?
A.10 任意保険(共済)では、自賠責保険・共済の支払分もまとめて支払う「一括払制度」があり、被害者が自賠責保険・共済へ別途請求する必要はありません。なお、示談が難航している場合は、一旦交渉を打ち切り、被害者が自賠責保険・共済へ直接請求することもできます。
Q11. 事故にあいましたが、加害者の任意損害保険会社(共済組合)の担当者と意見が合いません。自賠責保険・共済に直接請求したいのですがどうすればよいでしょうか?
A.11 加害者の任意損害保険会社(共済組合)への一括払いを解除し、自賠責保険・共済に被害者が直接請求することもできます。しかし、任意損害保険会社(共済組合)等から既に支払われている治療費等は控除され、残りの損害について支払われることになります。また、既に支払われている額の合計が、自賠責保険の限度額を超えている場合は支払額が生じません。
自賠責保険金(共済金)に関するよくある質問
Q1. 自賠責保険・共済の支払額は、何に基づいて決められているのですか?
A.1 自動車損害賠償保障法の規定により、損害保険会社(共済組合)は、国土交通大臣及び内閣総理大臣の定める支払基準に従って自賠責保険金(共済金)を支払わなければならない旨定められています。
同支払基準は、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)(PDF)」によって定められています。
Q2. 自賠責保険金(共済金)の支払内容にはどのようなものがありますか?
A.2 自賠責保険・共済は人身事故の被害者を救済するため、自動車損害賠償保障法によって、原則としてすべての自動車に契約が義務づけられている保険(共済)です。支払内容は次のようなものがあります。
1. 傷害による損害
治療関係費、文書料、休業損害及び慰謝料を支払対象としており、支払限度額は被害者1名につき120万円まで。
2. 後遺障害による損害
後遺障害とは、事故によって身体、運動能力、労働能力に支障がでており、将来においても回復困難で、障害が残ると見込まれるものをいいます。
自賠責保険・共済においては、当該事故において、傷害が治ったときに残存する当該傷害と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的な障害の存在が医学的に認められる場合、後遺障害による損害について請求を行うことが可能です。後遺障害による損害は、医師の後遺障害診断書にもとづき一定の手続きのもと後遺障害として認定された場合に後遺障害等級に応じた金額が支払われます。
支払限度額は等級により被害者1名につき4,000万円(別表第一1級)から75万円(別表第二14級)まで。
3. 死亡による損害
葬儀費、逸失利益、死亡本人の慰謝料及び遺族の慰謝料を支払対象としており、支払限度額は被害者1名につき3,000万円まで。
Q3. 被害者の損害額が自賠責保険・共済の限度額を超えた場合は誰に請求するのでしょうか?
A.3 交通事故による不法行為の損害賠償責任は、当然に事故の加害者にありますので、自賠責保険・共済の支払限度額を超えた損害については事故の加害者(の契約する任意保険(共済))等に対して請求することになります。
Q4. 自賠責保険金(共済金)は被害者の過失の割合によって減額されますか?
A.4 被害者の過失割合が70%以上でなければ減額しないことになっています。
Q5. 被害者保護が目的の自賠責保険・共済でも支払われない場合がありますか?
A.5 交通事故の被害者救済が、自動車損害賠償保障制度の第1の目的ですが、自賠責保険・共済は、自動車の「運行」によって「他人」を死傷させ、加害者が法律上の損害賠償責任を負った場合の損害が対象となるため、次のような場合には対象とはなりません。
1. 加害者に責任がない場合(3条件すべて立証できる場合)
【3条件】
自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと
自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと
2. 自損事故で死傷した場合
3. 自動車の運行によって死傷したものでない場合
4. 被害者が「他人」でない場合
他人とは「自己」に対する反対の概念で、運行供用者及び運転者以外の者をいう。
運行供用者:「自己のために自動車の運行の用に供する者」をいう(法第2条第3項)。
運転者:「他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者」をいう(法第2条第4項)。
5.保険契約者、保有者または運転者の悪意によって損害が生じた場合
Q6. 事故が原因で収入が減少したのですが、補償はありますか?
A.6 休業損害として補償されます。原則として1日につき6,100円支払われます。これ以上に収入が減少した立証がある場合には、19,000円を限度としてその実額が支払われます。
損害保険会社(組合)が決定した自賠責保険金(共済金)に不服がある場合に関するよくある質問
Q1. 自賠責損害保険会社(共済組合)の決定した自賠責保険金(共済金)に納得できない場合、どのようにしたら良いですか?
A.1 自賠責損害保険会社(共済組合)の決定した自賠責保険金(共済金)に納得できない場合、損害保険会社(共済組合)に対して「異議申立」をすることができます。詳細については、請求された損害保険会社(共済組合)にお問い合わせください。
また、「異議申立」制度のほかに、「(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構」に対して、紛争処理の申請を行うことができます。同機構は、公正中立で専門的な知見を有する第三者である弁護士、医師及び学識経験者で構成する紛争処理委員が紛争処理委員会において調停を実施するものです。
Q2. 後遺障害の認定等級に不服がある場合はどうすればいいのでしょうか?
A.2 後遺障害等級認定に不服がある場合は、新たな立証資料を添付のうえ、損害保険会社(共済組合)に対して異議申立を行うか、(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構へ調停の申請を行うことができます。
さらに、(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構の調停結果に不服がある場合は、再度、損害保険会社(共済組合)に対して新たな立証資料を添付のうえ異議申立を行うか、訴訟を提起して裁判上で争う事になります。
(参考)
(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構
○問い合わせ
0120-159-700
○ホームページ
https://www.jibai-adr.or.jp/
Q3. 自分は事故の加害者ですが、加害者が「被害者の事故による損害」を認めていないにもかかわらず、被害者へ自賠責保険金(共済金)が支払われているのは納得がいかないのですが。
A.3 自動車損害賠償保障制度は、被害者保護を目的として制定された制度です。自動車損害賠償保障法により被害者請求が認められており、被害者は、自動車の運行によって損害(人身)が発生したという事実のみを主張すればよいこととされています。よって、被害者に損害の発生した事実があり、証拠書類の提出により損害が立証される場合は、自賠責保険金(共済金)が支払われることになります。
Q4. 交通事故の相手方と訴訟係属中なのですが、後遺障害等級の認定を留保されています。なぜですか?
A.4 訴訟の内容にもよりますが、訴訟において後遺障害の等級が争点となっている場合や、事故と症状との相当因果関係が争点となっている場合、等級等は訴訟の中で明らかにすべきものです。したがって、係争中であれば、後遺障害等級の認定を留保せざるを得ません。なお、判決が確定すれば、自賠責保険・共済もその内容に従い支払できるものがあれば支払を行います。
Q5. 後遺障害等級認定を受けてから症状が悪化しました。どうすればいいのでしょうか?
A.5 後遺障害の悪化や新たに高次脳機能障害と診断されたことなどにより、既認定等級より重いものになった場合は、請求者が診断書やレントゲン写真など医学的な立証資料等を添付の上、損害保険会社(共済組合)に申請することが可能です。
Q6. 後遺障害症状固定後も治療を続けていますが、治療費は認定されるのでしょうか?
A.6 後遺障害の症状固定は、傷害が治ったときに、障害が残存していると医師が判断した場合になされるもので、これを後遺障害として等級を認定し、自賠責保険金(共済金)が支払われます。
したがって、後遺障害症状固定後の治療費については認定されません。
国土交通大臣に対する申出制度について
Q1. 国土交通大臣に対する申出制度について教えてください。
A.1 被害者または自賠責保険・共済契約者は、損害保険会社(共済組合)による自賠責保険金(共済金)の支払が支払基準に違反し、または支払基準の概要などの情報提供について、損害保険会社(共済組合)が書面の交付により適正な情報提供手続を行っていないと認めるときは、自動車損害賠償保障法第16条の7(国土交通大臣に対する申出)に基づき、国土交通大臣に対し、その事実を申し出ることができます。
国土交通大臣は、被害者または保険(共済)契約者からの申出に対して、損害保険会社(共済組合)が支払基準に従った自賠責保険金(共済金)の支払をしていない、または適正な情報提供手続に従っていないと認める場合には、自動車損害賠償保障法第16条の8(指示等)に基づき、損害保険会社(共済組合)に対して必要な指示を行います。
契約に関するよくあるご質問
Q1. 車やバイクを保有し運転するときは、自賠責保険・共済に加入しなければなりませんか?
A.1 自賠責保険・共済は、自動車損害賠償保障法により加入が義務づけられています。
Q2. 自動車保険(任意保険)で「対人無制限」や「ファミリーバイク特約」の契約をしているのですが、自賠責保険・共済は契約しなくても良いのでしょうか?
A.2 自賠責保険・共済は、自動車損害賠償保障法により加入が義務付けられており、「ファミリーバイク特約」や「対人無制限」の自動車保険(任意保険)に加入していたとしても、自賠責保険・共済に加入しなければなりません。
自賠責保険・共済に加入せず、自動車保険(任意保険)のみしか契約せずに運行し、事故を起こしてしまった場合には、自賠責保険・共済の支払限度額を超えた分についてしか支払われません(自賠責保険・共済で支払われる保険金(共済金)の限度額までは自分で支払うことになります。)ので、十分にご注意下さい。
Q3. 自賠責保険・共済の契約をしたいのですが、どこで契約できるのですか?
A.3 自賠責保険・共済の取扱いを行っている各損害保険会社(共済組合)の支店等窓口や代理店で契約することができます。
また、排気量が250CC以下のバイク(検査対象外軽二輪と原動機付自転車)等については、郵便局(簡易郵便局など一部の局を除く)、一部のコンビニエンスストアでも契約することができる ほか、一部の会社ではインターネットで契約することができます。
手続方法の詳細や必要書類については、契約を希望される損害保険会社(共済組合)、もしくは代理店等にご確認下さい。
Q4. 契約者が負担する自賠責保険料は誰が決めているのですか?
A.4 自賠責保険・共済の損害調査等を行っている損害保険料率算出機構において、交通事故発生の状況や保険金(共済金)支払額の状況等を踏まえた自賠責保険・共済収支の将来推計に基づき、次年度以降の保険料が算出され、金融庁に届出が行われます。
これを受け金融庁は、自動車損害賠償責任保険審議会に諮問を行い、審議の結果を受け、改定が行われる場合には、保険料の告示を行います。
譲渡・引っ越しなどに関する質問
Q1. 引っ越したのですが、住所変更の手続きはどこに行けばいいのでしょうか?
A.1 住所変更手続きは、契約されている損害保険会社(共済組合)の窓口で行っています。
手続きには自賠責保険・共済証明書等が必要となります。手続方法の詳細や必要書類については、契約されている損害保険会社(共済組合)にご確認下さい。(連絡先は、自賠責保険・共済証明書の下欄に記載してあります。)
Q2. 自動車(バイク)を譲渡するのですが、自賠責保険・共済で必要となる手続きを教えてください。
A.2 契約者変更(権利譲渡)の手続きが必要となります。また、手続きは、契約されている損害保険会社(共済組合)の窓口で行っています。
手続きには自賠責保険・共済証明書等が必要となります。手続方法の詳細や必要書類については、契約されている損害保険会社(共済組合)にご確認下さい。(連絡先は、自賠責保険・共済証明書の下欄に記載してあります。)
Q3. 中古車を購入したのですが、自賠責保険の取り扱いを教えてください。
A.3 中古車の譲渡等により、車両の所有者が変わり、自賠責保険・共済証明書の記載事項に変更があった場合には、速やかに契約されている損害保険会社(共済組合)において、証明書の記載事項を変更する必要があります。
手続きには自賠責保険・共済証明書等が必要となります。手続方法の詳細や必要書類については、損害保険会社(共済組合)までご確認下さい。(連絡先については自賠責保険・共済証明書の下欄に記載してあります。)
Q4. 自動車(バイク)を友人から譲り受けた場合、名義変更しないと保険金が支払われないのですか?
A.4 自賠責保険・共済の保険金(共済金)については支払われますが、自賠責保険・共済証明書の記載事項に変更があった場合には、速やかに契約されている損害保険会社(共済組合)において、証明書の記載事項を変更する必要があります。
手続きには自賠責保険・共済証明書等が必要となります。手続方法の詳細や必要書類については、損害保険会社(共済組合)までご確認下さい。(連絡先については自賠責保険・共済証明書の下欄に記載してあります。)
Q5. 名義変更をせずに車両を運行した場合、どうなるのでしょうか。
A.5 名義変更(自賠法第7条第2項に基づく自賠責保険・共済証明書の記載事項変更)を行わない場合、必要な通知が届かない、保険金支払いの際の手続きが複雑になるなどトラブルが起こる可能性がございますので、必ず変更するようにお願いいたします。また、自賠責保険証明書を備え付けずに運行した場合、自動車損害賠償保障法に基づき30万円以下の罰金となります。
解約に関するよくある質問
Q1. 車(バイク)を廃車(一時抹消も含みます)した場合、自賠責保険・共済はどのような手続きをすれば良いのですか?
A.1 契約されている損害保険会社(共済組合)の窓口(代理店ではできません)にて解約の手続きが可能です。
手続きには自賠責保険・共済証明書等が必要となります。手続方法の詳細や必要書類については、契約されている損害保険会社(共済組合)にご確認下さい。(連絡先は、自賠責保険・共済証明書の下欄に記載してあります。)
※保険(共済)契約については廃車した時点ではなく、損害保険会社(共済組合)にて手続きをして頂いた時点で初めて解約することとなりますので、十分にご注意下さい。
(保険料には損害保険会社(共済組合)の手数料が含まれており、返戻金額は手数料や保険期間を勘案した額となります。(仮に保険期間が始まる前に解約しても、全額の還付は受けられません。また、保険期間の残りが1か月未満の場合、解約返戻保険料はありません。)返戻金額等の詳細につきましては、損害保険会社(共済組合)にご確認ください。)
紛失に関するよくある質問
Q1. 自賠責保険・共済証明書を紛失したので、再発行をしてほしいのですが、どうすれば良いのですか?
A.1 再発行の手続きについては、契約者本人が契約された損害保険会社(共済組合)の窓口(代理店はできません)で行う必要があります。
お手続きには身分証明書等が必要となります。手続方法の詳細については、契約されている損害保険会社(共済組合)にご確認下さい。
国土交通省における無保険車対策(警告はがき)に関するよくある質問
Q1. 国土交通省から「自賠責保険・共済契約期間は切れていませんか?」というハガキが送られてきましたが、どうしたらいいのでしょうか?
A.1 国土交通省では、自賠責保険・共済契約期間を過ぎても、新たな契約を確認できないバイクの契約者に対して、警告ハガキをお送りし、無保険(共済)車ではないか注意喚起しています。
該当のバイクがお手元にあり、かつ、使用されている場合は、至急、自賠責保険・共済の契約手続をお願いします。
契約手続は、損害保険会社だけでなくバイク店、自動車整備工場、郵便局、コンビニエンスストア等で行うことができます。また契約の際には、旧自賠責保険・共済証明書又は購入時の書類等を持参してください。
バイクを知人等に譲渡した場合は、譲られた方が無保険(共済)のまま運行されている可能性がありますので、連絡が可能であれば、自賠責保険・共済の加入について伝えていただきますようお願いします。
バイクを既に廃車済、バイク店などに引き取ってもらった場合は、返信はがきの該当欄に廃車等の時期をご記入いただき、返信をお願いします。
Q2. バイクを廃車したのですが、無保険であるとハガキが送られてきました。なぜですか?
A.2 250CC以下のバイクについては、各市区町村や運輸支局等で廃車の手続きをしても、その情報を各損害保険会社(共済組合)で把握することができません。
無保険(無共済)車の可能性がある危険状態を少しでも回避するためのものですので、ご理解下さい。
Q3. 既に自賠責保険を契約(更新)しているのですが、無保険であるとはがきが送られてきました。なぜですか?
A.3 保険契約の締結から国土交通省のシステムへの反映まで約2ヶ月かかるため、行き違いでハガキをお送りする場合がございますので、ご理解ください。 また、ご契約の車両情報が当方で把握しているものと異なる場合、システムが契約継続をしていないと判断し、ハガキをお送りしております。その場合、ご契約の車両情報が誤っている可能性がございますので、保険証書をご確認ください。誤りがあった場合は、損害保険会社へ訂正のお手続きをお願いします。
なおハガキが届きましたら、加入状況把握のため、誤りの有無に関わらず、現在の保険契約の情報を返信ハガキにご記入いただき、ご返信ください。
Q4. 無保険車で運行した場合の罰則規定について教えてください。
A.4 自賠責保険・共済に加入しないで自動車を運行すると、自動車損害賠償保障法に基づき1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金及び道路交通法に基づき違反点数6点となり、免許停止の処罰の対象となります。また、自賠責保険・共済標章(ステッカー)を表示しないで運行した場合も30万円以下の罰金の処罰の対象となります。
類似サイトについて
Q1. jibai.jpというドメインのサイトがありますが、国土交通省自賠責ポータルサイトと関係がありますか。
A.1 当該ドメインは、過去に国土交通省が使用していましたが、現在は使用しておらず、当該サイトは国土交通省とは全く関係がございません。
ご利用にあたっては、ご注意くださいますようお願い申し上げます。
政府保障事業への請求に関すること
Q1. 「ひき逃げ事故」(又は「無保険(共済)事故」)にあって、政府保障事業への請求を考えているのですが、先ず何をしたらよいのでしょう?
A.1 自動車事故にあわれたら、直ぐに警察に人身事故として届け出て下さい。警察に届け出ていないと、交通事故証明書(自動車安全運転センター)が発行されず、人身事故にあった事実を証明するものがないため、損害塡補を受けられない場合があります。
Q2. 自動車事故による治療の場合は、健康保険が使えないと聞いているのですが本当ですか?
A.2 自動車事故によるケガで治療を受ける時でも、健康保険等の社会保険や労災保険を使用することができます。特に、「ひき逃げ事故」や「無保険(共済)事故」にあわれた場合は、医療機関に対し「ひき逃げ(又は無保険)による事故のため自賠責保険・共済が使えないので、健康保険(又は国民健康保険等の社会保険。業務中や通勤途中での事故の場合は労災保険)で治療して下さい。」と申し出て下さい。
さもないと、被害者の損害額が政府保障事業の法定限度額を超えるような場合は、超過部分が全額自己負担となってしまう可能性があります。したがって、必ず社会保険を使用するよう病院に申し出て下さい。
Q3. バイクのひったくりにあい、身に付けていたハンドバッグを掴まれた際に転倒して怪我をしてしまいましたが、この場合は政府保障事業の対象となりますか?
A.3 ご質問の場合のように、自動車の運行によるものと認められるような場合は、政府保障事業の対象となります。
Q4. 請求に必要とされている書類は、全て提出しなければならないのですか?
A.4 政府保障事業へ損害塡補請求を行う場合は、法令により請求に必要な書類を提出することが義務付けられています。これらの請求関係書類をご提出いただけない場合は、損害の事実を確認できないため、政府保障事業から損害の一部又は全部の塡補ができない場合がありますので、ご注意下さい。
Q5. ひき逃げ(又は無保険)事故にあったため、自分が加入してる人身傷害補償保険に請求したところ、先に政府保障事業に請求して損害塡補を受けなさいと言われたのですが、ひき逃げ(又は無保険)事故の場合は、先に政府保障事業に請求しなければならないのですか?
A.5 そんなことはありません。どちらを優先するかは請求者の自由意志です。ただし、両方からの重複支払はありません。
政府保障事業は、他の手段によって救済されない被害者に対し、必要最小限の救済を図ることを目的として創設された制度であり、被害者が人身傷害補償保険のような実損塡補型傷害保険など他の手段によって救済される場合は、その限度において被害者に対する損害の塡補を行いません。つまり、政府保障事業では、人身傷害補償保険の保険金(共済金)については、被害者の損害額から控除することとしていますので、二重支払は受けられません。
政府保障事業の債権回収に関すること
Q1. 政府保障事業債権とは、どのような債権でしょうか?
A.1 自動車損害賠償保障法第5条の規定に基づき、自動車を運行する場合に締結する必要がある自賠責保険・共済を締結せずに自動車を運行し、人身事故を起こした場合には、本来であれば自賠責保険・共済から事故の被害者に対して保険金(共済金)が支払われることになりますが、これを締結せずに運行した場合には、自賠責保険・共済の保険金(共済金)が支払われません。
そのため、事故の被害者は、十分な救済を受けることができないことから、国が、自動車損害賠償保障法第72条の規定に基づき、事故の加害者にかわって、被害者に対して事故による損害にかかる治療費、慰謝料等の保障金(以下「損害のてん補」といいます。)を支払う政府保障事業があります。
政府保障事業により、被害者に対して損害のてん補を行った場合には、自動車損害賠償保障法第76条の規定に基づき、被害者が損害賠償の責任を持っている者(加害者等)に対して持っている権利(損害賠償請求権)を国が取得し、求償することとされています。
Q2. 納入告知書が送達された時点で既に、納付期限(履行期限)が過ぎているのですが、どうしてでしょうか?
A.2 納入告知書では、国が被害者に対して損害のてん補を行った日(保障金を被害者に支払った日)を納付期限(履行期限)としています。
Q3. 政府保障事業債権を弁済しないまま放置しておくと、どうなりますか?
A.3 政府保障事業債権について弁済をしない場合には、政府保障事業債権の債務者を相手に国が損害賠償請求訴訟を裁判所へ訴えることになります。
その後、裁判所での判決結果に従い、政府保障事業債権の債務者が所持している自動車、土地や建物、債務者が給与所得者であれば雇用主より支払われている給与等について差押えを実施し、強制的に政府保障事業債権の回収を行うことになります。
不安の解消やサポートにご活用ください

交通事故にあったときには
国土交通省では、交通事故に遭われた方を対象に各種制度や手続きの周知・ご案内を目的に「交通事故にあったときには」と題したパンフレットを作成致しました。突然の交通事故により、抱える課題は時間の経過とともに変わっていきます。その時々の状況に応じてこの冊子の情報をご活用ください。
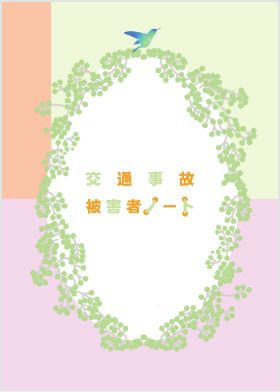
交通事故被害者ノート
国土交通省では、自動車事故にあわれた方々に少しでもお力添えできればとの思いから、自動車事故被害者ご本人やそのご家族などが、事故の概要等の記録を残していただくこと、警察や自治体、民間被害者支援団体などで行われている支援制度を知っていただくことなどを目的とした「交通事故被害者ノート」を作成しました。事故被害者皆様の不安の解消やサポートにつながることを願っております。